氷室零一2002BD企画SS
【最悪の日】
|
十一月六日の日暮れ前。
私は重い気持ちを抱えながら、私は靴を履いて昇降口を出た。
今日は朝から嫌なことばかりだ。
まず、昨晩にセットしたはずの目覚まし時計が鳴らなかった。電池切れで、時計の針が途中で止まっていたのである。お陰で朝食を食べ損ね、尽には「朝ぐらい、しゃんとしろよ」と馬鹿にされた。
登校すれば、朝のHR時に提出しなければいけないはずの進路調査のプリントを家に忘れていた。クラスで私だけが未提出だったので、担任の氷室先生に思いっきり冷たい目で見られてしまう。
そして各授業でも宿題を忘れていたり、指されても答えられなかったりと散々だった。
気晴らしの昼休みでさえ、家から持ってきたお弁当を床にぶちまける始末だ。仕方なく学生食堂で食べようとしたら、好きなうどんは売り切れていて、代わりに頼んだビーフカレーにはお肉が一つも入っていなかった。
おまけに……今日は憧れの氷室先生のお誕生日なので、他の教師の目を盗んでプレゼントを渡したら、『こんなものを用意する暇があったら、もっと勉学に励みたまえ。最近の君はたるんでいる』と言われてしまった。勿論、プレゼントは受け取ってもらえず、軽蔑めいたお小言まで浴びて、私の気持ちがどん底まで落ちたのは言うまでもない。
苦難は更に続く。
授業終了後の掃除では、男子が投げて遊んでいた雑巾が顔に当たるし、私が持っていたモップが壊れた。
放課後に図書室へ寄ったら、皆が静かに勉強や読書に励んでいるなか、大きな音を立てて顔からすっ転んだ。読みたかった小説の本は借りられていたし、机と椅子は全部埋まっていて、私は授業で出された課題の本を立って読む羽目になった。
暗くなってきたので下校しようとした時、まるで私の帰りを待っていたかのように雨が降り出した。折り畳み傘を教室に置いてあったので、わざわざ教室まで戻った。
そして今に至る。
「今日は散々だよ」
誰に言うでもなく、私は愚痴を吐いた。そうでもしなければやっていられない気分だった。
こんな日は早く寝てしまうに限る。家に帰ったらすぐに時計の電池を入れ直し、晩ご飯を食べ、お風呂に入った後は急いでベッドで眠ろう。
私は学園の正門を抜けた。細い道を、とぼとぼと歩いていく。辺りはすっかり闇が広がっており、道沿いにある電灯が淋しさを煽る。しかも雨がどんどん酷くなり、私の小さな傘は殆ど役に立っていなかった。
背後から車が近付いてくる音が耳に入った。私は白線内を歩いていたのだが、更に道の端に寄る。
ブロロロロ……と某有名国産車が私の横を通り過ぎた。
その瞬間! 何と、道路にあった水たまりの上を車のタイヤが通り、私は身を躱す暇もなく全身に泥水を被った。制服上下に加え、持っていた鞄と紙袋の荷物もぐしょぐしょだ。
「最低っ!」
暗い上に道幅が狭いので、車が水たまりを避けられなかったのは仕方がない。けれども、どうして私がこんな目に遭うのだ? 悲しくなった私はその場で立ち止まり、半泣きでポケットからハンカチを取り出して濡れた身体を拭いた。しかし元々雨で濡れている上に大量の水が掛かったものだから、全然意味が無い。スカートなど、手で絞れば水が出るほどだった。
私に水を浴びせた車が数メートル先の道端に止まる。右側のドアから運転者らしき人が傘を差してこちらに近付いてきた。暗いので顔がよく分からないが、背が高くて痩身の男性のようだ。
「すまない、濡れてしまったか?」
聞き覚えがある声に、私はハッとなって運転者を見た。何と、私の目の前にいるのは氷室先生ではないか。
「氷室先生」
「……君だったのか」
氷室先生は、私にハンカチを差し出した。しかし、その程度の布で拭いても仕方がないのは既に実証済みなので、有難く辞退する。今の私に必要なのは、大判のバスタオルなのだ。
「平気です。雨が酷いので拭いても拭かなくても一緒ですから、このまま濡れて帰ります」
「そうはいかない。風邪を引いたら大変だ。
家まで送っていくから、車に乗りなさい」
「えぇっ?」
思わず私は大声を出してしまった。過去に、嫌がる先生に無理矢理お願いして車に乗せてもらったことが数回あるが、先生からそう言ってきたのはこれが始めてだ。
しかも、私は全身濡れている。こんな状態でシートに座ったら大変だ。
「どうした?」
「いえ、結構です。私、びしょ濡れなので車を汚してしまいますし……」
「問題無い。それより早くしなさい」
そう言うと、先生は私の手に先程のハンカチを握らせ、一人でさっさと車に戻ってしまった。そしてドアの前で私が来るのを待っている。
どうしようかと一瞬躊躇したが、結局私は甘えることにした。氷室先生に貸してもらったハンカチで、シートに直接当たるお尻を重点的に拭く。借り物でよりによってお尻を拭くだなんて申し訳ないが、そう言える余裕が無い。どうせ洗って後日返すのだからと、この際しっかり使わせてもらった。
「失礼します」
私は恐る恐る言い、車の助手席に乗り込んだ。濡れた制服のスカートが、私のお尻や太腿にベチョッと貼り付く。私がシートベルトを付けると、先生は何も言わずに車を走らせた。
車の前方のライトに、雨が浮かんでいる。私が学校を出た時とは比べられないぐらい激しい。
「こんなに遅くなるまで、一体何をしていた?」
赤信号で止まった時、氷室先生が突然話しかけてきた。私は緊張しながら答える。
「図書室で、現国で出た課題の本を読んでいました」
「そうか。勉強に熱心なのは良いが、女子生徒が暗い道を一人で歩いて帰るのは感心できない。課題で使う本はできるだけ借りるようにして、もう少し早めに帰宅しなさい」
「明日からはそうします」
私は頷いた。別に暗闇を歩くのは怖くないが、氷室先生が心配するのも分かるので、ここはとりあえず素直になっておいた。
歩くと片道二十分近く掛かる距離でも、車なら僅か五分で着く。あっという間に家の前まで来た。
「先生、今日はどうも有難うございまし──あれ?」
「どうした?」
私は、窓から自宅を見て驚いていた。いつもなら灯りで明るくなっていても良いはずなのに、家の中が真っ暗なのだ。
「家に誰もいないみたいなんです」
「君のご両親は共稼ぎか?」
「はい。ただ、普段なら母も弟も帰っている時間なんですが」
私は念の為に携帯電話を見た。しかし着信もメールも無い。
まぁ、家に誰もいなくとも私が困ることはないので、私は再度礼を告げて車を降りた。濡れているシートをハンカチで一応拭く。無駄だと分かっていても、礼儀としてやりたかった。
私は門を開けて敷地に入った。屋根のある玄関前に入って傘を畳み、ドアノブを握る。
引いてもドアは開かない。やはり無人なのだ。確認でチャイムを鳴らしたけれど、予想通り何の応答もなかった。
私は合鍵を出すべく、鞄の中に手を入れた。
「え?」
いつも鍵を入れている場所は空だった。そんなはずはないと私は慌てて鞄を探る。
雨に濡れていない場所を利用して、私は鞄の中身を全部出した。しかし全く見つからない。
「えぇっ?」
出した教科書類を元に戻しながら、私は絶望感に襲われた。どうやら鍵を落としたか、部屋に忘れてきたのである。両親から貰った合鍵は一本のみなので、どこかへ出かける度に、その時持っていく鞄に移し替えていく。おそらくこの前の休日に外出したあと、この学生鞄に入れるのを忘れたようだ。
私の家では空き巣に入られるのを懸念して、外に合鍵を置いていない。どうやら家族の誰かが家に帰ってこない限り、私は中に入れないようだ。
バシャバシャという足音に振り向くと、傘を差した氷室先生が立っていた。
「何事だ?」
「家に入れないんです」
私は家に誰もいないことと、合鍵を忘れたことを氷室先生に伝えた。全部言い終わった途端、先生は瞼を閉じてふうっと大きな息を吐いた。
「家を出る時は、こういうことも想定して持ち物をしっかり準備するべきだ」
「はい……」
私は惨めな気分だった。本当に今日はついていない。濡れた身体は冷えきっていて、今すぐお風呂に直行したいのに、目の前まで来ていて駄目なのだから最悪だ。
氷室先生は、私が壁に立て掛けておいた傘を取ると、広げて私に出した。
「とにかく、一緒に来なさい」
「は?
いえ、どうせもうすぐ誰かが帰ってくるでしょうから、ここで大人しく待ってみます」
しかし氷室先生は首を振った。
「そんなに濡れているのに、このような寒い場所で待つのは宜しくない。着替えだけでも、何とかするべきだ」
「はぁ」
確かに寒いので、替えの服を用意できるのなら早く制服を脱いでしまいたい。私は申し訳なく思いながらも、氷室先生に甘えて車に乗せてもらうことにした。氷室先生が配慮したらしく、車内は暖房が効いていてとても心地良かった。
「少し遠いが、臨海地区のショッピングモールへ向かう」
「お願いします」
おそらく先生は、校外で生徒と二人でいるのを他人に見られたくなくて、わざわざそこを選んだのだろう。けれども、家の近くの商店街でなかったのは私にとって有難かった。濡れ鼠のようなみっともない格好で知人に会いたくなかったし、ショッピングモールにはカフェやファーストフードが多く、時間も潰せるので好都合なのだ。
車がショッピングモールの立体駐車場に着いた。私は先生と共に建物の中に入る。
もうすぐ夕食時だというのに、会社帰りらしき人々で各店は賑わっていた。
氷室先生が大きな咳払いをした。
「コホン。
君はいつも、どういうところで洋服を買っているのだ?」
「私ですか? ここなら、ブティックジェスですけれど」
「ならば、その店へ行こう。
──あぁ、あそこだな」
ジェスは建物の入口近くにある。私は先生に引き摺られるように、店の中に入った。
「いらっしゃいませー」
店員の、やや演技がかったわざとらしい挨拶が響く。
私は戸惑っていた。確かに私は、先生に伝えたようにこの店によく来るが、バイトをしていない高校生がほいほいと服を気軽に買える値段ではないのだ。小遣いを懸命に溜めてやっとブラウス一着を買うとか、年末の一日のみに行なわれる特別セールを狙う程度で、後は専らウィンドーショッピングである。制服は上着もスカートも靴下も濡れているので、できれば一通り替えたいが、お財布がそれを許さない。
しかし私の思いをよそに、氷室先生は女性店員を捕まえて何やら話している。
「ではお客様、こちらへどうぞ」
「は、はぁ?」
その女性店員が、私を棚の前に連れていく。これは如何、あれは如何とここぞとばかりに高い商品を勧めてくるので、私は持ち合わせがないのを白状した。
店員はクスクス笑う。
「あぁ、それなら大丈夫ですよ。お支払いは、あちらの方がなさるそうですから。貴方に似合いそうな服を選んでくれと言われております」
「そんな」
店員は、私と氷室先生をどう見ているのだろう? おそらく、同じクラスの教師と生徒だとは露程も思っていないはずだ。
とはいえ、着替えを買わないと始まらない。私は、とりあえず先生にお金を借りるつもりで服を選んだ。
暖かいニットに膝丈のボックススカート、ついでにハイソックスも添える。更衣室に入り、濡れた制服からそれらに着替えた。
その間、氷室先生は洋服の支払いを済ませていたらしい。私は濡れた制服を店員に渡してジェスのビニール袋に入れてもらうと、先生と共に店を出た。背後から、店員一同のお礼の言葉が聞こえてくる。
「先生、すみませんでした。後で母に事情を話して、洋服代をお返ししますね」
「代金のことは気にしないで宜しい。君が濡れたのは、私の責任でもあるのだ。
それよりもう寒くはないか?」
「はい、大丈夫です」
「そうか。では──」
そう言うと、氷室先生は建物内のレストランゾーンへ私を連れていった。そして、適度に賑わっているサンドイッチのカフェに入る。
「好きなものを注文しなさい」
先生はBLTサンドとコーヒーを頼んでいる。以前、車に乗せてもらった時には、錠剤ばかり飲んでまともな食事を取っていない旨の話を聞いたが、流石に外出時には違うようだ。私も遠慮なくツナサンドと温かい紅茶を注文した。
先生が会計を済ませる。丸テーブルが空いていたので、私達は食品が乗ったトレイを持って椅子に座った。お腹が空いていたので、私は早速サンドイッチをぱくつく。
先生がコーヒーを飲んでゆっくりと言う。
「荷物は濡れなかったか?」
「ええと」
私は、空いている椅子に置いてある鞄に目を遣った。鞄の外側は濡れているが、中身にそう影響はない。それは、私が自宅前で鍵を探す時に手で触っているので確かである。ただ、私はもう一つの荷物を持っていた。ビニールコーティングされた小さな紙袋なのだが、こちらは学生鞄を盾にして必死に庇ってきたのに、水でふやけてくたくたになっている。学校の休み時間に出して断られた、氷室先生へのプレゼントだ。
「それは確か、君が私に──」
氷室先生もその紙袋の存在に気付いたようだ。私は慌てて口をはさむ。
「あ、あの、大丈夫ですから。袋や包装はともかく、中身は濡れても平気な物なんです。
どうせ、私自身が使うことになりましたし。」
「出しなさい」
「は?」
「……私への贈り物だったのだろう?」
「はぁ」
あまりの惨めっぷりに、先生は一度は断ったものの受け取ってやろうと同情してくれたのだろうか。理由はともかく、私にしてみれば先生に貰ってもらうに越したことはないので、ぐしょぐしょになった紙袋をテーブルの上に出す。
先生は濡れて切れ易くなった包装紙を丁寧に剥がしていく。中から、やはりしっとりしている白い箱が現れる。先生は口を止めているテープを取り、中身を出した。それは、私が数日かけて選び抜いたガラスの一輪挿しだ。
暫くの間、先生はそれを手に取って眺めた。
「ふむ。君のセンスは素晴らしいものがあるな。この選択は非常に正しい。有難く頂いておく」
「は、はぁ」
先生の言葉がいつもと変わらず固いものだったので、本当に喜んでいるのかどうか、私は瞬時に分からなかった。しかし、花瓶を見る目が優しかったのと口元が僅かにほころんでいたのに気付き、ようやく本当に成功したのだと私は強く確信した。一度昼間に断られた分、この展開は凄く嬉しい。
それから、私は先生のお小言を含んだ話を聞きながら、それでも楽しくお茶をした。
時間がある程度経ったので、携帯電話で家に連絡をしてみる。母親が電話に出たので、再び先生の車で送ってもらった。
帰宅した私は、すぐお風呂に入った。
じっくり温まった後で母親に話を聞くと、あの時は弟の尽と共に急ぎの買い物で丁度外出中だったらしい。どうやら私があと十分ほど待っていれば母親達が帰ってきたようなのだが、そこで二人と鉢合わせしなかったことに、私は感謝をしなければならない。あのまま家に入れていたら、私は先生とお茶もできなかったし、プレゼントも渡せなかったのだから。
私は母親に、氷室先生に服を買ってもらった事情を詳しく説明した。みるみるうちに母親の顔がさぁっと青ざめていく。彼女は慌ててクラスの連絡簿を出し、そこに記されている先生の自宅の番号に電話した。
「──」
母親が話し出した。先生も既に帰宅したらしい。
私は横で聞いていたが、二人の詳しい会話の内容は分からなかった。しかし母親は恐縮しているので、おそらく先生は、私に言ったように洋服代は要らないと告げたのだろう。
会話が挨拶で終わり、母親が受話器を戻した。途端に重い溜め息をふうっと吐く。
「後でお遣いものを用意するから、氷室先生に渡して頂戴」
「はーい」
私の想像は当たっていたようだ。多分、洋服代は三万円前後掛かっただろうに、気にしないで良いだなんてなかなか言えることではない。今日は先生のお誕生日であるのに、何だか私の方が先生からプレゼントを貰ったみたいだ。
私は階段を上って自室に戻った。よく持ち歩いているバッグを開けると、やはり中に合鍵が入っていた。私はクスリと笑って学生鞄にしまう。それから、机の引き出しを開けて新しい電池を出し、目覚まし時計の裏に入れた。
まったく、今日は何という日だろうか。朝から夕方までこれ以上ないぐらいついていなかったのに、夜は幸せだった。事態に対する私の考え方の違いだろうが、先生の車に水を掛けられたことも、家の鍵が開いていなかったことも、濡れた服を着替えなければならなかったことも、結果的に私にとっては嬉しい出来事である。
私は鞄から濡れた先生のハンカチを出した。せめてこれだけは、洗ってちゃんと返さなければならない。母親とは別に、私もお礼の品を添えるつもりだ。また時間のある時に街に出向いて、先生が気に入りそうなものを探さなければ。
両腕を上げて大きく伸びをする。朝からの出来事で私は気疲れしていたが、充分な満足感があった。
私はショッピングモールでの先生との会話を思い出しながら、ゆっくりと眠りに就いた。 |
了
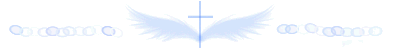
都合により、お誕生日にアップできないかもしれないので
少し早めの展示となりました。
氷室先生の車に水を引っ掛けられるというのは
もっと早くから思い付いていました。
誕生日記念SSももっと別の話にするつもりでしたが
丁度うまくくっつけられそうだったので
このように仕上げてみました。
(20021103 UP)
|
|