【コンテストの産物】
|
日曜日の昼下がり、私は葉月君と共にショッピングモールを訪れていた。丁度衣更の時期であるので、葉月君と一緒に洋服を選びたいと私から彼を誘ったのである。
普段は仕事で貰った服ばかりを着ているという葉月君だが、回ったお店では私以上に真剣になってくれた。ただ、ボタンが多く付いている服を私が手に取る度に、いちいち「それ、脱ぎ着が大変じゃないか」と言うのには苦笑したが。
買い物が一段落し、どこかでお茶でもしようかと私が葉月君と共に歩いていると、突然、誰かに後ろから肩を叩かれた。
「ねぇ、君達!」
私が振り返ると、二十代前半ぐらいの男性が額に汗しながら立っている。
「何ですか」
「あの……今、時間あるかな。これから中央広場で行なわれるベストカップルコンテストに、是非参加してもらいたいんだけど」
「はぁ?」
私は、思わず変な声を出してしまった。そして、横の葉月君の顔を見る。
葉月君は口元に手を当てて考えているようだったが、静かに首を左右に振った。
「……面倒臭い」
「そ、そこを何とかお願いできないかな? 僕はイベントスタッフなんだけど、前もって予定していたカップルのひと組にドタキャンされちゃってね。開始時間は迫っている上に、なるたけ“似合い”のカップルを探してこいって上から命令されて困っているんだ」
男性スタッフは顔を歪めながら必死で話している。
一方、聞いている私は、彼が放った“お似合いのカップル”という言葉に素早く反応し、だらしなく緩みそうになる口元を引き上げるので苦労していた。
「葉月君、どうする?」
「あ、出てくれるのなら、参加賞として女の子にはネコのぬいぐるみをあげるよ。勿論、上位入賞すれば、このショッピングモールでのお買い物券とかも出る。
頼むよ! ね、ね?」
「ネコの……ぬいぐるみ……?」
葉月君がぼそっと呟いた。
「そう。参加賞とはいえ、玩具で有名な××社の特製品だよ。三毛ネコで凄く可愛いから、彼女サンも喜ぶんじゃないかな」
私は内心で笑ってしまった。葉月君は、私以上にネコ好きである。コンテスト参加について、私が“葉月君のカノジョ”として出られる名誉の為に揺らいでいるのに対し、葉月君は参加賞のぬいぐるみに執着しているのだ。
私は、とどめの質問を男性スタッフにした。
「あの、そのネコのぬいぐるみなんですけど、女の子だけじゃなくて彼の分も貰えませんか? 私達、ネコが大好きなんです」
すると、男性スタッフは待ってましたと言わんばかりに顔を輝かせる。
「いいよ、いいよ! 数に余裕があるはずだから、それぐらいは調整してあげる。
じゃ、参加をお願いしても構わないよね?」
「──」
私は葉月君を見た。
葉月君も、私を見ている。
特に拒否の言葉が出なかったのを良いことに、私はすぐに口を開いた。
「はい、出ます。宜しくお願いします!」
やった!
私は内心でガッツポーズをした。葉月君と恋人同士としてコンテストに出るだなんて、恥ずかしいけれど嬉しい気持ちが大きい。
声かけに成功した男性スタッフは、私達が了承したことに心からホッとしている様子である。
それから、彼に連れられて私達は中央広場へと向かった。
途中で、葉月君が私の耳元に口を寄せる。
「悪かったな」
「ん?」
「俺がぬいぐるみを欲しそうにしていたから、お前が気を遣ってくれたんだろう?」
「……まぁ、私も欲しかったし。気にしないで」
本当を言うと、ネコのぬいぐるみは貰えるのなら欲しいけれど、何が何でもというほどではない。わざわざ訂正することでもないので、私は葉月君の勘違いに甘えた。
中央広場に着くと、男性スタッフは私達に白くて丸いプレートを渡した。そこには黒の太文字で、十四と書かれている。これが私達の番号だ。
コンテスト開始までは控え室にいてくれと言われ、男女別の部屋に通された。一人になった私は、そこでアンケートに答えさせられる。誕生日やら好きな食べ物といった他愛のない質問ばかりだったので、私は苦もなく書き上げたのだった。
そして、いよいよコンテストが始まった。
ステージ上にいる司会者がひと組の番号を読み上げ、舞台下手から男性が、舞台上手から女性がそれぞれ登場し、中央で揃う形式になっている。
コンテストは、ステージを見ているお客さんの投票結果の他、相手をどれくらい理解しているかで順位が競われるらしい。それを何で計るかというと、開始前に書いたアンケートを利用するようだ。そこにある答えを元に、司会者が相手に質問をする。つまり私達の場合、葉月君のことについて私が答え、私のことに葉月君が答えることになるのだ。
ひと組、またひと組……と終わっていき、いよいよ私達の番になった。
「では十四番の方、どうぞ!」
私はステージに歩み出た。反対の下手側から、葉月君も現れる。
舞台中央に並んだ私達は、見ているお客さん達に向かって軽く会釈をした。すると、目敏い人は葉月君があの“モデルの葉月珪”だと気付いたようで、悲鳴混じりの声が上がる。
司会者は、手に持っている資料らしき紙を見ながら言った。
「ええと、こちらはショッピングモールでお買い物中のところを、スタッフが見つけて参加をお願いしたカップルです。
カレシは凄く格好良いですねー。でも、どこかで見たことがあるんですが……」
途端に、客席から「珪ーっ!」と歓声が上がる。しかし、司会者はそれが分からないのか反応しなかった。
「では、早速質問を開始します。
まずカノジョさんの方。ちゃんと真面目に答えて下さいね。
第一問! 男の子の好きな食べ物は何でしょう?」
「ツナ、ですか?」
「正解です!」
これぐらいは簡単である。私は葉月君に向かってピースサインをした。
「続いて第二問! 好きな動物は何?」
「ネコ!」
「お、これもまた正解です」
こんな調子で、私は質問に次々と答えていった。
結果、勿論全問正解である。胸を張った私に、葉月君は何だか照れくさそうだった。
「カノジョさんは凄いですね〜。
続いてカレシくんに聞きます」
いよいよ葉月君の番だ。彼は私を分かってくれているのだろうか。やや心配になったが、すぐに大丈夫だと思い直した。私が葉月君と過ごした時間分だけ、彼も私と一緒にいたのだ。
「まず第一問! カノジョの、サンドイッチで好きな具は?」
葉月君は、うーんと首を傾げる。
「……ツナ?」
「不正解! 正しくはタマゴサンドでした。
次、第二問! 一番好きな動物は?」
「ネコ」
「おおっと、これも不正解です! 正解は犬ーっ!」
聞いていた私は愕然とした。次々と出される質問を、葉月君は間違って答えていく。今まで一緒に会っていた時間に、葉月君は私の何を見ていたのだろうか。恥ずかしさと悔しさで、私は顔が上げられなかった。
結局、私の全問正解に対し、葉月君は全滅という結果で終わった。これには司会者もフォローのしようがなかったようで、それ以上触れずに「どうも有難うございました」と言って、他の参加者が控えている舞台袖へ私達を帰した。
その途中、参加者の一人の女性が私を見てククッと笑った。
「あれ、葉月珪でしょう? 無理してカップルの振りしたって、こうボロが出たんじゃ駄目よねぇ」
私は更に惨めな気分になった。この言葉はおそらく彼女だけのものではない。あの場で葉月君の正体に気付いた人全員が、こう思っているだろう。
それから暫く経って、お客さんの投票結果が発表された。これに、先程の質問の正解率がポイントとして加えられる。
分かっていたことだが、見事にベストカップル賞を獲ったのは他の人達だった。私達は投票も正解率も一際低く、何と最下位である。葉月君のファンの人達が私達に票を入れるはずがないので、投票結果が悪いのは予め分かっていたが、それでも悲しかった。私達をカップルとして認めないと、強く否定された気になったからである。
表彰式が終わって私達が裏へ戻ると、最初に声をかけてきた男性スタッフと会った。
「いやぁ、却って悪いことをしちゃったみたいだね。
はい、参加賞のぬいぐるみ。どうも有難う」
男性スタッフは私に紙袋を渡すと去っていった。見ると、小さな白い箱が二個入っている。私は片方を葉月君に差し出した。
「はい」
「……あぁ」
葉月君が箱を開ける。中には、三毛ネコの可愛いぬいぐるみがあった。
「あ、可愛い! タダで貰えて良かったね、葉月君」
しかし葉月君は無言で鞄に箱をしまう。
「葉月君?」
「──すまない」
「何が?」
「答えたの、全部間違っていて」
「あぁ、そのこと」
なるべく気にしないようにと思っていたのだが、やはり葉月君の頭には残っていたらしい。私が全問正解に対し、葉月君は全問不正解だったのだから、それも仕方がないけれども。
ただ、私は彼の詫びの言葉を素直に受け取る訳にはいかなかった。あのステージから降りる時に気付いたことだが──こういう結果に終わったのは、私にも大きな責任があったからである。
「悪かったな。俺がちゃんと答えられたら、もっと良い成績だったのかもしれないのに」
「その件だけど、葉月君のせいじゃないんだ。私にも非があるの」
「ん?」
葉月君が、不思議そうに私を見た。
「実は私、葉月君に少しでも気に入られようと思って、自分の嗜好を無理に合わせていたんだよね。
例えば……私も葉月君と同じようにネコが好きだけど、本当はそれ以上に犬が好きなの。でも実際に葉月君と話していると、犬のことなんて全然出ないじゃない。だから私もそれを一旦どこかに置いておいて、『ネコ、大好き!』って言っちゃうのよね。嘘とは違うんだけど──でも、自分を偽っているとは言えると思う」
しかも、私はこれを無意識で行なっていた。大好きで憧れている葉月君に少しでも気に入ってもらう為に、私は私自身の心の上に薄いフィルターを被せたのだ。悪く言えば、“葉月君好みな私”を演じていたことになる。だが、これは恋する女の子なら誰でも多少なりしているので、私に罪の意識は全く無い。
「お前、俺に合わせて無理していたのか?」
「あ、誤解しないで! 無理なんて、全然していないんだから。ただ葉月君と楽しくお話する為に……そう、少し背伸びをしていたのかな。でも、葉月君に話を合わせるのは楽しかった。大変だと思ったことは一度も無いし、これでも充分幸せだったんだよ」
「そうか」
葉月君は表情を固くしていた。勢いに乗ってつい告白してしまったが、これで良かったのかと今になって私は慌て出す。
「あの……葉月君。ネコよりも犬で、ツナサンドよりもタマゴサンドな私じゃ駄目かな」
「要するに、それらが一番じゃないってことだろう?」
「うん。ネコもツナサンドも……他も、確かに好きに違いないんだ」
私は急いで頷く。
葉月君は、やや呆れた風にふうっと息を吐いた。
「別に、それで構わない。今までよく考えてこなかったけど、好みが俺と全部同じって個性無いぜ。俺は──お前の本当のことを知りたい」
「葉月君……」
どうやら私の懺悔は葉月君に受け入れられたらしい。嫌われなくて良かったと、私はホッと胸を撫で下ろした。
「これから、お前を沢山勉強しなくちゃな」
「『こんなことが好きだったのか』っていうのが結構あると思うよ。
どれくらい私を知ってくれたのか、抜き打ちテスト気分で、またコンテストに出るのも楽しいかもね」
「おい……また出るのか? これ」
口調は厳しかったが、私が見た限りだと葉月君の顔は少し微笑んでいるようだった。私にしてみれば冗談と本気が半分ずつだけれど、もし彼が許してくれるのなら再挑戦してみたいものである。
とりあえず、立ちっぱなしで疲れたのでカフェでお茶を飲むことにした。
まずは、少しずつ本当の私を葉月君に見てもらうことにする。葉月君と出会った入学式当初は、彼に好かれることばかり考えていたけれど、今は違う。偽の情報に包まれた私を気に入られても仕方がないのだと、あの舞台上で嫌というほど分かったからだ。
私はもう怖くない。
これまで過ごしてきた葉月君との時間が、私の背中を強く押してくれた。 |
了
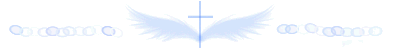
「ときメモGS」を遊んだ当初の頃にネタを思い付いたSSです。
ノートに「ベストカップルコンテスト」とだけ書いて
ほったらかしになっておりました。
その頃に考えていた話とは趣が違うのですが
この仕上がりには満足しています。
(20021023 UP)
|
|