【願いが叶った時】
|
昔から、私は物語のヒロインになりたいと思っていた。
本や映画で活躍する彼女達は、素敵な恋人と共に魅力的な生涯を送っている。私の物語の中で私自身が主人公なのは当然だが、こんな平凡な日常において、心踊るようなスリルやサスペンスは起こるはずがない。せっかく、お伽話に出てくる王子様のような葉月君がいつも傍にいてくれるというのに、その状況に慣れてしまった私は刺激に飢えていた。
さて、とある年の冬休みのこと。私は葉月君に誘われて、はばたき山へスキーをしにやって来た。
実を言うと、私が雪山でスキーを滑るのはこれが初めてである。約一ヶ月前に葉月君からこのスキーデートの話を持ちかけられてから、スポーツ万能な彼に合わせるべく、電車で片道一時間もかかる屋内スキー場で秘密の特訓をずっとしていたのだ。どうしても一ヶ月後にはベテラン並みに滑りたいという私の我が儘に指導員を巻き込み、私は全力で頑張った。暇さえあればそこへ通い、身体には嬉しくない痣も沢山できた。お陰で、指導員からお墨付きを貰うまでになったのだが、私はもうボロボロだった。たかがデートの為にと他人には笑われるかもしれないが、葉月君に失望されるよりはマシなのである。
現地に着いてスキーウェアに着替え、私は葉月君と共に滑り出した。最初こそ本当に大丈夫かと心配したけれど、実際に滑ってしまえば屋上スキーと大差はない。途中でボロが出るとまずいので、最初の一本を滑り終わった後に、私は葉月君に雪山でのスキーが未経験だと伝えた。はばたき高校へ転校する前は近くにスキー場が無かったと状況を説明すると、葉月君は素直に頷いてくれた。それにしては上手いと褒められたが、屋内スキー場で地獄の特訓をしたのは内緒にする。
初心者コースで馴らした後、私は葉月君と中級者コースを堪能した。葉月君のスキーの腕前は、私の目からもはっきりと分かった。滑り方が綺麗だし、何より格好良いのだ。私は彼の素晴らしさにぼーっとなりながら、懸命に後を追った。
午後一時を過ぎたところで、私達は山の中腹にある休憩所で昼食を取った。ゴーグルを外して顔を見せる葉月君に、休憩所中の女性が見とれる。中にはモデルとしての彼を知っている人もいたようで、「あれって絶対に葉月珪だよ……」という小さな声も所々に聞こえてきた。勿論、彼の横に陣取る私は鼻高々だ。少々のやっかみが、逆に心地良い。
優越感に浸った食事が終わった後、葉月君が傾斜のきつい上級者コースへ行きたいと言うので、私は応じた。葉月君は私に気を遣って「無理するな」と言ってくれたが、下で一人で待つだなんて淋しいではないか。これも経験だと、私は精一杯の勇気を出してついていった。
結局、そのコースも難無く終わった。葉月君はそこを一度滑って満足したのか、それとも私へ気遣いが続いているのか、もういいと言って、午前中に遊んだ中級者のコースへ戻った。私は緊張から開放されたことにホッと胸を撫で下ろし、今度は心底スキーを楽しんだ。
夕方になった。赤く染まりながら徐々に山へ沈んでいく夕陽は、とてもとても素敵だった。
翌日は学校があることだし、帰りがあまり遅くなってはいけないということで、私達はそろそろ帰ろうと話していた。その前に、もう一本だけ滑ろうと葉月君に言われ、私はすぐに賛成した。
そのコースのリフトは混雑していた。夕陽を浴びながらスキーをしようという私達の考えは、皆と同じだったらしい。
辛抱強く待って、いよいよ私達の番となった。二人乗りなので右側に葉月君が座り、その横に私が腰を下ろす。
リフトは素敵だ。大好きな人とこんなに密着できるだなんて、なんて素晴らしい乗り物だろうか。私は葉月君と他愛のないことを喋りながら、この幸せな時間がずっと続くと良いのにと、願っても仕方がないことを思っていた。
その時である。
ガクッとリフトが揺れて、突然動きが止まった。
私と葉月君は顔を見合わせた後、後ろを振り返る。
「……止まったな」
「うん」
リフトが止まるのは、よくあることらしい。特訓で非常にお世話になった指導員から、スキー場での体験談を色々聞いた中にこの話もあったので、私は全く慌てなかった。横の葉月君も落ち着いている。また、私の前後に座っている客達も呑気に雑談をしているようだった。少し待てば動くだろう、私は安心しながらそう思っていた。
何より、先程私が願ったことが叶ったのだ。スキーウェア越しではあるが、私の右腕は葉月君の左腕に密着している。眩しい夕陽を見つつ、それを背景にした葉月君の横顔に、私は暫くの間のぼせていた。
しかし、いつまで経ってもリフトは動き出さない。葉月君との会話がふと途切れた時に、私は再度振り返って後ろを見た。前は談笑していたはずの客に、焦りの表情が出ている。
待っている間に夕陽は落ち、辺りは暗くなってきた。このスキー場ではコース限定でナイトスキーを開催しているので、照明灯はすぐ近くにあるのだが、夜になったと思うと急に怖くなる。私は恐怖心を必死で押さえた。
それから一体どのぐらい待っただろうか。日が暮れてから、風が強くなった。雪が降っていないので、吹雪という最悪な状況ではないのだけれど、地面から高い位置にあるリフト上ではかなり寒い。私は手で自分の腕を抱きながら、ブルッと震えた。横の葉月君はずっと無口である。私も喋りたい気分でなかったし、口を開くと不安の言葉ばかり出そうだったので、逆にこの静かな時間が私を奮い立たせた。
ふと、背後から声が聞こえてきたので、私は再度振り返った。すると、後ろの客が私達に向かって叫んでいる。
「あのー、停電でリフトが動かないそうですよー! 可能な人は飛び下りるようにと、後ろから伝言がありました。
貴女も前の人にこの言葉を回してもらえますか?!」
飛び下りるようにと言われても困る。私が下を見る限り、地上から四、五メートルぐらいあるだろうか。とてもじゃないが、怖くてそんなことはできない。もしも飛び下りたとしても、絶対にただでは済まないはずだ。良くて打撲……骨折も充分考えられる。
可能なら飛び下りろだなんてなんと無責任な、と内心憤慨しながら、私は後ろの客がやったように大きな声を出して前の客に用件を伝えた。おそらく私がそうだったように、前の客は伝言の内容を聞いてぎょっとしている。
「葉月君、どうしよう。ずっとこのままなのかなぁ」
横の葉月君は、何も返事をしてくれない。
「葉月君?」
私が葉月君の顔を覗き込むと、彼は目を閉じている。どうやら、この緊急時にも関わらず眠っているらしい。
私は怒鳴った。
「──葉月君ってば! 寝ている場合じゃないよ!」
「……ん?」
「こんな寒いところで寝たら駄目だよ。起きて、ねぇ起きて!」
ようやく葉月君は目を擦りながら顔を上げる。
「ここ、どこだ?」
「スキー場だよ! 乗っていたリフトが止まっちゃったんじゃない」
「あぁ……そうか」
おそらく、現在リフトに乗っている客の中で一番呑気なのはこの葉月君だろう。何という人だろうかと、私は思わず笑ってしまった。
「さっきね、後ろから伝言が回ってきたの」
私は状況を説明する。葉月君は下を見て、ううんと唸った。
「じゃあ、さっさと降りるか?」
「ええ?! ほ、本気?!」
「だって自分で飛び下りるしかないんだろう?」
「それはそうだけど」
葉月君の言葉はもっともだが、この状況ではやはり無理がある。周囲の客もそう思っているらしく、私が見える範囲では全員がまだリフトに残っていた。
「ねぇ、ここから飛び下りたら骨が折れちゃうよ。仕事に支障が出たら大変だってば」
「……それもそうだな」
葉月君は本当に降りる気だったらしい。努力の鬼の私と違って、運動神経の発達が素晴らしい葉月君なら何とかなるかもしれないが、もしも万が一のことが起こったら大変である。
その結果、私達は周囲の客同様に救助隊が来るのを大人しく待とうと決めた。
更に三十分以上過ぎた後、駆けつけた救助隊が持ってきた棒状の道具を使って、私と葉月君はようやく無事に地上に降りた。私は寒さと恐怖でがたがたと震えていたが、葉月君は何事もなかったかのようにけろっとしている。あんな危機的状況で、どうしてこんなに平然としていられるのか、私は舌を巻いた。
「遅くなったけど、下まで一気に帰ろう」
葉月君はそう言うと、軽やかにスキーを滑り出した。自力で下に行ける人間はなるべくそうするようにと救助隊から言われていたので、彼の行動には問題が無かったけれど、私は体力も気力もとうに尽きていて、もうへとへとである。それでも先に行った葉月君の後を追おうと、私は最後に残っていた意地だけで滑った。
しかし、表面に積もっていた細かい雪は強風によって全部飛び散っており、ここはスケート場かと錯角しそうなぐらいに足元は凍っていた。ツルツルと異常によく滑る雪の上に、もはや身体を充分に支えられない膝と腰を使ってスキーをしたものだから、私はすぐに転んでしまう。しかもその場で止まらずに、ずるっと滑り落ちていく。
「きゃあっ!」
私の叫び声に、前方の葉月君が滑るのを止めて振り返ってくれた。しかし、腰から惨めに滑り落ちてくる私の姿に驚いたのか、ゴーグルを外した彼は唖然とした表情でこちらを見ている。
その場で待ってくれた葉月君の手を借りて、私はようやく止まった。葉月君が苦笑する。
「お前、そのまま下まで行くつもりだったのか?」
そんなつもりは微塵もない。私は恥ずかしさで顔を上げられなかった。
今日のリフト事故は、私が今まで生きてきた十数年の中でも上位に食い込むハプニングだった。その中で、私は間違いなくヒロインを演じていただろう。あの葉月君と共に、危険に身を晒しながら恐怖に耐えていたのだから。
しかし、もう充分だった。このまま死ぬかもしれないと思ったし、何より肉体にも精神にも辛過ぎる。やはりヒロインたるもの、何事にもタフでないといけないようだ。私にはそれに耐えられる力が無い。必要なかったのに最後は情けないオチまで付けて、私はこれまで抱いていたヒロイン願望を全て昇華したと実感した。
とにもかくにも、無事に帰れて良かったのである。物語は、できれば“めでたし、めでたし”で終わるべきだと思っているが、今回ほどそれを望んだことはない。
平凡が一番。私にとって、葉月君が横にいること自体でもう充分なのだと、私は心の底から思った。
そんな訳で、とりあえずめでたし、めでたし。 |
了
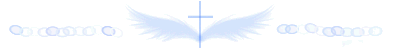
私はスキー未経験なので、このSSは全てにあやしいです(汗)。
一度ぐらいは話の種にやってみたいんですけどねー。
できれば温泉旅行とセットで ←こっちが本命だったり。
(20021003 UP)
|
|