【デッド・スター・エンド】
|
風が冷たくなりだした秋のとある平日。
学校の休み時間に私が廊下を歩いていると、後ろから誰かに名前を呼ばれた。振り返ると、珠美ちゃんがいる。
「珠美ちゃん、どうしたの?」
「あのね……今週の日曜日って空いてるかな?」
手帳を携帯していなかったので、私は予定を思い出しながら言った。
「確か、何もなかったと思う。暇だから、商店街に買い物でも行こうかと思っていたんだけど。
またバスケ部が他校と交流試合をやるの?」
「あ、いつもマネージャーの仕事を手伝ってくれて有難うね。
でも今回はそうじゃないの。遊園地のフリーパス券を四枚貰ったから、一緒に行ってくれないかなと思って」
はばたき市郊外にある遊園地は車に乗らないと行けない場所で少し遠いけれど、アトラクションがとても充実しているので人気のスポットである。私も数回行ったことがあり、とても楽しんだ思い出があった。
なので、即答する。
「いいよ。私もあの遊園地が好きだし。何よりタダ券で遊べるっていうのが良いね!」
「でしょう?」
「ところで、あと二人は誰を誘ったの?」
「それなんだけど……」
珠美ちゃんは、もじもじしながら恥ずかしそうに俯いた。その様子が可愛くて、見ていた私の口元に笑みが浮かんでしまう。これを珠美ちゃんに知られると失礼なので、慌てて表情を固くして笑いを消した。
「珠美ちゃん?」
「あ、ごめんね。休み時間は短いのに、私がこういう風にとろとろしていると迷惑だよね」
「そんなことはないけど」
「そう? 有難う。
あの……あのね、この前、体育館で鈴鹿君と色々話していたら、あの遊園地の話になったの。鈴鹿君も、あそこが大好きなんだって。だから彼を誘うと思ってるの」
「へぇ」
ははーん、と内心思った。私は前々から、珠美ちゃんが鈴鹿君を友人以上に意識しているのに気付いていたのだ。珠美ちゃんはそれを必死で隠しているようだが、はっきり言ってバレバレである。それに私から見ると、どうやら鈴鹿君の方もまんざらでもなさそうで、きっかけと珠美ちゃんの勇気さえあれば、巧く発展させられるのではと思っていた。遊園地の無料券を入手したのは偶然か、または珠美ちゃんの陰の努力の成果かもしれないけれど、とにかくこれを最大限に利用しようと彼女なりに考えたのだろう。言わば私は当て馬というか、出しに使われる立場として誘われたようだが、珠美ちゃんの為なら喜んで協力してあげよう。
ただ、少しだけ虐めてみる。
「なるほどね、鈴鹿君かぁ……。私はおまけ、ってことね」
「ち、違うよ! そういうつもりはないんだけど、あの……私一人で鈴鹿君を誘うのはちょっと……」
珠美ちゃんは、顔を真っ赤にしながら弁解の言葉を珍しく早口で喋る。少し可哀想になったので、私はすぐに謝った。
「ごめんごめん。大丈夫、私は喜んで行くよ。せっかく声を掛けてもらったんだからね。
でも、あと一人は? 鈴鹿君に友達を連れてきてもらうの?」
「それなんだけど、葉月君を誘ってもらえないかなぁ?」
「え?! 葉月君を? 私が?」
珠美ちゃんの口から出た人物に、私は意表をつかれた。彼女の中で、まさか葉月君の名前が候補に挙がっているとは思ってもみなかったからだ。
「だって仲良いじゃない。ね? お願いー!」
「……」
私には、珠美ちゃんの考えていることが何となく分かった。本当は、最後の一人は誰でも良いのだが、その人が中途半端に珠美ちゃん自身や鈴鹿君と親しいと、彼女が鈴鹿君と一緒にいられない可能性が出てくるのだ。遊園地の各アトラクションは二名一組が原則なものが多く、カップルで遊ぶには適している。もし万が一、話の流れによる変な組み合わせで遊ぶことになったら、彼女の大事な計画は崩れてしまう。その為に珠美ちゃんや、鈴鹿君よりも私を選ぶ人間を最後の一人として連れてくる必要があるのだ。これに適しているのが葉月君である。彼にとって珠美ちゃんは、他の同級生同様ただの顔見知り以下だろう。それを見越しての提案らしい。
どう返事をしようか、私は無言で考える。確かに他の人とくらべれば、私は葉月君と親しい方の部類に入るだろう。それに私個人で考えれば、葉月君と一緒に遊びに出掛けられるなんて嬉しいことだ。しかも所謂“Wデート”である。葉月君をいいなと思っている私にとって、公然と彼を誘えるこの機会はとても有難い。だが、その葉月君がこの話に乗ってくれるかなんて、勝算の低い賭である。行きたくないと軽く断られるかもしれないし、モデルの仕事が入っていることも考えられた。
「分かった。葉月君には私から誘ってみるよ。でも、断られるかもしれないことを頭に置いておいてね」
「早めに返事を貰ってくれるかな? その……次の人を、探さなくちゃいけないし」
「あぁ……うん、分かった」
三人だけで行く、という考えは頭にないらしい。他人事ながら大変だと思った私は、とりあえず笑って頷くと、珠美ちゃんと別れて教室へ戻った。
私は葉月君とも別のクラスなので、彼に会うには次の休み時間まで待たなければならなかった。
丁度、お昼の長い休みに入る。私は友達とお昼を済ませた後、葉月君の教室へ向かった。廊下の窓から覗くと、彼の姿はどこにもない。私は階段を駆け降りて昇降口まで行くと、靴を履き替えて外へ出た。
こういう時、葉月君は体育館裏にいることが多い。そこには猫の親子がいて、猫好きな彼はよく世話をしているのだ。猫の方も葉月君にとても懐いているようで、みゃーみゃー鳴きながら彼にまとわりつくのが、見ていていつも微笑ましかった。
私が体育館裏へ移動すると、葉月君はやはりそこで猫と遊んでいた。猫が怖がらないように、そっと近付いて小さな声で呼ぶ。
「葉月くん」
葉月君は顔だけ私の方を見ると、小さく頷いて応えてくれた。彼の身体や腕は、甘える猫達に占領されている。私は彼の向かい側に腰を下ろすと、一番近くにいた子猫を抱き上げた。
「ちょっと話があるんだけど」
「あぁ」
「紺野珠美ちゃんって分かる? ×組で、男子バスケ部のマネージャーをやっている女の子」
「……お前がよく話している奴だろう?」
「そう! あのね、珠美ちゃんが遊園地のフリーパス券を四枚貰ったんだって。今週の日曜日に行こうって誘われたんだけど、葉月君もどうかな? 私達と一緒に行かない?」
「この俺が?」
葉月君は無表情で私に問い直した。表情や声で彼の気持ちが分かるかと思ったが、これでは全く駄目である。私は誘いを続けた。
「そう。珠美ちゃんもね、バスケ部の男子を誘うって言ってたの。だから私も男の子を誘った方がバランスが取れて良いかなって思ったんだけど、こういう風に声を掛けられる知り合いっていないから……」
これまで一ヶ月に一回程度のペースで、私は葉月君と色んな場所へ遊びに行っている。近場は勿論、この遊園地にも二人だけで行ったことがあった。だから引いて引いて、私には葉月君しかいないということをアピールすれば、参加してくれるだろうと踏んだのだ。
葉月君は膝の上に乗っている猫達の頭を優しく撫でながら、少し考えているようだった。
暫くして、視線を私に向けて言った。
「分かった。他に用事も無いから、一緒に行ってやる」
「本当? 良かったー。じゃあ、待ち合わせとかの詳しいことは、決まり次第すぐ知らせるね」
「あぁ」
葉月君は、私に強く言われて「仕方がなく行く」といった感じで、この誘いを受けてくれた。彼はいつもこういう風に無愛想な返事をしてくる。だから本当にそうなのか、それとも照れてそうしてしまうのか、私には分かりかねるが、とにかく断られないで良かったという気持ちで私の心は一杯だった。早く珠美ちゃんに知らせたかったので、この旨を葉月君に伝えて体育館裏を後にした。
それから数日後。色んな意味で待望の日曜日がやって来た。
駅前のバスターミナル付近で集合した私達四人は、直通バスに乗って目的地の遊園地へ向かう。バスに乗る前に、早速珠美ちゃんにチャンス到来だと私は思ったのだが、車内が混んでいて空席が二つしかなく、私と珠美ちゃんで座ることになってしまった。私は、葉月君と鈴鹿君が巧くやっていけるかが心配だったが、特に親しい訳ではないけれど、ぽつぽつと普通に喋っているらしい。葉月君自身の取っ付き難さも、今日はいつもより薄いような気がしている。
開園直後だというのに、遊園地は適度に混んでいた。入口で案内図を貰い、これから向かうアトラクションを決める。
珠美ちゃんが案内図の一点を指しながら言った。
「私、これに乗りたいなー」
彼女が提案したのは、グリム童話を元にしたアトラクションだった。小さな車に乗り、その疑似世界を見て回る内容である。他に希望が出なかったし、このWデートの元を作った彼女の案であるから、私達はそれに賛成した。
列に並んで十分弱待ち、ようやく私達の番となった。車は四人乗りである。混んでいる時に二人組で参加した場合、スタッフが相乗りを強要してくるのだが、今はまだ空いているので、ちゃんと別々の車に乗せてくれていた。
スタッフが、一番近くにいた葉月君に聞く。
「何名様ですか?」
「よ──」
「二人! 二人です!!
葉月君、行こう?!」
私は横にいた葉月君の腕を取って、最初の車に無理矢理乗った。自動的に降りてきた安全バーに掴まって後ろを振り返ると、珠美ちゃんと鈴鹿君が新たに来た車に丁度乗るところである。良かった、と思いながら私は隣の葉月君を見た。
「ごめんね」
「いいのか? 一緒に乗らないで」
「うん。今日、私はその為にいるから」
「どういう意味?」
「えっと……」
私は口籠った。ここで勝手に説明をして良いものだろうか。第一、私は珠美ちゃんの気持ちすら確認していない状態なのである。だが、今日一日はずっとこんな感じになってしまうのだ。何も知らずにただ遊びに来たと思っている葉月君には、訳分からないことが続くだろう。それに、もしも彼が珠美ちゃんとペアを組みたいと望んでしまったら、後々面倒臭いことになる。
考えている内に、車はどんどんと進んでいく。今は、よく作られた中世ファンタジーチックな世界を通っている。童話に出てくる主人公達の人形が、私達に向かって手を振っていた。
私は葉月君を信じ、思い切って言ってみることにする。
「あのね、これはあくまでも私の推測でしかないんだけど……」
「ん?」
「珠美ちゃんはね、本当は鈴鹿君と二人だけでここに来たかったんだと思うの。でもそれが難しいから、こうして私達を誘った訳。
この意味、分かる?」
「……あぁ、そういうことか」
葉月君は低く呟いた。
「ちゃんと珠美ちゃんに確認したことがないから、もしかしたら違うかもしれない。でもあの二人、良い感じなのよー。
だからあの二人に嫌がられない限り、私は葉月君と一緒に行動するようになると思う」
「あ、そう」
葉月君は素っ気無く返事をした。本当は私の願望も入っているのだけど、というのはまだ内緒である。とにかく葉月君に嫌だと言われなくて良かったと、私はホッとした。
安心したところで、私は葉月君に白状する。
「ごめんね。実は、葉月君を誘う前からこうなることは分かっていたんだ。ほら、『珠美ちゃんがバスケ部の男子を連れてくる』って言ったでしょう? あれ、鈴鹿君のことだったの。
──呆れた?」
「あぁ」
「ええっ?!」
私は思わず大声を出してしまった。アトラクション内の狭い空間に、私の叫び声がわんわん響き渡る。横の葉月君がクスッと笑った。
「ごめん──冗談」
「……もう」
暗がりで葉月君には気付かれなかっただろうが、私は少し涙目になっていた。もし、これで葉月君が不快感を覚えたとしたら、夕方過ぎまで一緒にいるのにお互い辛い思いをしてしまう。珠美ちゃん達にも迷惑が掛かるかもしれない。
怖々と、私は葉月君に尋ねた。
「ねぇ、葉月君。さっきの……本当に平気? あんまりつまらなかったら、私が珠美ちゃんに交代してくれるよう頼んでみるけど」
「いいって。お前と二人でここに来たと思えば済む話だ。気にするな」
今度は本当に、心の底から安堵する。自分では分からなかったが、葉月君に事情を説明し始めてからずっと緊張していたらしい。身体中の筋肉が一気に弛緩するのを感じた。
そんな訳で、私はアトラクションどころではない心境だった。さぁ楽しもう!という頃には、もう終わりに差し掛かっていたのである。それは葉月君も同様だったようで、車から降りると私に向かって皮肉っぽい笑みを向けた。
「何だか、集中できないまま終わったな」
「ごめんなさい、私のせいだね」
「もう謝らなくていい。俺も納得したし、ちゃんと今日一日付き合ってやるよ。
あ、来たぜ」
葉月君の声に後ろを向くと、珠美ちゃん達の車が着いたところだった。二人は楽しそうに笑い声を上げながら、私達の方へ近付いてくる。
「面白かったね」
「なぁ、お前ら、変に盛り上がっていなかったか?」
鈴鹿君が、私と葉月君を見て言った。私は慌てて誤魔化す。
「そ、そうかなぁ。私達、全然関係ない話をしていたから……」
「ふうん」
「──次は何に乗る? 早くここを出ようよ」
私は急かして無理矢理話を締めた。暗い建物から明るい外に出たので、私達は揃って目を細める。
次のアトラクションはジェットコースターとなった。リニューアルしたばかりで、遊園地が今一番力を入れている乗り物である。以前のものなら、私も乗ったことがあるが、これはまだ未体験だ。ループが三回、そして高低差の大きな波が続く、ジェットコースターの中でもなかなか激しい部類に入る。
そこへ向かって歩いている途中、私は珠美ちゃんと並んだ。彼女が、小さな声で言う。
「ねぇねぇ、次は誰と乗りたい?」
私にそう聞くのか、と思わず苦笑してしまった。珠美ちゃんが不思議そうな顔をする。
ふと、私に名案が浮かんだ。これはある意味、事の真実を知るチャンスだ。
「私、次は鈴鹿君と乗ろうかなぁ。鈴鹿君、ジェットコースターって凄く好きそうじゃない。隣に座ってもらえると楽しいよね」
「えぇぇ?」
珠美ちゃんは素頓狂な声を挙げた。慌てて手で口を押さえる。
「あ、えっと……ごめんね、変な声出しちゃって。
あの──そそそそうだよね、さっきは私が鈴鹿君と乗ったんだもん。こ……交代しなくちゃいけないよね。うん、じゃあ……私は葉月君と……」
「嘘。私が葉月君と乗るから安心して」
「えっ」
私の言葉に、再び珠美ちゃんが叫んだ。流石にこれには、私達の後ろを歩いていた鈴鹿君と葉月君が「何だ?」と声を掛けてくる。
「何でもない」
私は慌てて両手を振った。
そして、横を歩く珠美ちゃんの耳に口を近付ける。
「今のは珠美ちゃんの気持ちを知る賭だったの。意地悪してごめんね」
「“賭”って……?」
「私が鈴鹿君とペアを組んだら珠美ちゃんが嫌がるかどうかを、ちゃんと確認しておきたかったの。
もう大丈夫。私、これから全部葉月君と乗るから」
「……」
珠美ちゃんは、これ以上ないというぐらいに顔を赤く染めて俯いてしまっている。そして、私の手をそっと取って言った。
「さっきの乗り物の時も、私に気を遣ってくれたよね? 有難う」
「ううん。だって今日は、珠美ちゃんが誘ってくれた遊園地じゃない。それぐらい、しっかり弁えてみせますって」
内緒話が終わると同時に、私達はジェットコースターに着いた。列に並ぶ早々、私の横に葉月君がくるよう巧く歩く。無事にそうなった時、葉月君が笑みを漏らした。私は彼にニッと笑ってみせた後、珠美ちゃんと鈴鹿君の様子を伺う。
楽しく喋っていると、次々回で乗れる番までやってきた。私達は、上りの階段にできた待機列の先頭にいる。ここは、人数だけ確認して列を仕切るようで、待機列の前にいるほどジェットコースターの好きな場所に乗れるようになっていた。
鈴鹿君が言う。
「なぁ、どこに乗る?」
「どこでも良いけど……」
私は返事をしながら、ジェットコースターの線路を目で追っていった。こういう絶叫ものは嫌いではないけれど、極端に激しいのは怖いと感じる質である。ずっとわくわくしながら待っているようだった鈴鹿君には悪いが、あまり前でない方が良いなと思っていた。
そこへ珍しく葉月君が意見を述べる。
「俺、後ろでいい」
確か葉月君も、私と同じようにジェットコースターに対して執着を持っていないはずだった。自分と同じ考えの人が提案してくれてホッとする。私は、鈴鹿君の顔を伺った。
しかし、気を悪くするかと思われた彼は、ニコニコと気持ちの良い笑みを浮かべると、「いいぜ」と嬉しそうに言う。
いよいよ、私達がジェットコースターの席に並ぶこととなった。スタッフにフリーパスを提示し、乗降所へ上がると後部座席の方へ歩く。結局、鈴鹿君と珠美ちゃんのペアが一番後ろで、私達がその前の席となった。
少し待って、人をぎっちり乗せたジェットコースターが目の前に着いた。乗客は皆、興奮状態で、大声で話し合う人や笑い声を上げる人達ばかりである。
席が空いたので、私と葉月君は並んで座った。きっちりシートベルトを締め、安全バーを下ろす。どれほど凄いのだろうかと私がドキドキしていると、背後から鈴鹿君の明るい声が聞こえた。
「ジェットコースターって、最前列もいいけど後ろも楽しいんだよな。遠心力がつくっていうか、振り回される感じがより強調されるんだよ」
彼の横で、珠美ちゃんが「そうなんだ」と呑気に感心している。私は、思わず葉月君と顔を見合わせてしまった。どうりで、スピード好きな鈴鹿君が簡単に了承する訳だ。
スタッフの安全確認が終わると、出発のベルが大きく鳴った。そして、ジェットコースターがガコガコとゆっくり動き出す。私は緊張でもう高鳴っている心臓を強く感じながら、背後から身体の全面に大きく掛かっている安全バーにぎゅっとしがみついた。ジェットコースターはベルトに乗り、徐々に高く上がっていく。
「景色、いいな」
横の葉月君がぼそっと言ったが、私には周囲の景色を楽しむ余裕なんてない。引き攣る顔でとりあえず同意した後は、怖くありませんようにとひたすら祈るだけだった。
・
・
・
私達の乗ったジェットコースターが物凄い勢いで線路を駆け抜け、再び乗降所に戻ってきた。鈴鹿君はハイになっていて、大声で楽しそうに珠美ちゃんに話しかけている。私はというと、想像以上だった迫力にすっかり度胆を抜かれていた。安全バーが上がったので立ち上がろうとすると、何かが引っ掛かって阻まれる。
「あれ?」
私は焦った。どうしても腰が持ち上がらない。
すると、横から葉月君が手を伸ばして、私のシートベルトの解除ボタンを押してくれる。途端に、私の腰が持ち上がった。気が動転していて、私はそれを外すのをすっかり忘れていたのだ。葉月君に手を貸してもらいながら、よろよろとジェットコースターから降りた。
「……ごめん」
「平気か? 顔色悪いぞ」
「びっくりしているだけ。すぐに元に戻ると思う」
激しいジェットコースターの急な開放に身体が追いついていないのは私だけでなく、周囲の客達も心なしかフラフラしていた。降りてもまだ頭がくらくらしているので、私の足元はおぼつかない。私はそのまま葉月君に手を借り、ゆっくりと階段を下りた。
とっくに地上に戻っていた珠美ちゃんは、鈴鹿君と出口付近で談笑していた。私の様子を見て、彼女が寄ってくる。
「大丈夫?」
「あはは、こんなんでごめんね。
それにしても怖かったねー。噂以上だったんじゃない?!」
私を気遣ってくれた葉月君の好意で、空いたベンチに座らせてもらった。更にジュースを奢ってもらい、身体の調子が回復するまでゆっくりと休む。
その後、私達四人はフリーパスを最大限に生かして、夕方まで様々な乗り物を楽しんだ。途中、昼食と数回のお茶をした時も含めて、私の横は全部葉月君である。意識してそうなるよう仕向けたのだが、後半は鈴鹿君でさえもこの固定組み合わせをしっかり認識したようで、自主的に珠美ちゃんを連れるようにまでなった。
帰る前に、私達は最後のアトラクションとして観覧車を選んだ。夕焼けを楽しもうという考えだが、遊園地にいた多くの人間がそう思ったようで、観覧車は大盛況である。それでも、本格的に混み始める前に並んだので、三十分強の待ち時間で済んだ。これなら、夕焼けは充分楽しめる。
乗降場へ上がり、順番がやっと回ってきたので、先に珠美ちゃんと鈴鹿君を乗せた。
次に来た観覧車に、私と葉月君が乗る。スタッフが「いってらっしゃい」の声と共に、入口のドアを閉めた。観覧車はゆっくりと上昇していく。
「お疲れ」
葉月君の声に、私は頷いた。
「うん、葉月君もお疲れさま。
──本当に疲れたでしょう?」
「……まぁな。でも楽しかった、来て良かった」
「そう? 私は葉月君を無理に巻き込んじゃった立場だから、そう思ってもらえると本当に嬉しい」
私は、窓から上空を仰いだ。珠美ちゃん達が乗っている観覧車の底部分が見える。
「あの二人、今は何を喋っているんだろう?」
「さぁ……」
「でも、今日のは成功だったよね? 珠美ちゃんと鈴鹿君、ちゃんとカップルでデートしている感じだったもの」
「お前が頑張った甲斐はあっただろうな」
高さが上がっていくにつれ、小さくなっていく周囲の建物を見ながら、私はふと考えた。私と葉月君は、端から見てどうだっただろうか。今日はずっと珠美ちゃんのフォローに回っていたので、私はそういうことを考える暇がこれまでなかった。それに、今になって気付いたのだが、さっきの私の発言は「自分達もそういう感じだった」と暗に押し付けていないか。言っておいて、私は急に恥ずかしくなってきた。誤魔化しついでに、私は窓の外を見るのにより集中した。
もうすぐ頂上というところで、先の観覧車の中が見えた。中に乗っている珠美ちゃん達も私達に気付き、嬉しそうに手を振ってくる。私も椅子から立ち上がって手を振り返した。
「心配する必要もなかったみたいだな」
「あはは、そうみたい。良かった良かった」
私は座り直した。珠美ちゃん達が視界から消え、私達の観覧車は頂上を過ぎた。ゆっくりとゆっくりと、これまでとは逆に下りていく。
ふと前を見ると、夕陽に照らされた葉月君の顔がある。何を考えているのか、ぼーっと外を見つめている彼があまりにも格好良くて、私は暫し見とれてしまった。これだけでもう、今日頑張ったご褒美を貰ったようなものだ。まるで、雑誌の一ページをそのまま実写で見ている感じがする。葉月君の顔に、長い睫の影ができているのが堪らない。モデルとして人気急上昇中の葉月君に憧れている女の子は沢山いるだろうに、今の私は彼を独占しているのだ。この時がずっと続けば良いのに、とついつい思ってしまう。
急に葉月君が私を見た。目と目が合ってしまったので、私は慌てて視線を逸らす。
「今度……」
「え、何?」
「──次は、二人だけで来ような」
「っっっ?!」
びっくりして私が顔を上げると、葉月君はもう顔を横に向けて外を眺めていた。ひえーっと叫びたくなるのを必死で我慢して、私は思いっきり首を上下に振って大きく頷く。手は勿論、拳を作った。
「行く行く! 絶対に行く!!」
「お前、俺達が今、観覧車に乗っている時って分かっているのか? そんなに騒いだら落ちるぞ」
「平気だよー。
あぁ、嬉しいな。次があるっていいね!」
葉月君にこう言われるまで私は、この観覧車で終わりという事実に、とりあえず自分に振られた役割は充分に果たしたという満足感と、それによる精神的な疲労感で一杯だった。それに、一応“仕方なく余り者同士”でペアを組んだ葉月君との、滅多にない幸せな時間に対する未練もあったのだ。それが一気に解消されて、私の中にはいつ来るとも分からない“次”への期待で心が弾んだ。
そう言っている間に、乗った観覧車はかなり低いところまで下りていた。終わってしまえば本当に僅かな時間で、肝心の夕陽はあまり記憶にない。
ガチャッと音がして、スタッフが外側から観覧車のドアを開けた。
「お疲れ様でしたー」
葉月君が先に降り、私に手を差し伸べてくれた。有難くその手を借りて降りる。こういうことを自然にやってくれるところが王子サマだと思いながら、入学式の既視感を覚えた私はつい懐かしい気分になった。
既に降りて待っていた珠美ちゃん達と合流する。私の気のせいかもしれないが、彼女は乗る前より更に幸せそうだった。
私はこっそり珠美ちゃんに近付いてみる。
「観覧車で、何か良いことでもあった?」
珠美ちゃんは私の手をぎゅっと握った。
「……鈴鹿君にね、また機会があったら一緒に遊びに行こうって誘われちゃった」
「へぇ」
「今日は本当に有難う。お陰で、前より鈴鹿君と仲良くなれた感じがするの」
「それは良かった。私も協力した甲斐があったよ」
「うん! 葉月君にもお礼を言わなくちゃね。私、宇宙の果てまでぶっ飛んじゃうかもしれないって思ったぐらい、今日はとっても幸せだったから」
私は敢えて、葉月君から同じような誘いを受けたことは、珠美ちゃんに黙っていた。嬉しがる彼女に対して喜んでいるのは素直な気持ちだけれど、またWデートをしようと、正直今は言われたくなかったからだ。こういうのもたまには楽しいだろうけれど、気持ちの余裕がない私にとってはやはり葉月君と二人だけがいい。彼と出かけるのに慣れてきたら、刺激として逆に利用するのも良いだろうけれど。
帰りも、四人揃ってバスに乗った。それから、着いたバスターミナルで解散となる。
よく“家に着くまでが遠足だ”と言うけれど、何と、あの葉月君が私を自宅まで送ってくれた。家の方向が途中まで同じだったというのが最大の要因だろうが、こんなことは知り合って以来初めてである。「送る」と言われた時には、すぐに信じられなくて夢を見ているのではないかと思ったぐらいだ。
すっかり日も暮れた帰り道、遊園地での話やこれからのことについて、私は葉月君と沢山喋った。珠美ちゃんの言葉にもあったように、私もたった一日で葉月君と随分親しくなれたようだ。これは凄く嬉しいおまけである。
遊園地に行く前に、今日の私はサンドイッチに必ず付いてくるパセリのような役割なのだと思っていた。絶対にメインにはなれない哀れな存在だ。だから表舞台に立てる可能性はないと思い込んでいたのに、こういう風に終わりを迎えるとは、幸せな誤算である。
葉月君とも別れて自室へ戻った後、私は珠美ちゃんの家がある方角に向かって「有難う」と頭を下げた。私も、その気になったら宇宙の果てまで飛んでいけるような感じである。 |
了
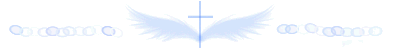
テーマがどうこう……というより、単にWデートを書きたかったのですよ。
王子を攻略している時に(←暇さえあればいつもやってる)
親友が珠美ちゃんの状態で、間違って和馬くんを出しちゃったんですー。
そうしたら早速Wデートに誘われまして。
勿論、私は王子狙いだから最初は彼を選んだのですが
その時の珠ちゃんの台詞が
「じゃあ、仕方ないから私は和馬くんと組むわー」的なニュアンスで
「?」と思ったのですよ。
それなら!と、次は和馬くんを選んだら、滅茶滅茶嫌そうに返事されて
「さっきのは珠ちゃんなりの芝居だったのね!」と分かった訳で。
面白かったので、その様子を自分で書いてみたかったのです。
タイトルは、ミッシェルさんの唄から。
WA3のジェットっぽいタイトルだと思ったので、彼のSSに使いたかったのですが
仕上げた時にそれを忘れてしまいましたー。
なので、ここで無理矢理使用。だから最後に歌詞のキメの部分を使いました。
これを言うと拳を上げたくなりますなー。
(20020727 UP)
|
|