【初めての「」】
|
天気の良いとある平日、私は四時間目の授業が終わると同時に教室を飛び出した。
行き先は、校舎一階端にある購買部だ。お弁当を持ってこない日はいつも、ここでパンを買っている。勿論、今日もそうだ。普段の購買部は立ち寄る生徒が少なくて閑散としているのに、お昼休みだけは物凄い混雑となる。購買部は学校内に一つしかないし、外出して買い物をするのは校則で禁じられているので、弁当を持参しなかった生徒が同じ時間帯にここへ詰め寄るのは当然だ。遅く着くほど長い列に並ばなければいけないし、人気のパンは早々と売切れてしまう。一刻も早く買い物を済ませる為に、私は急いでいた。
その途中で、廊下をしずしずと歩いている瑞希さんに会った。彼女とはクラスこそ違うが、入学式以来の大事な友達だ。ただ、悠長に話すゆとりは無いので手を振って挨拶をするだけにした。
「Attendez un peu ……」
突然、私の左手が後ろにぐいっと引っ張られた。振り返ると、その瑞希さんが私の腕を両手で強く握っている。
「瑞希さん?」
「ねぇ、そんなに急いでどちらへ行くの?」
「購買部だよ。お昼のパンを買うの」
「どうして走ってるの?」
「早くしないと混んじゃうし、欲しいパンが売切れちゃうから」
「ふーん」
私は焦っていた。今は一分一秒が惜しいので、いくら瑞希さんとでも呑気に話をしていられない。
「それじゃ、またね」
そう言って、私は再び走り出した。
しかし、またもや瑞希さんが私の腕を引く。
「瑞希も購買部とやらに行ってみようかしら。一緒に行っても構わない?」
「え? 瑞希さんって、ギャリソンさんが持ってくるお弁当があるんじゃないの?」
お昼になると毎日どこからかギャリソンさんが現れて、瑞希さんにお弁当を届けるのだという噂を聞いたことがある。私は見ていないけれど、財閥のお嬢様ならあり得る話だ。
「それは別にいいの。
さぁ、行きましょう!」
瑞希さんはにっこりと笑うと、私の腕を掴んだまま走り出す。その表情はとても子供っぽくて、彼女の好奇心の強さがよく表れていた。
私が瑞希さんを伴ってようやく購買部に着くと、そこは既に沢山の生徒で溢れていた。やはり瑞希さんと話していた分のロスは痛い。それでも、瑞希さんに悪気が無いのはよく分かっているので、私は現状を悲観しないでさっさと列の最後尾に並ぶことにした。私の後ろに瑞希さんが続く。
「ここが購買部なのね。初めて来たわ」
「普段は、授業で使うような文房具も売っているんだよ」
「瑞希が使っているエルメスのペンもあるのかしら?」
「……そ、それは無いと思うけど」
並ぶ私達の横を、パンが入った白い紙袋を抱えた女子生徒が嬉しそうに走り去っていく。それを見た瑞希さんが、首を傾げた。
「あんな風に喜ぶほど、ここのパンって美味しいの?」
「うーん、味は普通だと思うよ。あの子達は、きっと一番人気の揚げパンを買えたから喜んでいるんだよ」
「揚げパン?」
「もしかして瑞希さんは食べたことない? コッペパンを油で揚げて、砂糖をまぶしてあるんだよ。甘くて美味しいんだー」
さっきの女子生徒同様、私も揚げパンは好物である。ただ仕入数が少ないので、余程早く並ばない限り、買うのは難しい。
「み、瑞希はねぇ、Lucas Cartonのmille-feuilleが好きよ。あと、Tarte des demoiselles
Tatinも良いわね。
貴女は食べたことがある?」
ミルフィーユやタルトだとか、聞き慣れた単語が混じっていたけれど、どうせフランスにある超高級レストランのデザートだろう。外国旅行すらしたことがない私が、そんなものを食べるはずがない。
私が首を振ると、瑞希さんは満足そうに胸を張った。負けず嫌いの彼女は自信回復したようだ。
「それなら今度、私の家で行なうパーティーにご招待差し上げるわ。そこで出す料理は、いつもLucas Cartonの名誉シェフに作らせているから。貴女もきっと、その美味しさにびっくりするはずよ」
「……有難う」
とりあえず私は礼を言った。
それから十五分後、ようやく私の番になった。一番食べたかった揚げパンは既になくなっている。今日は比較的女子が多く並んでいたので、甘いデザートパンから売切れていったようだ。メロンパンや、チョココルネもない。
「えっと……焼そばパンとコロッケパンをください」
私は惣菜パンを指し、代金と引き換えにそれらが入った紙袋を受け取った。
次は瑞希さんの番だ。彼女は小首を傾げて陳列されたパンを見ている。
「おい、早くしろよ!」
男子の荒っぽい声が聞こえてきた。瑞希さんがあまり熱心に見ているので、後ろに並んでいる生徒達はやきもきし出したようだ。彼女も流石にまずいと思ったらしく、私も買った焼そばパンを掴み、スカートのポケットから何かのカードを出す。もしやと思った私は、慌てて彼女の手の中にあるカードを見た。
「瑞希さん、これってクレジットカードだよね? 購買部では、現金じゃないと買えないんだよ」
「何ですって?」
流石、お嬢様である。私は自分のお財布を再び出してその焼そばパン代を支払うと、その場から逃げるように走りさった。
そのまま暫く足を進め、日の当たる中庭に出た。私が無理矢理連れてきたので、瑞希さんはラップに包まれたままの焼そばパンを剥き出しで握りしめている。
芝生で止まると同時に、瑞希さんが不満そうに言った。
「ねぇ、カードが使えないってどういうこと? それってとても不公平じゃない?」
「私達は学生だもの。カードを持ってる方が珍しいよ。
それに、瑞希さんが持っているそのカードだって、ご両親の名義でしょう?」
「だって、これで好きにしていいって言われているもの! 現金でしか受け付けないだなんて変よ」
話していて、私は段々頭が痛くなってきた。やはり彼女とは、常識の物差の目盛りが少し違うらしい。そこが彼女の魅力の一つなのだが、日常生活に支障が出るほどでは、今後の彼女にとっても駄目だろう。いや、もしかしたらそんな庶民の生活とは一生縁なく過ごすのかもしれないが。
「瑞希さん、その辺の個人商店とか小さなスーパーで買い物ってしたことがある?」
「失礼ね。一応あるわよ」
「その時の支払いはどうしたの? そういう所じゃ、カードは使えないよね」
「いつもはギャリソンが払ってくれるもの。
あ、でも瑞希も一人で買い物する時があるわよ。銀座の和光とか、三越とか……このカードで問題無かったわ」
「……」
つまり、普段は現金を持ち歩かないという訳か。今度ギャリソンさんに会ったら、小銭で構わないから彼女に現金を持たせて買い物をさせるべきだと進言しようと決めた。
その時である。
背後から誰かが近付いてきたと思ったら、そのギャリソンさん当人が現れた。
「お嬢様、こんなところにおいででしたか……」
「ギャリソン。何の用?」
「はい、お嬢様のお昼をお届けに参りました。」
「あ、そう。でも今日は要らないわ。購買部でパンを買ったから」
「お嬢様がですか? はて……」
不思議がるギャリソンさんに、私は事情を説明した。途端に、ギャリソンさんが汗を掻きながら私に頭を下げる。
「それはそれは」
けれども、当の瑞希さんはけろっとしている。
「さ、ギャリソンは放っておいて、パンを食べましょう」
「お嬢様! しかしそれではお弁当が……。今日は吉兆に作らせたものですぞ」
「え? 吉兆って、あの“吉兆”? しかも作らせたって……凄いじゃない!」
私は心底驚いた。吉兆とは、超高級老舗料理店である。余程のことがない限り、私とは縁がない割烹だ。声にこそ出さなかったが、ひえーっとおののく。
しかし、瑞希さんは不思議そうに私を見る。
「吉兆だと何が凄いの?」
「だ、だって、私達がお昼ご飯に食べるようなお弁当じゃないよ! 私なんか、お店にすら入れないと思うし」
「それなら、貴女がこれを食べれば良いじゃない。その代わり、瑞希が買わなかった方のパンと交換して頂戴」
「え?」
私の買った惣菜パン……瑞希さんが買ったのは焼そばパンだけだから、彼女が所望しているのはどうやらコロッケパンのようだが、それと吉兆の特製弁当を交換するという。私にとってはこの上ない幸運だし、この機会を逃したら一生食べられないだろうから、とても有難いが……。
私は改めて瑞希さんを見た。彼女の視線は、私が持っているパン入りの紙袋に熱く注がれている。まるで中身を透視しているみたいだ。
それから私は、瑞希さんの横で困ったような顔をしているギャリソンさんに目を遣った。彼は私が見ているのに気付くと、軽く会釈をする。
私の沈黙に耐えられなくなったらしい瑞希さんが、やや苛々したように口を開いた。
「ねぇ、どうするの? 瑞希、お腹が空いたわ」
「え……ええと……もし構わないのなら、是非そのお弁当を食べてみたいんだけど……本当に大丈夫?」
なるたけ失礼にならないように、私は恐る恐る希望を言ってみた。途端に、瑞希さんの顔が輝く。
「じゃ、決まりね!
ギャリソン、お弁当を差し上げて。さぁ、瑞希にパンを頂戴!」
「かしこまりました、お嬢様」
ギャリソンさんが、芝生に大きな布を敷いた。私は瑞希さんと共に、その上に座らせてもらう。厚手なので、青々と伸びた芝生の上だというのにちっとも痛くなかった。
私は紙袋を開けて中からコロッケパンを取り、瑞希さんに差し出した。彼女は喜々と受け取る。
「では、どうぞ」
ギャリソンさんが紫の風呂敷を溶き、桐のお弁当箱を私の前に用意してくれた。蓋を取ってみると、中は縦横それぞれ二つずつ仕切りの板が通っており、全部で九つの正方形に分けられている。その中に、一種類ずつご飯とおかずが品良くあった。
「うわ、素敵っ!」
私は箸を持った。
それと同時に、瑞希さんが焼そばパンの周りを包んでいるラップを剥がす。私はお弁当を食べる前に、彼女の反応を見ることにした。
瑞希さんが焼そばパンを手で小さくちぎった。そこで切れなかった焼そばが、中途半端にパンから下に伸びる。
「食べ辛いのね」
「焼そばパンはね、行儀が悪いけど、直接齧った方が食べ易いんだよ」
「そういうものなの……」
瑞希さんは焼そばパンをじっと見つめた後、手で持ったままのちぎった欠片を口に入れた。もぐもぐと口を動かして噛み、嚥下する。
「あら、意外に美味しいのね。焼そばとパンだなんて、主食同士の組み合わせで変だと思ったけれど、これなら抵抗無く食べられるわ」
「でしょう? しかも、真ん中に乗っている紅ショウガが口休めになるから、味が濃いのに飽きないんだよ」
「ふーん」
瑞希さんが口を大きく開けてパンにかぶりついた。横で見ているギャリソンさんは驚いているようだったが、これもお嬢様の庶民体験の一つだと思っているのか、無言のままでいる。
観察を止めて、私もいよいよ食べ始めた。いよいよ吉兆の初体験だ。何と、献立の詳細が書かれた“お品書き”付きである。
お弁当の中に入っているものは、まるで芸術品のように美しく盛られていた。少しずつ分けられているので、見た目も食べるのも楽しい。献立にあるおかずはそう珍しいものはなかったが、高級食材であろうことは簡単に想像できる。普段食べている炊き合わせも、出汁から違うようだ。私にはやや上品過ぎて、味に物足りなさも感じたが、それでもやはり美味しかった。お金持ちの人はこういうものを食べて生活しているのかと、しみじみ思ったぐらいである。
私がお弁当を全部たいらげた頃、瑞希さんも焼そばパンに続いてコロッケパンも食べ終わっており、ギャリソンさんが魔法瓶で持ってきた熱いお茶を飲んでいた。
「どうもごちそうさまでした。とても美味しかったです」
私は頭を下げて、お弁当箱と箸をギャリソンさんに返した。お品書きは、記念に貰う。
瑞希さんが大きく頷いた。
「私も満足よ。たまにはこういうものを食べるのも良いわね。貴重な経験だったわ。
そうだ! 今度うちのシェフに作らせてみようかしら……」
それではシェフが泣くだろうに。私は心の中で同情した。
「──ところで、瑞希さん」
「何かしら」
「いつもお昼はどこで食べているの? 教室……じゃないよね。私、別の用事でたまに瑞希さんのクラスへ遊びに行くんだけど、姿を見たことがないもの」
「天気が良い日はここよ。ベンチだったり、こうして芝生の上に座ってみたり、色々だけれど」
「じゃあ、もしかして一人で食べているの?」
瑞希さんは下唇を噛むと、横にいるギャルソンさんを見た。
「一人じゃないわ、ギャリソンがいるもの」
「あ、ごめんなさい。そういう意味じゃなくて。
誰か学校の友達と、お弁当を一緒に食べたりしないのかなって思ったの」
「……。
瑞希の豪華なお弁当を、皆に見せつける訳にはいかないでしょう? 学園のエトワールとしては、そのぐらいの気遣いをしなければいけないの!」
瑞希さんは強い口調で言った。ギャリソンさんがおろおろとしている。
私は、彼女の触れてはいけない部分を刺激したらしい。どう謝ろうかと急いで考える。
しかし、私が言う前に瑞希さんが口を開いた。
「で……でも、貴女は違うわよ! 吉兆のお弁当を食べたことがないだなんて、人としていけないわ!
瑞希がちゃんと面倒をみてあげるから、これから毎日しっかり学んだら如何?
ギャリソン、今、瑞希が言った通りよ。明日からお昼のお弁当は二人分にして頂戴」
「かしこまりました」
瑞希さんの言葉を受けて、ギャリソンさんは深々と頭を下げた。
どうやら、瑞希さんは私をお昼に誘ってくれたようだ。私自身は、日によって一人で食べたり、クラスの仲良い友達と机を囲んだりしているので、それでも全く構わない。彼女と二人きりで食べるのは勿論、たまには他の女子も呼んで楽しく食べるのも良いだろう。それに、毎日ああいう素敵なお弁当が食べられるのは、かなりの魅力だ。彼女が言ったように、私にとっては正に舌の勉強になるかもしれない。
有難う、と私が礼を言うと、瑞希さんが子供っぽく笑った。
「たまには、今日みたいなパンでも宜しくてよ。その……早く並べば、揚げパンとやらも食べられるんでしょう? 学園のエトワールとして、そういうものも知っておかないといけないわよね」
私は、瑞希さんの可愛いこじつけに思わず笑ってしまった。
「……今日は楽しかったよ」
「瑞希の方が、もっともっと楽しかったんだから」
「あはは、そう? だったら良いけど」
ギャリソンさんは、私達に挨拶をすると再びどこかへ去っていった。放課後になったら、下校する彼女を車で送る為に、またここへ来るはずである。
残っていた私の焼そばパンは、瑞希さんの希望により紙袋ごと彼女に進呈した。彼女はこれを持ち帰って家のシェフに渡すらしい。きっと、物凄く上品な焼そばパンが出来上がるだろう。
それから、私は瑞希さんと手を繋いで教室に戻った。今日のお昼は、私にとっても瑞希さんにとっても、それぞれ違う意味で思い出深いものになったに違いない。 |
了
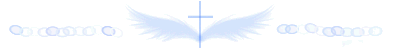
瑞希ちゃんは、すぐに張り合おうとするところが一番好きです。
気を抜くと、彼女が自分を呼ぶ時につい「私」と打ってしまい、
慌てて訂正するというのが何度もありました。
書くのに慣れていないキャラはやはり大変です……。
(20021009 UP)
|
|