【嫉妬】
|
暖かい日の夜、私は家から離れた大きな本屋にいた。家の近所にも個人で経営している本屋があるのだが、欲しい本を扱っていなかったので、わざわざ歩いてここまでやってきたのである。
目当ての本はすぐに見つかった。だが、私はせっかく来たのだからと店内をゆっくり見て回る。漫画本、小説本、PC関連の専門書、はばたき市近辺の案内雑誌、ファッション雑誌……ときて、私は雑誌の棚の向こう側に姫条君がいるのを見つけた。一応手を振ってみるが、彼は熱心に雑誌を読んでいるようで、私には全然気付かない。
私はこっそりと彼の後ろに移動した。間近で見て、やはり目の前の人が彼だと核心する。
「姫条君」
私が背中を突きながら姫条君の名前を呼ぶと、彼はびくっとしながらこちらを見た。
「お、自分か。こんな所で会うなんて奇遇やな」
「うん。私、あっちの棚から手を振ったんだよ。知らないでしょう?」
「ほんまか? 俺、この雑誌読むのに気ぃ取られてて、全然分からんかった。すまんすまん」
私は姫条君の手元を覗き込んだ。流行に煩い彼のことだから、今読んでいるのはファッション雑誌かと思いきや、渋い和食惣菜の写真が沢山載っているものである。
「あ、料理の本?」
「そう、俺は一人暮らしやし、あんまり贅沢できひんし。食べたいモンは作らなあかんねん」
「だって親からの仕送りを貰っていないんでしょう? 凄いよね。私には絶対にできないから、尊敬する」
「うーん。俺の場合、意地もあったしな。とにかく出来るとこまで頑張るつもりやねん。
ところで自分は面白い漫画でもあったか?」
私は首を振る。
「漫画じゃないよ。私はね、氷室先生ご推薦の参考書を買いにきたんだ。家や学校の近くの本屋さんには無かったの。ここに電話をしたら『ある』って言われたから、わざわざ来たんだ」
「おっ! 流石、氷室学級のエース! 自分、いつも勉強頑張ってるもんな〜。
そういや、自分の進路って進学やったっけ。一流大学目指すなんて大変やん」
「あはは、私なんかより頑張っている人なんか沢山いるよー」
他愛のない話をしながら、私は姫条君と共に店内をゆっくり歩いた。結局、他に買うものが無かったので、私は参考書の会計を済ます。すぐ隣で、姫条君も料理の本を買っていた。
「自分、歩いてここまで来たん?」
「うん。今、自転車が壊れているの。親に車で送ってもらっても良かったけど、散歩がてら歩いてきちゃった」
「そっか。じゃ、家まで送るわ」
「有難う」
私はもっと姫条君と話がしたかったので、彼の好意に甘えることにした。
しかし姫条君は店から出ると、道路へ行かずに店鋪脇の駐車場に向かって歩いていく。
「姫条君、どこへ行くの?」
「俺、バイクで来てんねん。ちょっと取ってくるわ」
そう言うと、姫条君は大きなバイクの所へ行った。それはいつか私が放課後に見た、彼が先輩から餞別で貰ったというバイクである。どうやら、私を後ろに乗せてくれるらしい。バイクなど、私は初めて乗るので嬉しくなった。心を弾ませながら私はそれを指す。
「先輩に貰ったバイクでしょう? 乗っているんだ?」
「ああ、頑張って教習所通って中免取ってん。
さ、行こか」
だが、姫条君はバイクに乗ろうとしない。この重い車体を転がしながら、私と共に歩いてくれる。
「姫条君! 送るって……バイクに乗せてくれるんじゃないの?」
「違うで。メット、俺の分しかないし。それに俺、女を後ろに乗せへん主義やし。タンデムはせえへん」
「そ……そうなんだ……」
「あ、今、自分『姫条君ってつまらない人〜』って思ったやろ。
免許取ろうって決めた時から、ずーっと思ってた事やねん。ごめんな」
「ううん。乗れなくて残念って思ったのは確かだけど、姫条君がそうなら仕方ないよ。
それより、押して歩くのって大変じゃない?」
「それは平気。俺の事は気にせんといて」
とはいえ、勝手に想像してぬか喜びに終わったことは、ちょっとショックだった。やはり先輩から貰った大事なバイクだからなのだろうか。それともあまり考えたくはないが、特別な人……つまり“彼女”しか乗せないつもりなのか。
それから私は姫条君に送られながら帰宅したが、正直あまり楽しくなかった。つまらないという訳ではない。どうもバイクのことが気になってしまい、会話に集中できなかったのだ。おそらく姫条君も、私の口数が少ないことに気付いただろう。
「自分、もしかして疲れてるんとちゃう? ちゃんと寝なあかんで」
「うん、有難う」
せっかく姫条君に会えたのに、彼に心配されて終わるとは最悪だ。精一杯の笑顔を見せて、私は帰っていく彼の背中を見つめた。
数日後の放課後。
図書室で自習していて下校が遅くなった私が家に向かって歩いていると、途中の道端であのバイクを止めて佇んでいる姫条君を見つけた。私は姫条君に近付くべく走り出したが、彼の背後に奈津実ちゃんの姿があるのに気が付く。慌てて物陰に隠れて様子を伺った。
姫条君は私服だが、奈津実ちゃんは私と同じように帰宅途中らしく制服姿である。二人は仲良さそうに話していた。時折、楽し気な笑い声が上がっている。
二人は何を喋っているのだろう? おそらく、私と姫条君でしているようなごく普通の会話だと思うが、こうして身を隠して端々を聞いていると、物凄く気になってくる。しかし、これ以上接近すると二人に気付かれてしまう。別に、私が普通に近付いて話しかけても良いのだが、奈津実ちゃんは不機嫌になるだろうし、会話も途中で終わるはずだ。
私が暫くそうして様子を見ていると、二人に動きがあった。姫条君がヘルメットを取り出し、奈津実ちゃんにポンと投げた。彼女はそれを軽く受け取ると、頭にはめる。そして次の瞬間、奈津実ちゃんは止めてある姫条君のバイクの後ろに跨がった。
「?」
私は、急いで姫条君に視線を移した。私に「女を乗せない主義」と言い放った彼は、それを見ても平然としている。というより、ヘルメットを投げたことからいって、彼が奈津実ちゃんを進んで乗せたと考えた方が良いだろう。
この状況に、私は後ろから思いっきり殴られたようなショックを受けた。奈津実ちゃんがバイクに乗っているだけでも悔しいのに、それを私が隠れて覗き見している状況というのが羞恥心を更に煽る。
もうそれ以上見ていたくなくて、私はそろそろと離れた。幸い、最後まで二人に気付かれなかったようなので、私は彼らの姿が完全に見えなくなった途端、道路を全力疾走する。走って走って、もう本当に駄目だと思うところまで私は逃げた。
その後、私は何となく姫条君と話をしたくなくて、彼を避けるようになっていた。とはいえ嫌いではないので、無視などといった失礼なことはしていない。会えば挨拶をするし、話しかけられればちゃんと返事もしたが、以前のように気安く喋らなくなった。
だが、そんなある日の放課後、不審に思ったらしい姫条君にとうとう呼び出された。嫌だなと思っても、ここで断ると後が面倒になりそうなので、しぶしぶ応じる。高等部の中庭のベンチが待ち合わせの指定の場所だ。
私がベンチに着くと、既に姫条君がいた。とりあえず私は挨拶をする。
姫条君は、髪をかきあげながら口を開いた。
「自分、なんで俺に呼ばれたんか分かってんのやろ」
「……」
「俺、余計なことはべらべしゃべるくせに、大事なことに限っていつも言えなくなって。だから俺がつまらないこと言ったんか、それとも言わなあかんことを黙ってたんかで、自分を傷付けてしまったんかって、ここんとこずっと考えてた。でも情けないけど、俺には全く思い当たらへんかった。自分がずっと笑ってくれてたせいかな。
だから悪いけど、俺に自分の不機嫌の理由を教えてくれへんか。そしたらちゃんと謝るから……」
この言葉を聞いていて、姫条君は良い人なのだと私はしみじみと思った。そう、私の不機嫌の理由は彼にあるのではなく、私自身の醜い嫉妬からだ。でも、それを明かす素直さが私には無かった。何も言わず、首を左右に振って答える。
「何で? もう弁解させてくれへんほど嫌いか?」
「そ、そうじゃないよ」
「でも……」
私は慌てた。これでは逆に、私が姫条君を傷付けているみたいである。
どうしようかと思ったが、ここで嘘を吐くのはいけない気がした。観念して、真実を話すことにする。
「ごめんね。本当は、姫条君が悪いんじゃないの。私が悪いの」
「どういうこと?」
「言葉で言っちゃえば、ただの嫉妬かな。
この前ね、姫条君が奈津実ちゃんをあのバイクに乗せているところを見ちゃった。私が姫条君と本屋で会った時、『女は乗せない主義だ』って言っていたよね? 奈津実ちゃんだけは特別なのかなぁ……って思ったら、姫条君と会うのが辛くなったの」
「焼きもちか。それは嬉しいけど、そんな事あったかなぁ。俺、あいつをバイクに乗せた覚えはないで」
姫条君はあさっての方を見ながらうんうん唸っている。
しかし私は今でもすぐに思い出せるほど、あの光景を目に焼きつけているのだ。
「だって本当に見たもの! 十日ぐらい前に、学校から駅に向かう途中の坂の下で、姫条君が奈津実ちゃんにヘルメットを渡して──」
「ちょ、ちょー待てや!」
姫条君が、物凄い剣幕で口をはさんできた。
「……思い出した! 確かそんな事あったけど、自分の思い違いのせいで事実がねじれてるで」
「思い違い?」
「あぁ、俺の話をよぉ聞きや。あん時、俺は確かにあいつをバイクに乗せた。けどな、あれからバイクで走った訳ちゃうで。ほんまに止めたバイクに“乗せた”だけなんや。
……俺が『女を乗せへん主義』って言ったんは、簡単に言うたら二人乗りせえへんってこと。
知ってるか? 自動車の助手席と同じ、事故った時に怪我すんのは後ろに乗ってるほうやねんで。だから自分と本屋から帰る時も後ろに乗せて送ったら簡単なんやけど、もし万が一、事故起こしたら大変やし止めたんや。説明不足で誤解させてもうてごめんな」
私は身体の力ががくっと抜けた。この話が真実なら、私は道化だったことになる。
「でも、姫条君は奈津実ちゃんにヘルメットを渡していたじゃない。二つ持っているのなら、いつでも後ろに人を乗せられるよね?」
「それは俺のメットやで。一度被ってみたいって煩くせがまれたから、しょうがないし、渡したん。俺は後ろに人を乗せて絶対走らへんからな。女の子はさっき言った理由やし。野郎と相乗りなんてむさ苦しいやんか?」
「……勝手に勘違いしてごめんなさい」
これで、私も姫条君の説明を認めざるを得なかった。私が見たのは、あくまで静止しているバイクに跨がった奈津実ちゃんだ。また彼女がヘルメットを被った時、姫条君の頭には何も無かった。
私が頭の中を整理していると、姫条君がニッと笑った。
「さて、もう誤解もなくなったかな。これで好感度アップやー!」
「好感度?」
「ん? あぁ、何でもない何でもない。
ところで、自分の焼きもちはかなりびびったわ。ま、その分、自分に深〜く愛されてるって思ってもええんかな?」
「何、それ」
思わず笑ってしまった。私が冷たい態度を取ったというのに、姫条君はいつもと変わらない軽口を叩いてきたからだ。
「お、いつもの自分に戻ったな。もう少し長くしんみりしてくれたんなら、そこにつけこんでどうにかしたのに。残念やな」
私と姫条君は笑いあった。本当に、事実をちゃんと確認してみれば何てことない──嫉妬したことが恥ずかしくなった思い違いである。
その後、すっかり元通りの仲になった私は、姫条君に連れられて学園の裏にやって来た。高等部の敷地に直接乗り込めないので、いつもここにバイクを止めて隠してあるという。
姫条君はにやにやしながら、私に向かってヘルメットを投げた。
「さ、乗ってみ」
「えぇっ?」
私は驚いたが、奈津実ちゃんのことを思えば頷くしかない。姫条君の言葉に甘えて、奈津実ちゃんがしたようにヘルメットを頭に被った後、止まっているバイクに跨がる。
「気分はどうや?」
「……別に、何とも」
「そうか、じゃ行こか。これからは自分が初めてやで」
すると姫条君は私を乗せたまま、バイクのハンドルを両手で持って前に歩き出した。
「姫条君?」
「ごめんな。後ろに乗せて走れたらええんやけど、やっぱ俺にはこれで精一杯やねん。ちゃんと家まで送るし、我慢してな」
結局、私はそのまま姫条君が転がすバイクに乗せられて、自宅まで送ってもらった。通りすがりに会った人が不思議そうにこちらを見たけれど、姫条君と楽しく話していたので全然気にならなかった。
勿論、本音とすれば、姫条君の背中につかまりたい。そして、風を切って颯爽と走るバイクに乗ってみたいものだ。だが、本当に後ろに乗る人の安全を考えて、タンデムをしないという姫条君の意思はとても素敵だと思う。
とりあえず、こうしてバイクに人の乗せて“歩いた”のは私が初めてだと姫条君が言うし、これで満足しておこう。そして、できることならその権利がずっと私だけにあって欲しいと、心の底から強く願った。 |
了
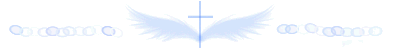
姫条君のバイクの件も、ゲーム本編では詳しい説明がないので
あそこで語られている会話以上に書きようがないのが残念です。
まさか大型じゃないだろう……と思い、一応中型にしました。
限定解除は免許に合格するのも大変ですしね。
(20021017 UP)
|
|