【クラプフェン】
|
四時間目の授業の終わりを告げるチャイムが鳴った。途端に嬉しそうに騒ぎ出す生徒達に、教壇に立っていた教師がムッとした顔をする。
時間は十二時過ぎ。これから待望のお昼休みが始まるのだ。
なのに──私は気が重かった。よし、と無理に気合いを入れて立ち上がる。ロッカーに入れておいた鞄を持って、私は廊下を走った。
階段を降りて昇降口に行く。上履きから外履きのローファーに替えて、校舎裏の芝生に移動した。
豊かに葉を繁らせる大きな木の下には、葉月君が既にいた。私と葉月君は違うクラスなので、今日はこれが初めて会うことになる。私は手を振って彼の元に走り寄った。
「早いねーっ! 私、これでも教室から走ってきたんだよ」
「四時間目が自習だったから。ここでずっと寝てた」
「……そう」
葉月君はまだ起きたばかりなのか、頭を掻きながらぼーっとしている。普段、周囲から怖がられている彼であるが、こういうギャップが私には堪らなく魅力的に思えた。「皆、この葉月君を知らないんだよね」と一人優越感に浸って、そんな葉月君をじっと見つめる。
「何だ?」
「ううん、別に」
私は誤魔化すと、持ってきた鞄に手を伸ばした。チャックを開けて、大きな包みを取り出す。私が作ったお弁当だ。ご飯だけが詰まっている二つの箱を出し、片方を葉月君に渡す。もう一つは私のだ。そして、それらよりも大きな箱の蓋を開け、中を葉月君に見せた。今朝、私が頑張って作ったおかずである。
「じゃーん! 昨日の夜に近所から大きな海老をお裾分けしてもらったので、今日のお弁当で早速使ってみました。
一晩しっかり漬け込んでから焼いた海老のスパイシーグリルに、蟹とピーナッツのミニ揚げ春巻き、茄子の中華風サラダ、スペイン風オムレツ、そしてご飯でーす。間にお醤油付きの海苔を挿んでまーす」
実は、秋に葉月君と森林公園へ遊びに行って以来、私はこうして一方的にお弁当を作り、彼と昼食を共にしている。最初の頃は葉月君の方も私の余計な行動を煙たがっていたようだが、今では嫌な顔をしないし、彼自身が自分の昼食を用意しなくなっている。そしてここは、何となく決まった私達の待ち合わせ兼食事所だ。
私が何故、こんなことをしているかというと……言うのは恥ずかしいが、ただの意地である。私の作ったお弁当を、葉月君に心の底から「美味しい」と言わせてみたい、ただそれだけなのだ。
きっかけとなったその森林公園の時にも、私は自作のお弁当を持っていった。その時は、葉月君に食べてもらう初めての食事とあって、私は緊張しながら心を込めて丁寧に作ったものだ。しかし結果は、寡黙な葉月君の前に撃沈することになる。最終的には辛うじて「美味しい」と言ってもらったけれど、それは私が無理矢理言わせたようなもので、彼の本当の感想はただの無言であった。
そんな訳で、学校がある日の私は葉月君にお弁当を作り続けている。元々料理に興味がない私にとって、毎日のおかずを考えるのも、朝早くから起きてちまちまと調理するのも、かなり大変な作業だ。学校とはばたき市の図書館で料理の本を借りて研究し、分からないことは料理クラブの子達に尋ねまくる。お陰で私の腕は急激に上達した、と思う。アレンジの仕方も大分覚えた。母親は、急に料理に興味を持った娘に嬉しそうな顔をしたが、作るのはあくまでお弁当だけで、夕食などの手伝いなどは全然しなかったものだから、時々軽い嫌味を言ってくる。私は気にしていない。
しかし残念なことに、今日もお昼もいつも通りの結果に終わった。葉月君は手元の白米と、私の分も一緒に盛ってあるおかずによく箸を伸ばしてくれるが、黙々と食した。彼は暫くそうして食べた後、私の懇願めいた視線に気付いてようやく「……美味いよ」と言うのだ。不味く感じていないであろうことは、その箸の進み具合を見ていれば私にも分かる。でも、口に運んですぐに「美味い!」という言葉を聞きたい私にとって、随分物足りない態度だった。また葉月君の方も、毎回毎回同じであるのだからまた困る。私の気持ちを察して、後になって美味しいと言ってくれる気遣いができるのなら、どうしてそれを進化させられないのか? 勝手な望みだと分かっていても、私はそう思わずにはいられなかった。
だから毎日、お昼休みを告げるチャイムが鳴ると、私の気持ちは諦めが八割、希望が二割となる。どうせ今日も言ってくれないのだと分かっていても、何とかして言わせたいという底力が湧いてしまうのだ。
それから一週間が経った。嫌がられないのを良いことに、私は相も変わらず葉月君と一緒に食べる為のお弁当を用意している。
今日は、おかずの参考にするべく、街の本屋に立ち寄っている。毎日毎日新作料理といきたいところだけれど、現実問題としてなかなかそうはいかないので、巧くレパートリーを組み立てつつ、変化を出しているのだった。特に最近は新進料理研究家が多く台頭してきているので、どこの家庭でも作り易い献立が多く載っている主婦雑誌のチェックは欠かせない。
「明日のメインは……つくねにしようか。中に刻んだ竹の子を入れて触感を良くさせて。副菜はれんこんがいいな。明太子と和えて辛くしよう。後は、豚小間と一緒に野菜を炒めて、卵焼きを付ける、と。
あぁ、葉月君のクラスって、明日は体育の授業があるんだっけ。もう少しボリュームあった方が良いのかなぁ……」
そう言いながら、私は料理雑誌のコーナーをうろうろしていた。手を取ってパラパラめくっては次を取り、を繰り返す。
その時、台の上で平積みになっているとある本が目についた。雑誌ではなく、ちゃんとカバーの付いた料理の書籍だ。ちょっと引っ掛かることがあったので、私はこれをじっくりと立ち読みする。それだけでは足りなくて、結局買ってしまった。値段を見ずにレジへ出してしまったので、店員に告げられた金額に一瞬驚いてしまった。ずっと立ちっぱなしで足が疲れており、帰宅する前にどこかでお茶をしたかったけれど、お財布はすっかり空なので、気力を振り絞ってまっすぐ帰る。
翌日、お昼休みが始まると、私はいつもの通り校舎裏へ急いだ。そこに葉月君はまだ来ておらず、私は用意を整えながら彼を待った。
十五分ほど経っただろうか。五分前後の遅刻なら二人ともよくあるけれど、葉月君がこんなに遅れるのは珍しい。お腹も空いてきたし、何かあったのかと葉月君の携帯電話に連絡を入れようかと思い始めた時、ばたばたという足音と共に彼が駆け込んできた。
「悪い、待たせたか?」
「ちょっとね。でも平気だよ」
「四時間目の現国が、チャイム鳴っても終わらなかったんだ」
「あぁ、あの先生なら仕方がないよ。熱心なのは良いんだけど、休み時間に急な用事がある時は困るよね」
葉月君が腰を下ろして落ち着いたところで、私は既に用意しておいたお弁当箱を彼の前に出した。蓋を開けて、彼に中身を見せる。
おかずは、昨日に私が本屋で考えた通りだった。葉月君は、私が差し出した白米入りの弁当箱と箸を受け取り、早速口に運んだ。
私も、自分の分のご飯と共用のおかずを食べながら、葉月君の様子を伺う。しかし彼はおかずを一通り食べたけれど、やはり何も言わない。顔を顰めたりすることは一度もなかったから、いつものように「不味くはない」のだろうが。
あまりじろじろ見るのも失礼なので、私は自分の食事に集中することにした。今日は比較的作り慣れたメニューだったので、味に自信がある。
二人して昼食をぺろりと平らげて、それぞれ持っていたペットボトルのお茶を飲んだ。
頃合を見計らって、私は鞄から別の包みを出す。
「今日はね、デザートというか食後のお菓子があるんだ。葉月君のクラス、体育の授業があったでしょう? まだ足りないかと思って作ってきたんだけど、食べられる?」
「……あぁ」
葉月君は普通に返事をした。無理に食べさせてはと思ったけれど、これなら平気そうだ。
私は包みを開ける。表面に粉砂糖を振るった、中央に穴の開いていない拳大のドーナツが二つある。持つ手が汚れないよう紙ナプキンを添え、私はドーナツを葉月君に渡した。
「ん、サンキュー」
ちゃんと昼食を食べたというのに、葉月君は躊躇いなくドーナツを食べ始める。二〜三口目だろうか、葉月君の動きがぱっと止まった。
「──美味い」
「ほ、本当?」
「あぁ。美味しいし、凄く懐かしいお菓子だ。
これ、俺を意識して作ったのか?」
返事をする前に、私も食べてみた。見かけはふんわりと柔らかく揚がったドーナツだが、中身にアプリコットジャムを入れてある。生地自体の優しい甘さと、ジャムの際立った甘さの差がとても美味しい。
「へへへ。実を言うと、昨日本屋をぶらぶらしていたら、ドイツ料理の本を見つけたんで、買ってみたんだ。
葉月君のお祖父さんってドイツの方なんでしょう? このお菓子はドイツでメジャーな家庭料理だって言うし、もしかしたら葉月君も小さな頃に食べたことがあるかもと思って、作ってみたの」
今、葉月君に言ったように、私が本屋で見つけたとある本というのは、ドイツ料理を初心者向けに紹介しているものだった。嬉しいことにあまり堅苦しいものでなく、簡単に作れそうなお菓子も沢山乗っていたのが購入の決め手である。その中で、私の料理レベルで楽に作れそうだと思えたのがこのドーナツ菓子・クラプフェンだった。ドイツ全土で日常的に食されるお菓子であり、地方によって呼び名は変わるようだが、味や形はほぼ同じだという。また、生地だけでパンのように食べたり、中へ入れるものも様々なジャムだったりクリームだったりして、元々が素朴なだけに味の広がりは豊かそうだ。
これなら美味しいとすぐに言ってくれるかもしれない、という私の読みは、ずばり当たったことになる。ずっと抱いていた願いが叶って、私は嬉しくて堪らなかった。これで駄目だったらもう、永遠に聞けないような気すらしていたのだ。
葉月君は、ぱくぱくと食べている。
しかし半分が過ぎたところで、葉月君が「ん?」という顔をした。
「中に何か入っている──紙?」
葉月君は、食べかけのクラプフェンに指を当て、中から小さな紙を穿り出した。ちなみに、調理途中で偶然入ってしまったものではない。大晦日などに食べるクラプフェンには、おまけの楽しみとして色んな運勢を書いた紙を入れておくのだと、買った本に書いてあったのだ。今日はその大晦日でも何でもないが、私が初めてドイツを意識して作ったお菓子であるので、記念として入れたのである。葉月君は紙を見ると、ふふっと口元を綻ばせた。
「こんなところまで似せたんだな。あぁ、大吉だって」
「たった二個しか作らないんじゃ種がもったいないから、他の友達にも分けようと思ってそれなりの量を作ったの。でも大吉はたった一個だよ? やっぱり葉月君は凄いねー。
さて、私の運勢はどうだろう」
私は急いでクラプフェンを食べた。中から出てきた紙には“吉”とある。まぁ、こんなものかと納得した。ただ、葉月君の素直な「美味しい」という感想をやっと聞けたのだから、“吉”どころではなかったけれども。良かった良かったと幸せを実感しながら、私はクラプフェンを食べ終えた。
手に付いた僅かな汚れを払って、私達は全部の食事を終えた。空になったお弁当箱を鞄にしまう私を見て、葉月君が柔らかな笑みを向ける。
「なぁ……もしかして、俺に自分から『美味い』って言わせる為にこれを作ったのか?」
「ははは、バレた? だって、いつも私が言わせているみたいなんだもの。もし作戦が当たったら、葉月君は懐かしさの勢いで言ってくれるかなーって思った」
「お前、いつもは『美味いって言え』って目で煩く言ってくるのに、今日に限って諦めがよくて、何か企んでいる顔をしていたから」
「だって、頑張って作るからには、美味しいって喜んでいるのを見たいよ。もし不味くて言えないのなら、作る方が頑張らなくちゃいけないけれど──そうじゃないんでしょう?」
「あぁ」
「でも良かった。私、さっきの葉月君の態度で、これからもお弁当作れるよ。
って……明日からも私が葉月君のお弁当を作っても良いよね? 迷惑じゃないよね?」
「いい加減、俺も反省する。今までつまらない思いをさせて悪かったな。
また弁当を作ってくれると嬉しい。あと、こういう甘いのも」
私はホッと一安心した。わざわざ宣言しなくても、せっかく手に入れた“葉月君と一緒にお昼を食べられる権利”を逃すつもりはさらさらなかったが、内心嫌がられていたらどうしようかと思っていたのだ。これで、心置きなく今まで通りに続けられる。
私は大きく頷いた。
「うん、分かった。どうも有難う」
葉月君は満腹で眠くなってきたらしく、小さな欠伸をした。
「俺、少し寝るから。チャイムが鳴る五分前になったら起こしてくれないか?」
「いいよ」
腕を枕代わりにして、葉月君は芝生の上にごろんと横になる。私は、鞄の中に図書館で借りた小説の文庫本を入れていたので、それを読んで時間を潰そうとした。
不意に、眠り出したはずの葉月君が声を出した。
「お菓子の中に入っていたおみくじ、当たってるな」
「ん?」
「俺、十数年振りにあれを食べられて、凄く嬉しかった。忘れていたはずの昔のことが、ぱーっと頭に浮かんだ。俺にとっては、本当に“大吉”だったよ。それに……美味かったし。サンキュー」
「……う、うん」
これでは私の方が“大吉”ではないか。葉月君は目を瞑っているので、照れで赤くなった私の顔を彼が見ないで済むことにホッとした。こんなにやけた顔、恥ずかし過ぎて見せられたものではない。
少し憂鬱めいた午後が、この瞬間から急に輝きだした。安らかに寝息を立てる葉月君を見ながら、私は翌日のお弁当の献立を早速練り始める。今度はこんな裏技に頼らず、彼に言わせてみせようと思う。 |
了
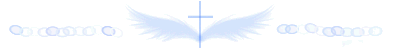
クラプフェンは実在するお菓子ですが、文中で説明したように
ドイツ国内でも場所によって色々な名前で呼ばれているようです。
今回のときメモGSでは、キャラの過去が中途半端にしか描かれていないので
昔の葉月君に関して殆ど書けないのが残念です。
(20020722 UP)
|
|