【昼の風景】
|
学校がある平日、私はいつも欠かさずお弁当を作っている。
調理台に用意するお弁当箱は三つ。小さいのは私のご飯用。その次の大きさのは、何と葉月君用だ。一番大きな箱は、二人で分けて食べるおかず用である。
ご飯は簡単でいい。朝、炊いたものを詰めるだけだからだ。海苔や多彩なふりかけを使ったり、俵型に握ったり、枠を使ってちまちまと懐石風に詰めたり……と、バリエーションは豊かにできる。
問題はおかずだ。まるでもう家庭の主婦になったかのように、毎日毎日私は悩んでいる。お弁当を作ろうと決めてから、基本とされる料理を母親から習い続け、今では暇さえあれば図書室で料理の本を借りて研究するようになった。主婦雑誌や新聞の料理記事のチェックとスクラップも欠かせない。
特に、私には格闘している食材があった。葉月君の嫌いなカイワレだ。秋に、葉月君と一緒に森林公園へ行った時に判明したのだが、彼はこのカイワレを苦手としている。どうも、苦味のある生野菜全般を好きではないようで、お弁当に入れても箸を避けてしまう。
偏食は無いに限る。私は、お節介ながらも何とかしようと、週一回のペースでお弁当にそれを入れているのだ。
葉月君がおかずを見た時にカイワレだと分からなければ良いだろうと、最近は細かく刻んで他の食材に混ぜている。それだと、味付けを濃くしてしまえば全く分からない。たまにその苦さを感じて、葉月君が「ん?」と顔をしかめることもあるけれど、私は無視して笑っている。
だが、果たしてこれで良いのだろうかと思うようになった。葉月君がカイワレを食べてくれるに越したことはないけれど、誤魔化しているのでは、好き嫌いを克服したとは全く言えない。葉月君はずっとカイワレを苦手とするだろうし、私が頑張っている意味もなくなる。
さて、明日はカイワレを入れる日だ。
どうしようかと私は頭を抱えて料理本を睨む。
そして翌日の昼休み。
いつも通り、私は葉月君と中庭で待ち合わせた。
日当たりの良い芝生に座り、私は早速お弁当箱を出す。ご飯が詰まったものを葉月君に渡し、おかず入りのを二人の間に置く。
和風醤油たれのミートボール、ぶりの照焼き、八宝菜、ミニトマト、シラス入りの卵焼き……そしてカイワレのベーコン巻きだ。誤魔化しは微塵も無い、正攻法である。葉月君は、私がお弁当箱の蓋を開けた瞬間にそれが目に入ったらしく、うっと言って顔をしかめた。私は何も聞かなかったことにし、どうぞと進めた。
私と葉月君は、他愛のないことをだらだらと喋りながら楽しく過ごした。お弁当は、ご飯もおかずもどんどんなくなっていく。しかし四つ入れたカイワレのベーコン巻きだけはしっかり残っており、異様な存在感を放っていた。私は、己の分として半分の二つを食べる。
「ふう、お腹いっぱいになっちゃった」
私は先に箸を置いた。
「あぁ。美味しかった。サンキュー」
葉月君も、空になったご飯用のお弁当箱の蓋を閉めた。続けて箸を置こうとするので、私は慌てて口をはさむ。
「ねぇ、まだおかずが残っているよ」
それは勿論、カイワレのベーコン巻きだ。葉月君は首を左右に振る。
「……お前が食べればいい」
「私は食べたもの。葉月君が食べて」
「いらない」
やはり今回も葉月君は素直に食べないらしい。まぁ、これぐらいは私の予想範囲内だ。負けるものかと、次の手を打つ。
「ほら葉月君、カイワレ君が泣いているよ? せっかく食べられる為にここまで育ったのに、忌み嫌われてお弁当箱に残るだなんて可哀想じゃない」
「カイワレ君?」
困った時の“カイワレ君頼み”だ。最初に森林公園でこう言って以来、私は時々わざとらしく演技をして、葉月君を脅している。
しかし葉月君はふうと息を吐くと、私をじろっと見た。
「それ、もう飽きた」
「え?」
葉月君は箸こそ持っているものの、目線を周りの景色に移している。カイワレが残っている弁当箱には見向きもしない。
どうしようか。
飽きた、と言われても私は困ってしまう。いつもこれで成功していたので、他を考えたことがないのだ。何か気のきいた言葉でも出ればいいのだが、私の頭はすっかりパニックになっている。
私は弁当箱を見た。
残っている二つのカイワレのベーコン巻き──私は別に嫌いではないので、葉月君の代わりにパクッと食べても構わない。ただ、それでは悲しいし、わざわざこのメニューを入れた甲斐がなくなる。
私は必死で考えた末、口を開いた。
「わ、私、葉月君に食べてほしくて、頑張って作ったんだよ。美味しいから試してみて」
だが、葉月君は微笑むだけで、箸を動かそうとしない。
「お願いー」
「いらない」
「そんな」
どうしても葉月君は食べないつもりのようだ。
私は諦め半分で、最後の手を使った。
「──これを食べないと、葉月君とはもうデートしないよ?」
その瞬間、葉月君は手からぽろりと箸を落とした。そして彼はそれを拾いもせず、私をあの涼やかな目で見つめてくる。
「えっと……」
葉月君が何か言ってくれないと、私が困る。言い慣れないことを口にしたので、顔が恥ずかしさでカーッと火照り出した。葉月君の目には、真っ赤になっている私が見えているはずだ。
暫くすると、葉月君が落ちた箸をようやく手に取った。
私は恐る恐る言う。
「葉月君は、私とデートできなくても困らないの?」
もしも葉月君がこう考えているとすれば、私は大きな勘違いをしていたことになる。言葉はもう空気に溶けてしまったから取り返しがつかないけれど、すぐにでもごめんなさいと謝らなければ。
私は、全身に冷や汗をだらだらながしながら返事を待った。
葉月君がゆっくりと口を開く。
さぁ、どちらだ?
「……別に。できなくてもいい」
「えええっ?」
どうやら私の発言は裏目に出たようだ。しまった、と心で嘆くがもう遅い。
「そ、そうなんだ」
私はがっくりと肩を落とした。もう、お弁当を食べてもらうどころの話ではない。これ以上何も言う気が起こらないので、私はお弁当箱を片付けることにした。
しかし途中で、伸ばされた葉月君の手によって止められる。
「葉月君?」
「さっきの、嘘。ごめん」
「え?」
私は葉月君を見た。
葉月君は可笑しそうにクククと笑うと、私がしまいかけたお弁当箱を奪い、カイワレのベーコン巻きを二つ一緒にサッと手で摘んだ。そして一気に口に入れた後、顔をややしかめながらもぐもぐと噛んで嚥下する。
私はハンカチを差し出した。
「大丈夫?」
「あぁ、平気」
葉月君は私のハンカチで手を拭くと、脇に置いておいたペットボトルのお茶をぐいっと飲んだ。そして、はぁっと大きく息を吐く。
「お前とデートできないと困るからな」
「ほ……本当?」
葉月君は大きく頷いてくれる。でも、私はまだ信じられなかった。
「本当に本当?」
「あぁ」
「本当に本当に本当に本当?」
「……しつこい」
「ごめん」
怒られて、ようやく私も笑えた。何度も確かめたくなるような気持ちだったので、私は心底ホッとしたのだ。
「──俺、ちゃんと食べたからな。今度の休みにどこかへ行こう。
植物園がいいな」
「うん。勿論OKだよ。その時は、葉月君の好物だけでお弁当を作るね」
「あぁ、頼む。これでも、お前のお陰でカイワレも大分食べられるようになったんだけど、やっぱりまだ進んで食べる気にはなれないからな」
葉月君は、やれやれというように肩をすくめた。そんな彼を見て、私も顔が自然にほころぶ。
先程はもう駄目かと心底悲しかったのだ。嘘で良かった、しみじみ思わずにいられない。
私は、空になったお弁当箱を今度こそ片付けて昼食を終えた。それから、急遽決まった週末の植物園デートの打ち合わせを二人で行なう。
しかし私の戦いはこれで終わりではないのだ。今週は何とか無事に終わったが、また来週になれば、お弁当に入れるカイワレ料理と格闘しなければならない。ただ、次回からは自ら墓穴を掘るような発言は絶対に止めようと誓った。こんな緊張を味わうのは、本当にもうごめんだと思っている。 |
了
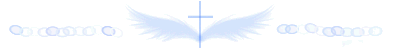
馬鹿ップルお弁当話です。
ええとSS「クラプフェン」を書いた頃、同時に書き出したもので
たった数行打っただけで放置しておりました。
カイワレと格闘するというテーマはその最初の文にあったので
すぐにそのまま続けられたのですが
どういう展開にするかを全く覚えておらず
適当に書き流したという感じです。
その割には変に時間がかかってしまってイヤーな気持ち。
(20021118 UP)
|
|