【優しい魔法】
|
よく晴れた夏の日のお昼過ぎ、私は市内の美術館を訪れていた。
横には、あの三原色君がいる。色気も何も無いけれど、一応デートというものだ。
しかもこの美術館の特設会場では、期間限定の特別企画として三原君の個展が行なわれていた。彼がここ数年に仕上げた作品だけを集めて展示しているのだ。作者自らが横で解説してくれるというのだから、私にとってこれ以上の幸せはない。
その特設会場に入るには、入館券とは別に入場料を取られる。切符売場で応対したスタッフの女性は、三原色本人の突然の登場にびびり、「少々お待ち下さい」と言って裏へ駆け込んだ。しかし三原君自身は何も考えていないようで、別のスタッフに声を掛けて二人分の切符を買う。もしも私が三原君なら、スタッフにわざわざ名を明かしてタダで入るところなのに、彼にはそういう偉ぶったところが無いらしい。
「これはこれは、よくいらっしゃいました」
受付スタッフに呼ばれたらしいかっぷくの良い老人が、両手を広げて現れた。三原君は臆することなく彼と握手をする。どうやら老人は、ここの館長のようだ。彼は、三原君の後ろにいた私に目を遣った。「何だ、この子娘は」と言うような視線のように思えたが、私は愛想笑いをして目礼をする。今日は朝からとても暑かったから、Tシャツにプリーツスカートとラフな格好にしてしまったけれど、こんなことならブラウスぐらい着てくれば良かった。後悔しても後の祭なので、これ以上は気にしないように考えたが。
館長は先を歩き、私達と一緒に作品を鑑賞するつもりらしかった。しかし、三原君は首を振る。
「今日は、一人の美術愛好家として来たんだ。義理のお節介などこの僕には必要ないから、邪魔しないでくれ」
館長はうっと呻いて不快そうに眉を寄せたが、引き攣った笑いを浮かべて大人らしく去っていった。三原君が、やれやれと呟いて笑う。
「僕の大事な連れをあんな風に見るだなんて許せないからね。平気だったかい?」
あの視線に三原君も気付いていたのだ。大事な連れ、という言葉に私は嬉しくなる。
「うん。でも美術館なんだし、もっとちゃんとした格好をすれば良かった。迷惑をかけてごめんなさい」
「いや、君は謝らなくていい。僕が生み出す芸術は、来る人の服装を選ぶような堅苦しいものじゃない。僕の素晴らしい作品は、万人に公開されるべきだ。本当は、こうやって別料金にされているのも不本意だよ。中にはそれで敬遠し、僕の作品と出会えない人は沢山いるだろう。それは、悲しむべき不幸だ」
「……そうだね」
三原君の作品は、皆が気楽に見られる公共施設に飾られていることが多い。彼はこのはばたき市が世界に誇るアーティストなので、そういう意味でよく使われているのだと私は思っていたけれど、もしかしたら彼のこうした願いが含まれているのかもしれない。
その辺に沢山転がっている自称アーティスト達は、三原君とは逆だ。己の才能よりも、プライドばかりを磨こうとする。
私の配慮へはともかく、才能溢れる三原君が素晴らしい考えをしていることに、私は感服した。流石だなと、改めて彼を尊敬する。
それから私は三原君の丁寧な説明を聞きながら、彼の作品を一つ一つ丁寧に拝見した。休日の午後とあって、特設会場の中は少し混雑している。
若いOLの二人組が三原君の存在に気付いた後、連鎖的に騒ぎが起こった。中にはサインをしてくれと煩くせがむ中年女性もいたが、三原君が笑顔でやんわりと断ると、遠巻きに彼を見るまで静まった。
三原君と一緒にいたことで、私は女性客からの不躾な視線を大量に受けたが、先程の館長ほどではなかったので平気だった。逆に、こそこそと噂話をされて気分が良かったぐらいである。ただ、それは三原君が凄いからであるので、私は勘違いして高飛車にならないよう気を付けた。
そんな時、数人の子供の大きな嬌声が聞こえてきた。作品に感激して出されたとは思えない、場違いなほど煩い声である。私が顔をそちらへ向けると、幼稚園生ぐらいの少年達が数人でバタバタと遊んでいた。すぐ傍では、彼らの親らしき男女達が子供達を何とかなだめようと必死になっている。却ってそれが騒ぎを助長させているとも知らずに。
私が推測するに、親達に連れられて子供達はここにいるが、幼い彼らは芸術作品を静かに鑑賞することをまだ知らないらしい。だから飽きて、こうして騒いでいるのだろう。子供達は今すぐにでも外へ出たいようだが、親達はまだ中にいたいようで、そこで歪みが生じている。
親達は、子供達を叱りながら三原君を怖々と見ている。私も、こうした場面に出くわした彼がどう出るのかが気になったので、横で彼を静かに見守った。
三原君が小さく咳払いをする。その後、つかつかと子供達に歩み寄った。
子供達は、まさか目の前にいる三原君がこれらの作者だとは知らない。だが周囲の雰囲気から、彼がその辺にいる普通の客ではないと感じ取ったようで、とりあえず騒ぐのを一旦止めた。
三原君は、子供達の目線に合わせるように腰を屈めた。
「こんにちは。僕の個展へようこそ。
作品を見てくれているのかな?」
子供達は頷く。しかしこれは優等生風に返事をしただけで、あくまで建て前であろう。
「ここにあるものは、僕が全部作ったんだ」
「この絵も?」
一人の男子が、すぐ傍にあった大きな油絵を指した。
「勿論。最初の下絵から仕上げまで、頑張ったんだよ」
「大変だった?」
「まぁね。でも、絵を描くのはとても楽しいから」
「へぇぇ」
口を開けて驚いている子供達に、三原君が優しく笑いかけた。
「そうだ! こうしてせっかく来てもらったのだから、君達だけに秘密を教えてあげよう。
内緒にしてくれるかい?」
「いいよ!」
「何、何?」
秘密と聞いた途端、子供達の顔がパッと輝く。三原君は満足そうに頷いた。
「実はね、この美術館に飾られている絵の中で、本物の虫を塗り込めたものが一つだけあるんだ。上から絵の具を乗せただけだから、見たらすぐに分かるよ。どれがそうなのか、皆で探してごらん」
子供達は、ワーッと歓声を上げて散っていった。先程までのつまらない表情は消え、己が一番最初に絵の中の虫を探そうと、必死になって絵を見ている。
私は、三原君に近寄った。
「どういうこと?」
三原君は楽しそうに絵を見る子供達に視線を向けて、フフッと微笑する。
「今、僕が言った通りさ。
とある油絵を床に置いて仕上げている最中、僕の知らない間に一匹の虫が乗っていたんだよ。邪魔だと思った僕はすぐに追い払おうとしたのだけれど、虫は既に死んでいた。
僕は虫を退けようと思った。でもふと、虫は何らかの縁があってその絵の上で死んだんじゃないかと思ってね。どうせならそれさえも絵に生かそうと、虫をそこから動かさないよう慎重に作業したんだ」
「ふーん」
「僕の絵の素晴らしさは万人に理解されると思うけれど、子供に難しい美術の話をしても無理だから。強制的に芸術に触れても、ちっとも楽しくないだろう? それではいけないんだ。
虫をその絵に塗り込めた時は、まさか将来こんなことになるなんて思ってもみなかった。でも急に思い付いたとはいえ、僕のこの提案なら、皆が素直に興味を持てると思うんだ。楽しい思い出と一緒にね」
「うん」
おそらく、子供達には強い印象として今日が残るだろう。美術品を相手に探し物など、そう滅多にできるものではない。
我先にと虫を探す子供達を見て、私はとても羨ましくなった。三原君と親しく知り合った今でこそ、芸術に興味を持ってこうして美術館などに足を伸ばしているが、幼い頃はつまらないとしか感じられなかったのだ。世間で素晴らしいとされている作品を見ても興味は無かったし、売買されている金額ばかりが気になって、その値段の高さでしか価値を計れなかった。もし、こういう楽しい経験を一度でもしていたら、少しは変われていただろうに。感受性が敏感なうちに良い芸術と触れあうことは大事らしいから、その点で私は損をしている。
「さぁ、君も探してごらん」
「うん」
三原君に促されて、私も探すことにした。また、他の見学者達も次々に参加していく。
その特設会場にいた皆は、三原君が仕掛けた魔法にかかったようだった。それは芸術を理解するのに今後大きく作用し、皆に楽しい思い出と幸せを運ぶに違いない。 |
了
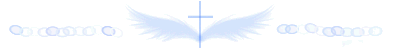
色サマは一度しかクリアしていないので
口調がこれで良いのかと少し心配です。
芸術に対してはやや偉そうに、そして勿体ぶった感じで書いてみました。
虫を塗り込めた絵というのは、実際にちょこちょこある話だそうで。
主人公ちゃんの最後のモノローグは私の言葉そのものです。
(20021020 UP)
|
|