【不覚の後】
|
今は、三時間目の授業中である。
会議室にいる私は、ブラウスの左袖を二の腕までまくり上げて立っていた。
これから私は初めての献血をするのだ。今日は学校に献血車が来ており、希望者は三時間目にこの会議室へ来るよう言われていた。献血など今までやったことは無いが、一度ぐらいは体験してみたいと思っていたので、同じクラスの女子数人と誘い合わせて参加したのである。そこに、三時間目が大嫌いな古典の授業で、公然とサボれるからという理由があったのは内緒だ。
広い会議室は、多くの生徒でそれなりに混雑していた。皆、献血を早く終わらせて授業に参加しようという気はさらさら無いようで、室内はのんびりとした空気に包まれている。
不意に後ろから名前を呼ばれた。
振り向くと、奈津実ちゃんが私のすぐ後ろにいる。私は笑顔で彼女に話しかけた。
「奈津実ちゃんも献血するんだ?」
「うん。あんたも授業サボりたくて来たんでしょ?」
「あはははは、分かる?」
「ここに来てる奴って皆そうだもん。勿論、私もね」
検査の列が空いたので、そこに並ぶ。まずここで採血をし、血液の状態を調べてもらうのだ。
私は奈津実ちゃんと並んで椅子に座り、同時に血を採ってもらう。
「ここでさ、貧血で駄目だとか言われるとちょっと気分良くない? 何だかか弱い感じがしてさ」
「そうだね。でも、やっぱり私達は大丈夫みたいだよ」
「私なんか、姫条君に言われちゃったよ。『自分、少しは血ぃ抜いた方がいいで。ちょっとは落ち着けるんちゃうか』だって。私ってそんなに血走ってるかな」
「姫条君なりの冗談なんだよ」
「大体、あいつの方が血を抜いてもらうべきじゃない? ちょっと可愛い女の子を見ると、すぐフラフラするんだから。
ねぇ、あんたも姫条君と仲良いみたいだけど、もしかして狙ってるの?」
「えぇ?」
どうやら奈津実ちゃんは私に探りを入れているようだ。
「だって、姫条君ってばあんたの話ばっかりするんだもん。私と喋っているのにだよ? 失礼しちゃうよね。あんたが姫条君を狙っているのだとすると、こっちも考えがあるんだから」
「そ……それはたまたまじゃないかな。私、そんなに姫条君とは喋ってないよ。会ったら挨拶する程度だし。奈津実ちゃんは一緒に買い物とか行く仲なんでしょう? 私とは比較にならないじゃない。
それに私は姫条君を友達としか見ていないし、第一私の好きな人は──」
最後はごにょごにょと呟いて誤魔化す。奈津実ちゃんが不思議そうに私を見たが、慌てて首を左右に振って「何でもない」と答える。
奈津実ちゃんは入学当初から姫条君を好きらしい、というのは、私にもよく分かっていた。彼女から相談されたことは一度も無いけれど、この態度や発言を考えれば丸分かりだ。それに彼女の方も、私が察しているのを前提として話してきている。私は奈津実ちゃんが大好きだし、相談を持ちかけられるのは嬉しいけれど、時折こうして探りを入れられるので困っていた。
姫条君のことは好きだ。但し、大事な男友達として。
実際、奈津実ちゃんと姫条君はとても良い感じなのである。奈津実ちゃんはああ言っていたが、私からすれば姫条君が彼女を話題にする時は、顔が少し和らいでいると思う。だからどちらかが告白すればすぐに進展するはずなのに、照れがあるのかなかなかそうはいかないらしい。余計な嫉妬を抱かれるのも疲れるので、私としては早く二人がくっついてくれると嬉しいのだけれど。
私には、ちゃんと好きな人がいる。
誰にもいえないが、担任の氷室先生だ。
私を親友と認めてくれる奈津実ちゃんにも、悪いが話していない。彼女にとって、氷室先生は天敵だそうだからだ。
氷室先生は表面上は怖いけれど、その反面、一旦懐に入ってしまえばとても優しくしてくれる。何を隠そう、私は先生と休日にデートまでしているのだ。先生は照れて「社会見学だ」と言うけれど、中身は普通のデートと変わりはない。もしかしたら私以外の生徒に声を掛けているのかもと思い、慎重に調べたりもしたが、そういうことは一切無かった。だから私にとって先生が特別なように、先生にとっても私が特別なのだと信じている。
だからこそ、本当は奈津実ちゃんに何もかも話したかった。こんな私でも、氷室先生との付き合いで悩みはある。その最も大きな問題は、立場上、交際を大っぴらに公表できないことと、なかなか会いづらいことだ。また、奈津実ちゃんが姫条君のことで愚痴を吐くように、私も氷室先生への不満を相談したい。秘める恋はただそれだけで魅力があるけれど、その代償として大きな苦痛を伴うのだと私は常々実感させられているのだ。
さて、検査が終わっていよいよ採血となった。今度もまた、奈津実ちゃんと一緒になる。
椅子に座って腕を出すと、患部を消毒された。注射を含めて、針を刺される瞬間はどうしても嫌なので、顔を背けて目をギュッと瞑る。
腕にチクッと痛みが走った。顔を正面に戻し、薄目でちらっと腕を見ると、太い注射に私の血がどんどん吸い取られていく。そのまま見るのは辛かったので、すぐにまた目を閉じた。
「はい、終わりましたよー。しばらくここを押さえていてね」
採血した部分に絆創膏が貼られた。私は空いている手でそこを圧迫しながら腰を上げる。隣でやってもらっていた奈津実ちゃんもほぼ同時に終わっており、私達は渋い顔で見合った。
「やっぱ、注射針が刺さる時って怖いっ! 私の友達に、この瞬間がたまらなく好きだって言う奴がいたんだけど、絶対変わってるよね」
「うん。私も見ていられなくて目を瞑っちゃった」
まくっていたブラウスを元に戻し、私と奈津実ちゃんは会議室の端に椅子を移動させて座った。一緒に来た同じクラスの女子達も、殆どがそこにいる。
スタッフからお菓子と紙パックのオレンジジュースを手渡された。それは後で具合が悪くならないよう、きちんと糖分を補給しておくべきだからだとは分かっているのだが、私達にとってはただのおやつだ。皆でそれらを食べながら楽しい噂話をし、採血の邪魔にならない程度に騒ぐ。
とうとう、三時間目終了のチャイムが鳴るまで会議室に粘ってしまった。流石に次の授業まではサボれないので、その場に残っていた生徒全員が仕方なさそうに腰を上げる。
「じゃ、またね〜」
奈津実ちゃんも、私に手を振って元気良く会議室を出ていった。
私達も揃って教室に戻る。皆は、次の授業が氷室先生の数学だからと憂鬱そうだ。一応、私も彼女らに態度を合わせているけれど、内心は嬉しくて仕方がない。
しかし、いつも楽しみな授業が今日は違っていた。
予習も復習も完璧にこなして、肝心の授業もバッチリ……のはずが、何故か少しも頭に入らないのである。氷室先生が丁寧に説明する大事な公式や説明は、私の右耳から左耳へ抜けてしまう。懸命に聞こうとするのだが、全然駄目なのだ。頭が回らない。焦れば焦る度、私の集中力は欠けていく。
それにさっきから吐き気がする。胸の辺りと頭がもやもやと重い。全身で汗を掻いており、それがまた気持ち悪かった。
一体どうしたのだろう?
気分の悪さを自覚した途端、それらの症状がひどくなってきた。とうとう私は耐えられなくなり、机の上に突っ伏す。誰か──氷室先生でもいいから私の変化を察知してくれないかと思ったが、周囲の生徒は単に私が寝ているのだと勘違いしているらしく、誰も声を掛けてこない。また、先生も私に気付いていないようだ。
暫くこうして休んでいれば平気かと思い、私はその状態で耐えた。
だが、吐き気が波のように続けて襲ってくる。今の波は耐えられたが、次もそうであるかは分からない。
とりあえずトイレに行こう!
もし万が一、ここで迷惑を掛けるような事態になってはいけない。自分で動けるうちに、そうなっても平気な場所まで移動しておくべきだ。
私は残っていた力を振り絞って上体を起こした。そして右手を挙げる。
「先生……っ!」
「何だ?」
私の突然の挙手に、氷室先生は眉を寄せている。
「あの、私、気分がとても悪いので……」
言っている途中で、ひどい目眩がした。目の前が真っ暗になるのを感じながら、何とか口を動かそうと頑張った。
・
・
・
・
大好きな氷室先生に呼ばれたような気がして目を開けてみると、真っ白な天井が広がっていた。
「……あれ?」
いつの間にか、私は身体を横たえている。教室の自分の椅子に座っていたはずなのに、何故だろうか。それに、ここはどうやら保健室のようだ。
「気が付いた? 良かった」
「奈津実ちゃん?」
聞こえてきた声の方に首を向けると、奈津実ちゃんが心配そうに私を見ている。私は訳が分からず、辺りを見回した。氷室先生の姿はない。幻聴だったのだろうか。
確かにここは保健室である。苦しかった吐き気は治まっているが、頭や腰が鈍く痛い。
奈津実ちゃんが私の手を握る。私の手は冷えており、彼女の手の温かさが心地良かった。
「あんた、授業中に貧血で倒れたんだって。気分はどう?」
「うん、もう……平気。
でもどうして奈津実ちゃんがここに?」
「あんたが保健室に運ばれたって聞いたから飛んできたんじゃない! 今は昼休みだよ。あんたのクラスの女子もここに顔を出していたんだけど、保健の先生が『付き添いは一人でいい』って注意してきて。でも我が儘言って、私が残らせてもらったんだ」
あの時の私は、おそらく気分が悪いと言ったことで張り詰めていた気が弛んだのだろう。それで倒れてしまったに違いない。この頭と腰の痛みは、その時に打ったせいか。
私は心から御礼を言った。
「奈津実ちゃん、有難う」
「あはは、お礼はいいよ。倒れちゃったのは、さっきの献血のせいだね。ゆっくり休みな」
「うん……」
奈津実ちゃんは立ち上がると、私の為にお水を汲んでくれた。喉が乾いていた私はコップを受け取り、ゴクゴクと飲み干す。
「それにしてもさ」
「ん?」
「私がここに来る前、ヒムロッチが真っ青な顔してここであんたを見ていたんだよ。それこそ、倒れたあんたより顔色が悪かったんだから。それがあんまり意外だったんでつい笑っちゃったら、ヒムロッチがギロッと睨んできてねー。でも、私があんたを見に来たって言ったら、『そうか』って返事をしてそそくさと出ていっちゃった」
「ひ……氷室先生が?」
「うん。聞いた話だけど、倒れたあんたをここに運んだのもヒムロッチなんだって。あいつがここであんたの傍についていたから、その後の授業が無くなったって皆が喜んでいたらしいんだけど。あの厳しいヒムロッチがそこまで生徒を心配するだなんて、何か不思議」
「……」
氷室先生が、大事な授業を放っておいても私を心配してくれたというのか。もしそれが本当だとしたら、こんなに嬉しいことはない。私はこみ上げてくる喜びを必死で押え、真っ赤になった顔を隠す為に再び布団に潜った。
「ん? 大丈夫?
また倒れたらいけないから、完全に良くなるまでここで寝ていていいってさ。
あ、ご飯は食べられたらちゃんと取るべきなんだって。あんた、いつもお弁当だったよね? 私が教室に行って取ってこようか?」
「う……うん、お願いしようかな」
「じゃあ、ちょっと待っててね」
そう言うと、奈津実ちゃんは勢いよく外へ出ていった。
入れ代わりに、私と同じクラスの女の子達が数人入ってくる。保健医は私達の方をじろっと見たが、何も言ってこなかった。
彼女らの説明によると、私はやはり氷室先生に抱っこされてここまで運ばれてきたらしい。
「凄かったのー! ヒムロッチったら、倒れたあんたにダッシュで駆け寄っちゃって」
「そうそう! 教室で何度もあんたの身体を揺さぶりながら、必死で名前を呼んでてねー。ヒムロッチがあんなに熱くなったのって初めて見たよね?」
「うん、びっくりした。お姫様抱っこをした後、『これから私は保健室へ行く。君達はここで自習をしていたまえ』って言い放って、颯爽と廊下へ出ていっちゃってさ。ヒムロッチが王子に見えたよ」
「気が動転するってああいうのを言うんだろうね。流石、ヒムロッチ。取る行動全てが教育に繋がる!」
聞いていて、私は更に恥ずかしくなった。顔がカーッと熱くなる。それと同時に、再び頭がクラクラした。貧血なのに、変に興奮したからかもしれない。
「どうしたの?」
女子の一人が私の顔を覗きこんで口を開く。私は小さく頭を振った。
「ううん……。そういう氷室先生なら、私も見てみたかったなと思って」
「あ、そうか。倒れている当人は見られないんだよね」
「勿体無いー。あのヒムロッチは一見の価値があったのに」
皆とは逆の意味でなんだけどね、と私は心の中でペロッと舌を出す。
あぁ、どうしてそんな大事な場面をこの私自身が見られないのだろう? 皆が面白可笑しく語っているその慌て振りは、私にとっては違う意味がある。先生と生徒という関係上、学校にいる時は悲しくなるぐらい普通で、素っ気無いと感じてしまう態度を取る氷室先生だ。何だか、先生に大事な存在だと思われているようでとても嬉しい。もし皆がいなければ、やったーと叫んで飛び跳ねたい気分である。
「でもさ、ヒムロッチには経過報告を兼ねてお礼を言った方が良いよ」
「勿論」
そんなことは当然である。具合が完全に良くなったら、職員室に行くつもりだ。もう大丈夫です、ご迷惑をお掛けしました──在り来たりな言葉の裏に、皆の前では言えない本音をそこに含めるのだ。後は、次に二人きりになった時に素直な気持ちを告げれば良い。
私は、氷室先生に抱き上げられている図を想像しながら、再びベッドに横になった。そして私だけが知らない、私が倒れた時の状況を勝手に想像して一人楽しむ。皆がびっくりするぐらいの慌てっぷりとは、一体どんなものだろう。
機会があるのなら、是非先生自身に問いただしてみたいものである。 |
了
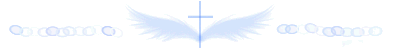
これは実話がベースです。
高校の時、学校で初めて献血したんですけど、
その日だけで二回もぶっ倒れました。
そのうちの一回はSSにあるように授業中……。
すぐ気付いたので、友達に付き添ってもらって自力で保健室に行きました。
その後、当時住んでいた街の駅前で献血をしたのですが
その時も見事に倒れました。
それ以後、世間の迷惑になると思い、やっておりません。
(20020930 UP)
|
|