【愛情過多】
|
最近、守村君の様子が変だ。
普段からもの静かな彼が、ここ十日ほどはとみに寡黙になっている。何かあったのかと私が直接聞いても、彼は「平気です」と言う。ただ、私の問いを否定しないので、答えを貰ったのも同然なのだが。
ずっと気になっていたので、私は女友達の奈津実ちゃんにこのことを相談をした。本当は、守村君の男友達に当たれば一番良いのだが、情けないことに私は彼の交友関係をよく知らないのである。それに本人を差し置いて私が出しゃばるのもどうかと思い、同じ傍観者の立場である彼女に彼のことを聞いてみたのだった。
「守村かぁ。いつもああじゃなかったっけ?」
「全然違うよ。元気が無いというか、落ち込んでいるみたいなの」
「園芸部の花が誰かにむしられたとか?」
「あ、それはあり得るかも。守村君、学校の花壇を凄く大事にしているし!」
早速、その日の放課後に私は高等部の中庭や裏庭を回ってみた。しかし、季節の花が咲いている花壇は見事な手入れ振りだ。中には何もない淋しい花壇もあったけれど、土に差してある札を見る限り、種や球根を植えたばかりかお休み中といったものだった。
「ううん、原因は花壇じゃないのかな」
そう結論を出した私は、そのまま校門へ向かって帰ることにした。
しかしその途中で、私は守村君を見つけた。彼は、いつも持っている分厚い植物図鑑を歩きながら読んでいる。危険な行動なので、私はそういう彼を見る度に注意しているのだが、彼は何故か決して止めようとしない。
「守む……?」
私は守村君の名前呼んだが、途中で声が出なくなった。彼は怪我をしているらしく、頬に大きな絆創膏を貼っている。また、持っている愛用の植物図鑑は泥水に濡れたのか紙が波打っており、所々が染みで汚れていた。
何があったのだろう。
私は再度守村君を呼び、走り寄った。
「守村君!」
「あ、こんにちは。
そんなに急いでどうしたんですか?」
守村君は、いつも通りの優しい笑みを私に向けてくる。私は首を振り、彼の頬にある絆創膏を指した。
「それ、どうしたの?」
「ははは、見つかっちゃいましたね。ちょっと怪我をしてしまったんです」
「……誰かに殴られたのね?」
それしかあり得ない。こんなに温厚な彼を誰が傷付けたのかと、私は一人で憤慨した。
しかし、守村君は慌てたように口を開く。
「いえ、違うんです。これは……あの……」
「殴った人を庇っているのね。その本も、そいつに汚されたんでしょう?」
「え、これですか?」
「守村君がしづらいのなら、私が文句を言ってきてあげる。
何組の誰?」
「あ、あの、本当に違うんです! ごめんなさいっ!」
守村君は腰を折ってぺこりと頭を下げた。私は呆気に取られる。
「……違うの?」
「はい。この頬の怪我は、花の世話をしている最中に僕が転んでしまって、煉瓦で擦った時にできたんです。もしまだ貴方が疑うなら、絆創膏を取りますよ? 傷口が、殴られてできるような怪我とは全然違いますから」
「い、いい」
流石にそれは遠慮する。誰かに殴られていないのなら、それに越したことはない。
だが、私の疑問はまだ晴れていない。
「その本は?」
途端に、守村君は黙り込む。先程の、頬の傷に対する私の言葉を否定した時の勢いはもう無かった。
「やっぱり学校の誰かに嫌がらせでもされているんじゃないの?
守村君?」
「いえ、違います。これは僕と父の諍いでこうなってしまったんです」
「お父さんと?」
守村君が父親との確執を持っているというのは私も知っている。将来のことで、二人の意見が大きく違っているのだ。樹木医になりたいと望む彼を、父親が激しく否定してくるらしい。確かに、父親が植物図鑑を汚したのなら私にも頷ける。
しかし、守村君はそう思った私の頭の中を読んだかのように言う。
「でも、誤解しないで下さい。僕がこれを読みながら歩いているのを父に見つかってしまって、言い合っているうちに、弾みで父の手が僕の手に当たり、本が地面に落ちたんです。そこがたまたま水たまりの上で……」
「そうなんだ。変なことを言ってごめんなさい」
「いえ。貴方を心配させてしまって、こちらこそすみません。
そんな訳で、僕は大丈夫ですから」
「……うん。
もしかして最近の守村君に元気がなかったのも、お父さんとのことがあったからなのかな」
私の言葉に、守村君はハッと顔を上げた。
「──貴方には隠し事ができませんね。
実はそうなんです。僕がいくら真剣に説得しても、父は聞いてくれない上に家で顔を合わせる度に煩く文句を言ってくるものですから、最近は家に帰るのが憂鬱で。最近では、なるべく父を避けるようにしているんです」
「大変なんだね」
そう言っても、私は守村君の苦労を全然理解できていないと思う。かつて一度、彼の家に遊びに行った時にたまたま見た二人の会話は、とても辛いものだった。あれが毎日続いているなんて、私には耐えられそうにない。
それから、私達は一緒に下校した。帰宅するのは気が重いという彼に合わせて、道沿いにあった喫茶店や花屋に立ち寄る。そうしている守村君の表情や雰囲気はいつも通りの柔らかいもので、私は彼に何と言ったら良いかが分からなかった。
翌日。
昼休みに私が中庭をぷらぷら歩いていると、花壇を手入れしている守村君に会った。
「守村君」
「あぁ、こんにちは」
「本当にいつも手をかけているんだね。ご苦労様」
「僕はこの花壇が大好きなんですよ。それに植物を見て回るのは本当に楽しいですから、時間があれば、園芸部以外の花壇や木々もなるべく世話をするようにしています。
ただ……」
ふと守村君は顔を曇らせた。
「どうしたの?」
「以前からこの学校には、僕や園芸部の他に、学校の植物に興味を持ってくれる人がいるようなんです。それはとても嬉しいことなのですが……困ったことに、その方は知識不足なんです」
「知識不足? それって、手入れ方法が間違っているってこと?」
私の問いに守村君が頷いた。
「はい。水や肥料は、ただやれば良いというものではないのです。適切な時期に適切な量をやるのがとても大事なのに、そこを分かって頂けていないようで」
「そういえば、前にもそんなことがあったよね。
ほら、校門の傍の木を見て、守村君が大慌てしていたじゃない」
「はい。あれも肥料のやり過ぎでした。そのまま放っておいたら、根が負けていたでしょう。
人間と違って植物は口をきけませんから、間違った世話を受けても文句が言えないんです」
「ふーん」
私は頷いてはみたが、実は守村君のように植物の微妙な変化など読み取れるはずがない。何せ、何度も家の観葉植物を枯らしているのだ。
私は守村君が繊細なのだと改めて感じていたが、ふと別なことを思い付いた。
「ねぇ、守村君」
「はい?」
「守村君のお父さんもこれと同じじゃない?」
「僕の父が、ですか?」
守村君はきょとんとしている。
構わず、私は言葉を続けた。
「お父さんが守村君の進路に文句を言っているのって、守村君の幸せを願ってのことに違いないもの。守村君自身は放っておいてほしいと思っているのに、お父さんはこれが一番良いんだと信じているから、気持ちが行き違っているんだよね。愛情を注ぐこと自体はとても素晴らしいのに、方法が間違っている点では、植物への肥料や水のやり過ぎと同じだと思う」
「──確かにそうですね」
「でも、植物と守村君とでは大きな違いがあるわ。植物はそれが間違っていると知っていてもじっと耐えるしかないけれど、守村君には意思を伝える口がちゃんと付いている。会えば文句の言い合いになっちゃうお父さんとじっくり話すのは大変かもしれないけれど、やっぱり諦めずに根気よく続けるべきだよ」
守村君はじっと何かを考えていたようだったが、暫く経って首を横に振った。
「でも駄目なんです。僕がいくら言っても聞いてもらえないんですから」
「守村君って一人っ子だったよね?」
「はい、そうですが……」
「ということは、守村君の子供歴と、守村君のお父さんの父親歴は一緒なんだ。私達がまだまだ未熟なように、守村君のお父さんも父親としてまだ完璧じゃないんだよ。
だから、守村君がお父さんを父親として何でも求めちゃ駄目。どこかで私達も妥協しなくちゃ。
真正面からぶつかっていって受け入れてもらえなかったと嘆く暇があったら、僅かでも話を聞いてもらえるような環境をまず整えたらどうかしら。守村君が目指している樹木医って、日本ではまだ珍しいけれど素晴らしい職業なんだし、胸張って主張できることでしょう? まずはお母さんを味方につけるとか、お祖父さんやお祖母さんに話をしてみるとか、周りから攻めることから始めてみれば?」
「──」
「守村君?」
少し生意気な発言だったかなと私は頭を掻いた。他人の家の事情に勝手に踏み込むのは、完全なマナー違反だ。
しかし守村君の顔は、次第に優しい笑顔に変わる。
「そう……ですね。貴方の言う通りです。僕も父も、僕の将来のことになると必要以上に我を張ってしまうので、間に人を介して話すのも良いかもしれません。そうやって、少し頭を冷やすのが僕達には必要なのでしょう」
「うん」
「今まで僕は、父が僕よりも二十年以上も人間として生きているのに僕の気持ちを全く分からないだなんてと、内心怒っていました。でも思い返してみると、それは本当に僕の進路についてだけなんです。喧嘩状態のせいか、父が何でも僕を否定するのだと、ついさっきまで錯角していたようです。
僕も父も、息子と父親という役割ではまだ不完全なんですね。経験が浅くて未熟だから、僕が父を理解できないように父も僕が理解できない。でも、僕がそれだけでも気付けた分、大きな前進だと思うんです。
僕は貴女にお礼を言わなければ。
有難う。お陰で、気分が本当に楽になりました」
守村君は深々と頭を下げてきた。私は慌てる。
「い、いやぁ……。勝手に偉そうなことを言ってごめんね」
だが、私の言葉は守村君に大きく作用したようで、彼は晴れ晴れとした顔で校舎へ戻っていった。私はホッとしながらも、僅かな罪悪感のようなものを胸にチクッと感じていた。
あんなことを言いながらも、私自身はというと、親に対する気持ちのコントロールはまるでできていない。煩く言ってくる親を疎ましく思ったり、私が勝手にひねくれるのもしょっちゅうだ。しかもそんな時の理由は大抵がくだらないもので、守村君のような真剣さは欠片も無いのである。情けないの一言だ。
昼休み終了の鐘が鳴った。私は大きく伸びをすると、先に行った守村君同様に校舎へ戻る。
途中の花壇で、私は綺麗に咲いている小さな花を見つけた。花の名前は分からないが、これも守村君の適量な愛情を受けて育った植物に違いない。
そう、私達には口がある。将来こうした花を咲かせるべく、それぞれの未熟さをせめてもの心遣いでカバーしながら、日々頑張らなくてはならない。 |
了
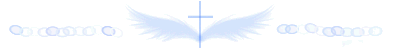
守村君を初めて攻略している時に思い付いた話……
とはいえ、一度しかEDを見ていないので
それ以来ずっと放っておいた訳ですが。
全然書き慣れていないので守村君は凄く難しいです。
今回のはちょっと説教臭かったかなと反省しています。
(20021109 UP)
|
|