【贈り物】
|
三月一日の夜。
私を乗せた氷室先生の車が、とある路地を入った小さな駐車場に止まる。
ドアを開けて外に出た私と先生は、寒さに肩をすくめながら、すぐ近くにある店に向かった。
氷室先生が木製の重いドアを開けてくれる。低めの鈴がカランカランと鳴るなか、私は先に店の中に入った。
「いらっしゃい──やぁ」
カウンターの中にいるマスターさんが、優しい声で私達を出迎えてくれた。
私は頭を下げる。
「こんばんは、マスターさん」
「外は寒いだろう? さぁ、どうぞ」
促されて、私はカウンターに近付く。上に着ていたコートを脱ぎ、畳んで手に持った。
後から来た先生が空いている席に座ったので、私もその隣の椅子に腰を掛ける。丁度マスターさんの目の前だ。
「今日もレモネードを二つで良いのかな?」
「あぁ」
「はい、お願いします」
本当は色々飲んでみたいところだが、氷室先生と一緒にここへ来る限り、当分無理だろう。私は、ここで唯一飲んだことのあるレモネードを今回も頼んだ。
「ところで生徒さんは、いつもにも増してお洒落をしているじゃないか。気取った場所へデート、いや“社会見学”でも行ってきたのかい?」
「今日は高校の卒業式だったんです。続けて三時から謝恩会だったもので」
卒業式は高校の制服で参加したが、謝恩会は服装自由だというので、仲の良い女友達と一緒に赤のカクテルドレスを着たのだ。会の終了後にそのまま氷室先生の車に乗った為、私はドレス姿のままである。
「やっぱり制服の時よりは大人っぽく見えるね」
「あはは、そうですか。こういうのは着慣れていないので、なかなか大変ですけど」
「それじゃ、卒業おめでとうということで、これは俺の奢り」
マスターさんが、私と氷室先生の前にレモネードが注がれたグラスを置く。私は礼を言って早速口を付けた。喉が乾いていたので、いつも以上に美味しく感じる。
氷室先生は何故か無口だ。担任教師として私達三年生を送りだすのは、やはり疲れるのだろうか。ただ、無言状態の先生があまり気にもならなかったので、私はマスターさんの仕事の邪魔にならない程度に彼と話した。
「生徒さんは、零一が三年間ぶっ続けで受け持ったんだっけ?」
「はい。お陰様で随分鍛えられました。
何せ私、第一印象が悪かったんですよ。最初のHRに私の制服のスカーフが曲がっていて、名指しで注意されたんですから。他にも本当に色々あったんですけど、今となってはどれも良い思い出です。もう氷室先生の生徒じゃないんだと思うと、ホッとする以上に淋しかったりします」
「そうか。じゃあ、俺が君を“生徒さん”って呼ぶのは失礼だね。
ええと──もう“彼女さん”は解禁かな」
マスターさんは、片方の眉をくっと上げて笑う。
私は恥ずかしながらも頷いた。
「実はそうなんです」
「俺に言わせれば、今更って感じだけどね。
ま、とりあえずこっちもおめでとう。良かったなぁ、零一」
「煩い」
氷室先生はムスッとしながら大きく息を吐く。それを見たマスターさんが、やれやれという顔をした。
「零一、今日は態度が悪いだろう? でもこれ、ただの緊張の裏返しだから安心してね、彼女さん」
「緊張?」
ここは氷室先生の馴染みの店である。なのに緊張とはどういうことだろう。だが、確かに今日の先生はどことなく変だ。私はそれを疲れだと判断していたが、マスターさんの目には異なってみえるらしい。
マスターさんは、くくくと意味ありげに笑う。
「零一、この前までのアレはそういうことだろう?」
「“アレ”?」
話が見えず、私は首を傾げた。氷室先生は居心地悪そうな表情で黙ったまま、レモネードを飲んでいる。
マスターさんが可笑しそうに口を開いた。
「零一はね、『今のマンションにはピアノを入れられないから』と言って、最近ずっとここでピアノの練習をしていたんだよ。練習とはいえ零一の腕は凄いから、俺としては大歓迎だったんだけど」
「でも、練習なら学校の方が便利なんじゃないですか?」
「そこが難しいところだったらしいよ。
家にピアノは無い。学校で弾いていると、君に見つかる可能性がある。かといってピアノを弾く為だけに実家に戻るのはとても面倒。多少茶化されても、ここで練習するのが最適だという結論に至った訳だ」
「氷室先生の練習なら、私も是非聞きたかったです」
「ははは。単なる普通の練習なら音楽室で心置きなくやっただろうが、今回だけはそうもいかなかったらしいよ。
実は、君が卒業したと聞いて俺もようやく合点したのだが──零一から君に、曲のプレゼントがあるそうだ」
「えええっ?」
私は驚いて横の氷室先生を見た。
しかし氷室先生はそれに答えず、椅子からすっと立ち上がり、店に置いてあるピアノに向かって歩いていった。これまで私は、氷室先生がここでピアノを弾くのを数回目撃している。だがどれもマスターさんの要望に仕方なく応じるという形だったので、氷室先生が自主的にピアノを弾くのを見るのはこれが初めてだ。
氷室先生はピアノの蓋を開けると、ポロポロと適当に弾いて指を馴らしている。
私は固唾を飲んでそれを見守った。
「零一、君の為に凄く練習していたんだ。どうか一音も聞き逃さないでやってね」
「はい」
氷室先生は、どうしてプロにならなかったのかと思うほどの腕前だ。そんな人からピアノ演奏のプレゼントなんて嬉し過ぎる。
ふと、氷室先生が私を見た。私が軽く手を振って応じると、先生は僅かに表情を柔らかくしてピアノに向かった。
一呼吸分の間があり、先生の演奏が始まる。
少しけだるい感じの前奏の後、明るいハ長調の軽快なワルツが店内に流れた。テレビなどで聴いたことがあるが、曲名や作曲者名は分からない。演奏後に氷室先生から質問されるだろうから、今のうちに答えを考えておかなければいけないのだが、曲そのものを楽しめなくなるので止めにした。耳から入る美麗なメロディと共に、ピアノを弾く氷室先生の姿もしっかり目に焼きつけておく。
転調の後、主題が数度繰り返されて、約五分の演奏が終わった。途端に、店内中の客が拍手と歓声で湧く。勿論、私も手が痛くなるぐらい叩いた。
氷室先生は片手を上げて聴衆に軽く答えると、何も無かったかのように平然と私の横の椅子に戻ってきた。私は興奮しながら話し掛ける。
「感動しました! 氷室先生の演奏はいつも凄いと思うのですが、何だか今日は普段以上に心に響いてきました」
「……それは何よりだ」
照れているのか、氷室先生は私の方を見ようとしない。それでも、私は思い付く限りの賛辞を氷室先生に浴びせ続けた。
それが一段落して私が残りのレモネードを啜っていると、マスターさんが話しかけてきた。
「ところで彼女さんは、さっきの曲のタイトルを知っているかい?」
「え?」
やばい、と私は焦りだした。氷室先生が何も言わないのですっかり安心していたのだ。まさかマスターさんからこの質問を振られるとは思ってもみなかったので、油断していた私は慌てる羽目になった。
「ええと──あの、どこかで聴いたことのある曲なんですが……その……」
私はしどろもどろになりながら、横の氷室先生をちらっと盗み見た。
先生と視線が合う。
心なしか、先生は答えられない私にがっくりしているようだった。
「う……す、すみません……」
どう頑張っても誤魔化せそうにないので、私は素直に謝った。これでも、氷室先生の影響でクラシックをかなり聴くようになったのだが、まだまだ会話に生かせるまでになっていない。
落ち込む私に、マスターさんが一枚のMDを出してきた。
「どうぞ。さっきの演奏を録音したものだよ」
「わぁ! 有難うございます」
勉強し直してからもう一度聴きたいと思っていたので、これは嬉しいプレゼントだ。
しかしマスターさんは、私の横にいる氷室先生にペンとMD用のシールを差し出している。
「MDを鞄にしまうのはちょっと待っていてね。今、零一に曲名を書かせるから」
「は、はい」
書いてもらえるのか、と私は内心で喜んだ。これで調べる手間が省ける。私でも聴いたことがあるのだから世間的にメジャーな曲なのだろうけれど、何も手掛かりが無い状態から一つ一つ当たっていくのは本当に手間が掛かるのだ。
氷室先生はコホンと咳払いをすると、ペンのキャップを外してさらさらと文字を書いた。
そしてシールを私に渡してくれる。そこには“Je Te Veux/E.Satie”とあった。
「──あぁ、サティ! 名前はよく聞きますけど……これがそうだったんですか。
曲名はジェテ……? 英語じゃないですよね。フランス語ですか?」
残念ながら、私はフランス語に明るくない。私は後で、瑞希さんにでも意味を聞いてみようと決めた。
私が台紙から剥がしたシールをMDに貼っていると、マスターさんが氷室先生を小突いた。
「零一も大変だな。まぁ、フランス語じゃ仕方がないか」
氷室先生はマスターさんの言葉を打ち消すように、わざとらしく再び咳払いをする。
「彼女さん。零一の為にも、その曲名の意味は早く調べてあげてね」
「はぁ……」
結局、その後も詳細が分からないまま、私は氷室先生の車で帰宅した。
家にはフランス語の辞書が無いし、瑞希さんに電話をするには時間があまりにも遅かったので、曲名の意味調べは翌日に持ち越すことにした。
私は部屋のラジカセに貰ったMDをセットして、何度も何度も繰り返し聞いた。目を閉じれば、その時の氷室先生の姿が瞼に浮かぶ。うっとりとしながら、私は幸せの余韻に浸っていた。
その後。
翌朝、近所の本屋でフランス語の会話集を立ち読みした私は、その曲名の和訳にびっくりしてしまった。恥ずかしさでたちまち顔が紅潮する。そして、昨晩のあの場でそれをすぐに理解できなかったことを激しく悔やんだ。まさかこんな題とは……考えもしなかったのだ。
昨晩数十回も聴いたお陰ですっかり覚えたメロディを鼻唄で奏でながら、私は本屋を出た。ポケットから携帯電話を取り出し、先生に連絡を入れる。
「あ、氷室先生! 私です。昨日は色々と有難うございました。
それで、あの……早速、昨日の曲の意味を調べてみたのですが──」
もしかしたら電話の向こう側の先生も、私と同じように照れているかもしれない。私は自然ににやけてくる顔を必死で自制しながら、その感想を心を込めて丁寧に伝えた。 |
了
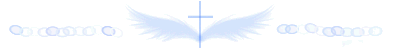
これは氷室先生で最初に思い付いた話です。
書こう書こうと思っていて今まで延び延びになっていました。
ベタなネタですね(笑)。
曲のタイトルは「ジュ トゥ ヴー」。
小説や漫画でよく取り上げられるものなので、
ご存知の方も多いと思いますが、意味は……勿論あの言葉です。
初めてこの曲の存在を知ったという方は是非調べてみて下さい。
どうしても分からないーという方はメールで問い合わせを。
サティはジムノペディ第一番の方が私は好きだったりします。
(こちらも超有名な曲です)
(20021109 UP)
|
|