【眠りの国の王子】
|
木々がすっかり落葉し、冬が間近に迫ったとある日の午後のこと、私は駅向こうにある公園入口に向かって歩いていた。
今日は、奈津実ちゃんと買い物の約束をしているのだ。彼女は流行りに煩いので、出掛ける前にネットで花椿せんせいのコラムを読んで支度をする。黒が彼のお勧め色だというので、それをメインに用意してみた。綿ブラウスに赤のリボンタイを付け、上から薄いカーディガンを羽織る。ボトムは膝丈のバルーンスカートだ。着替え終わった後、時間に遅れないようにちゃんと早めに家を出た。
家から十分ほど歩くと、児童公園の前にさしかかった。ここは学校帰りによく寄る場所だ。こうした休日にも、ごくたまに知り合いがいたりするので、私はちょっと寄り道をして公園内を伺った。嬌声を上げて遊ぶ子供達、ベンチに座って読書に勤しむ若い男性、ペットボトルのお茶を飲んで休憩している女性……と視線を移動させていくと、見たことのある服を着た人間が、一つの大きな木製ベンチを占領して横になっている。私の記憶によると、その人間とはあの葉月珪だ。まさか?と思いつつ、私は小走りでそのベンチに近付く。
ベンチにいたのは、やはり葉月君だった。荷物らしいバッグを枕にし、仰向けの状態でぐうぐうとよく寝ている。陽射しが直接当たって眩しいのか、左腕は折り曲げられて目の上に置かれていた。
「おおい」
私は、小さな声で呼び掛けた。しかし、葉月君は安らかな寝息を立てるだけで、私の声にぴくりとも反応しない。私は黙り、静かに彼の寝顔を見つめた。
私がこうして葉月君の寝顔を見るのは、これでもう何度目だろうか。私と葉月君は違うクラスだが、休み時間に別件でその教室に遊びに行くと、眠っている彼の姿を見ることがある。二人で森林公園へ出掛けた時には、着いた早々に葉月君が「昼寝したい」と言って私を驚かせた。いつだったか、今日のような休日に葉月君がこの公園で寝ていたのも見ている。どうやら葉月珪という人は己の睡魔に忠実らしく、眠くなったらいつでもどこでも……というのが信条のようだ。
葉月君は、そう簡単には起きそうにない。私は眠っている彼にバイバイと手を振ると、奈津実ちゃんとの約束の場所へ向かう為に、公園を離れた。
奈津実ちゃんとの買い物はスムーズに進んだ。数日前に一緒に見たファッション雑誌で、買う物をある程度決めていたからである。奈津実ちゃんはチェックのプリーツスカートと靴を、私はレースが付いた白いブラウスを購入した。
休日なので、どこの店も混雑していた。目的の物を買い終えた私達は、カフェの空席を見つけてお茶がてら休憩する。
奈津実ちゃんが、ホットココアを飲みながら言った。
「やっぱり日曜日は混むねー」
「うん。でも、目を付けていた物がお店にまだ残っていて良かったよね。奈津実ちゃんが買ったスカート、あれで最後だったじゃない」
「そうなのー。もしここで買えなかったら、隣の市のデパートまで足を伸ばす羽目になったよ。
ねぇ、ここを出てもすぐに帰らないよね?」
「うん、時間があるから付き合うよ」
「まだもうちょっと洋服を見たいんだ」
奈津実ちゃんはさっさとココアを飲み終えると、口紅を直して立ち上がってしまった。私も急いで、飲んでいた紅茶を口に入れる。
そして再び、沢山の客で賑わう各店内をぶらついた。
先程は素通りした店で、私は気になる物を見つけた。オフホワイトの別珍で作られた秋冬用のジャケットである。ウエスト部分の両脇に取り外しのきく細い帯状の布が付いており、それを後ろでリボン結びにして飾りとできる仕様だ。しかも襟がさりげなくハート型になっていた。洒落ていて可愛らしいデザインだが、付いている値段もそれなりにする。高校生の私が、気軽に買えるものではない。
私は、ハンガーに掛けられたそのジャケットを手に取って見つめた。見れば見るほど欲しくなってくる。意見を聞こうと、すぐ傍にいるはずの奈津実ちゃんに声を掛けた。しかし彼女は、自分の買い物の為に遠くの棚へ行ってしまっている。ここから名前を呼んでも、人混みで奈津実ちゃんには届きそうにもない。
私が値札とジャケットを交互に見て一人おろおろとしていると、前から店員がやって来た。
「羽織ってみますか?」
「う……」
実際に着てしまったら終わりのような気がする。欲しい気持ちが具体的になって、購入確定になるのは間違いない。買ってしまったら今月の小遣いは残らないのだと、頭の中で何度も自分を諌めるが、店員の笑みが私の欲求を後押しする。
「じゃあ、ちょっとだけ」
気が付いたら店員に鏡の前に連れていかれて、私はそのジャケットを着ていた。ハンガーに掛けられていた時には気付かなかったが、リボンがなくとも腰の部分が絞られているデザインなので、錯角でウエストが細く見える。これでまた、欲しい気持ちが一段アップした。
「あ! それ、いいじゃん! 買うの?」
声が聞こえたので私が振り向くと、奈津実ちゃんが傍に来ていた。
「欲しいんだけど、ちょっと高くて……」
「何? 持ち合わせが足りないとか? 貸してあげるよ」
「ううん。それは平気なんだけど」
私はジャケットを着たまま、鏡の前で横や後ろを向く。やはり欲しい。これを着て、この秋冬は街を歩きたい。
前ボタンに手を掛け、ううんと何度も唸った後、私は店員に言った。
「……これ、ください」
遂に決めてしまったと、私はつい溜め息を吐いた。それぐらい、今の私にとっては大きな買い物だったのだ。私は店員と共にレジへ移動した。代金を支払い、包装されたジャケット入りの紙袋を受け取る。これからのことを考えると気が重かったが、私は不思議な充実感に包まれていた。私の横では、奈津実ちゃんも会計を済ませている。新しく、ハイソックスを買ったらしい。
帰りの道すがら、奈津実ちゃんが言った。
「そのジャケット、高かったけど買って絶対正解だよ。良かったね」
「うん」
後で味わうであろう苦しみは置いておいて、とりあえず私は幸せだった。早く家に帰って、もう一度着ようと強く思う。
その後、私と奈津実ちゃんは駅付近で別れた。まだ五時過ぎだが、もう既に日が暮れている。奈津実ちゃんと喋ってきた時は楽しくて何も感じなかったのに、急に寒さを覚えた。おまけに風が強い。しかも、季節の割に日中が暖かかったのでつい油断してしまい、上には薄いカーディガンしか着ていないのだ。がちがちと歯を打ち鳴らしながら、私は家路を急ぐ。
行きと同じ道を通るので、私は再び児童公園を通り掛かった。一旦、そのまま素通りして立ち去ったが、ふと嫌な予感がしたので慌てて引き返す。何となくであるが、葉月君があのベンチでまだ寝ているような気がしたのだ。
暗くなった公園内は、ぽつりぽつりと灯る電灯の光でぼんやりと明るかった。昼間ののどかな雰囲気は去っており、妙に淋しく感じられる。私は、目的の場所まで急いだ。
葉月君はいた。しかも、まだ眠っている。ベンチが丁度街灯の下にあるので、彼の寝姿はほのかな明かりに照らされていた。私が昼間に見かけた時から、ずっと寝っぱなしなのだろうか。
私はどうしようかと悩んだ。眠りを邪魔したら、余計なお節介だと文句を言われるかもしれない。しかし日没を過ぎて寒くなっているので、葉月君に風邪を引かせない為にも、ここは起こした方が良いと決めた。
「葉月君!」
名前を呼びながら、私は彼の身体を揺すった。しかし、「うーん」と小さな声で唸っただけで、全く目を覚まさない。
「起きてよ、葉月君! 風邪引いちゃうよ!」
何度も何度も、呼び掛けと揺さぶりを繰り返す。それでも、葉月君は起きてくれない。
困った事態に私は頭を悩ませた。寒いのでいい加減に帰りたいが、葉月君をこのまま放ってはおけない。こうなったら、彼が自分から目覚めるまで持久戦である。
私は改めて葉月君を見た。ざっくりとした手編み風のニットに、綿パンツを履いている。時間が経つにつれ空気がどんどん冷えているので、彼は眠りながら間違いなく寒さを感じているはずだ。幾ら何でもと、私は着ていたカーディガンに手を掛けた。寝ている彼の身体に掛けてあげようと思ったのだ。
しかし考え直す。このカーディガンは春秋用の薄いものだ。脱いだら私も寒いが、葉月君に暖を与えてあげられるだろうか。
少し考えて、私は一度大きく頷いた。そして持っていた紙袋を開け、買ったばかりのジャケットを取り出す。別珍製のこれなら、風も通さず相当暖かいはずだ。私は包装を破り、ジャケットを葉月君の身体の上にそっと掛けた。
「これで良し、と」
葉月君はずっと眠り続けている。
ふと、私は古典バレエを思い出した。悪の妖精カラボスに呪いを掛けられたオーロラ姫は、百年の眠りの後、姫を心から愛する王子のキスで目を覚ます。王子と姫の立場が逆であるし、私が葉月君と舞台に上がるにはあまりにも役不足だが、自分のキスで葉月君は目覚めるかしらと、ついつい試したくなる。それぐらいに、葉月君は静かに眠っていた。
暫くの間、私は葉月君の横で彼が起きるのを待った。しかし容赦なく寒くなってくるし、お腹も減っている。ついでに、トイレにも行っておきたい。
私は葉月君の顔を覗き込み、彼がまだ当分目覚めそうにないのをよく確認すると、家に向かって全速力で走った。一旦帰宅し、準備を整えてからまたここへ来るのだ。
自宅へ戻ると、母親が既に夕食の支度を終えていた。だが、私に食事を取る時間はない。友達が外で待っているからと告げ、私は急いで支度をする。携帯カイロと、台所に置いてあったパンとお菓子を鞄に入れた。葉月君用に厚い膝掛けを持ち、自分の防寒対策でコートを着る。トイレも済ませて、私は家を走り出た。
可能な限り急いだのだが、私が家を往復して公園へ戻った時には、三十分以上の時間が過ぎていた。公園に入ってからも、速度を緩めずにひたすら走る。
しかし、目当てのベンチは無人だった。
「あれ?」
場所を間違えたかと、私は辺りを見回した。だが、そんなはずはない。確かにここだったのだ。
ベンチには、葉月君当人は勿論、彼の荷物も私のジャケットもなかった。私はベンチに触れてみる。ひんやりと、冷たい木の感触がした。
念の為、私は周囲のベンチを回ってみたけれど、葉月君はどこにもいなかった。
散々歩き回って葉月君がいないのを確信すると、彼がいたはずのベンチに再び戻って腰を下ろす。持ってきた荷物を脇に置き、私は状況を整理することにした。
きっと、私がいなくなった間に葉月君は一人で起きたのだろう。そして家に帰ったに違いない。最悪、私が親切心で掛けたあのジャケットは、一体誰のか分からない気味悪いものとして処分された可能性もある。
私は、葉月君の携帯電話に連絡を入れてみることにした。だが、電源が切られている旨の音声が聞こえてくる。私は勢いよく通話を切った。
「え……?」
葉月君がいない。連絡も取れない。
私は、彼の行方もジャケットのことも心配だった。いっそのこと、このまま彼の家へ行ってみようかと思ったが、今まで行ったことがないので場所が分からない。噂好きな奈津実ちゃんに尋ねれば、住所ぐらいすぐに分かるだろうけれど、彼女に変に勘ぐられたくなかったし、突然の来訪が葉月君の迷惑なのもあり得る話だ。
仕方ないと諦めて、私はベンチから立った。明日になったら、学校で直接葉月君に詳細を尋ねることにする。荷物を持ち、先程帰ったばかりの道をまた歩いた。
さっきはあんなに走れたのに、私の足はひどく重かった。時折蹌踉けながら、一歩一歩ゆっくりと家へ向かう。
だが、翌日に学校で葉月君に尋ねる予定は叶わなかった。寒いのに薄着で我慢していたせいで、私は重い風邪を引いてしまったからだ。あれから帰宅した後、私は身体にだるさを感じて夕食も取らずに寝てしまった。それっきり、ベッドから起きられなくなったのである。
一日、二日、そして三日目の夕方になった。充分に休んだせいで食欲もかなり戻り、高かった熱も普通に下がっている。
身体が楽になっているのにただ寝ているのはつまらなく、私はパジャマから部屋着に着替えてだらだらとテレビを見ていた。昼休みの時間に、私を心配したらしい奈津実ちゃんからの電話が携帯に入ったが、忙しい彼女をずっと電話で引き止めておく訳にはいかず、私の暇つぶしにはならなかった。相手をしてくれるはずの専業主婦の母親は、ずっと買い物に出掛けている。私は家に一人きりだった。
突然、玄関のチャイムが鳴った。
私はインターフォンで応対する。
「はい」
『……葉月と申しますが──』
「葉月君っ?」
スピーカーからの聞き慣れた低い声に、私は飛び上がって驚いた。そのまま玄関まで走り、鍵を外してドアを開ける。
そこには、確かに葉月君がいた。学校帰りで直接ここに来たのか、制服のままである。
「お前、具合はもういいのか?」
「あ、うん。熱も下がったし、もう大丈夫みたい。学校は明日から行くけど──一体どうしたの?」
「これ……」
葉月君は、持っていた大きな紙袋を出した。私はそれを受け取り、中を見る。入っていたのは、あの別珍ジャケットだった。
「えぇっ?」
驚いた私は、紙袋の中と葉月君の顔を交互に見つめる。葉月君はこれを返す為にわざわざここまで来たのか。それにしても、何故持ち主が私だと分かったのだろうか。
問う前に、葉月君の方が口を開いた。
「あの日、俺は凄く眠くて……ずっと寝てたんだ」
「知ってる。だって私、お昼過ぎにあのベンチで眠っている葉月君を一度見ているもの」
「そうか」
葉月君は苦笑した。
「凄く気持ち良さそうに寝てた」
「あぁ。何度か途中で起きたんだけど、まだ眠かったからそのままでいたんだ。
暫く経って、何となく誰かが俺の傍にいる気配がして俺は目を開けたけど、結局誰もいなかった……。でもそのジャケットを見て、やっぱりそうだったんだと確信したんだ。不思議だけど、それがお前だって俺は思った」
「私、何回も葉月君の名前を呼んだり、身体を揺すったりしたから。深層意識で覚えていたんじゃない?」
「そうかもしれない。
でも、それだけじゃないぜ。お前はよくこういう系の服を着ているから、自然に結びついたのかもしれない。
それで次の日……一昨日のことだけど、学校にジャケットを持っていってお前に尋ねようとしたら、休みだと聞いて驚いた。どうしようかと俺がジャケットを持ったまま廊下で立ち尽くしていたら、えぇと……藤沢?とかいう奴が、どうしてこのジャケットを俺が持っているんだと煩く言ってきたんだ。それで詳しく話を聞いてみたら──」
「うん。私ね、奈津実ちゃんと買い物をした帰りだったの。そのジャケットは、買うのに私が散々悩んだから、彼女の方でも強く覚えていたんだと思う」
続けて、私はあの夜の説明をした。昼間と同じ場所で寝ている葉月君を見つけたこと、寒そうだったので毛布代わりにジャケットを使ったこと、まだ当分起きそうにないと勝手に判断したので家へ帰って準備をした後に公園にまた戻ったこと……。
私が話し終わると、葉月君は目を閉じて軽く頭を下げた。
「すまなかったな。迷惑を掛けるつもりはなかったんだが。風邪だって、俺のせいなんだろう?」
私は慌てて手を出し、葉月君に頭を上げてもらう。こんなことをさせる為に、私はジャケットを貸したのではない。
「私が勝手にそうしたんだよ。葉月君が謝ることじゃないってば。
でも、ジャケットがこうやってちゃんと返ってきて嬉しいな。凄く気に入ってたの。私も、学校へ行ったら葉月君に聞こうと思っていたんだよ。
そういえば、葉月君がいなくなってから携帯に電話したんだけど、電源入れてなかったの?」
「あぁ、ずっと切りっぱなしだった。すまない」
話が一段落して、私はまた紙袋の中を見た。すると今まで気付かなかったのだが、ジャケットの他に何かが入っている。手を伸ばして探ってみると、同じ別珍で作られた服のようだ。私はそれを紙袋から完全に出す。広げてみると、膝上の丈のふんわりとしたスカートだと分かった。
「葉月君、これは?」
「俺、少し前にファッション雑誌の仕事を受けたんだ。その雑誌が押している各ブランドの秋冬新作ものを紹介する巻頭特集記事で、その中にはこのジャケットのブランドも入っていた。
実はその記事で、このジャケットを着た女性モデルの写真が使われているんだ。同じコンセプトで作られたスカートとセットで。でも、ジャケットは販売されたけど、スカートは参考商品のままで終わってしまった。
急いでこのブランドのプレスに聞いてみたら、それがまだ残っているって言うんで、頼んで譲ってもらった。せっかくジャケットに合わせて作られたスカートなんだし、どうせなら一緒に着たらどうかと思ったんだ。
お礼……にならないかもしれないけど、とりあえずこれは俺の気持ち。受け取ってもらえないか?」
話を聞いている間、私はびっくりし過ぎて声が出なかった。慌てて、何度も頷く。
途端に、葉月君はホッとしたような表情を浮かべた。もしかしたら、今まで彼の心のどこかに緊張があったのかもしれない。
「良かった。話には、まだ続きがあるんだ」
「??」
私は無言で首を傾げた。
葉月君が続ける。
「記事に使われたこのジャケットの写真だけど、女性モデルの横には、同じテーマの服を着た俺がいたんだ。勿論メンズで──このブランドはレディースしか販売しないから、これも参考商品だったんだけど。
ついでに、その服も上下一式貰ってきた。今度、お互いにそれを着て、どこかへ出掛けないか?」
「!」
ジャケットが無事に返ってきただけでも本当に嬉しいのに、非売品のセットのスカートが付いてきて、更に葉月君からのお誘いである。しかも狙ったお揃いの服で、だ。私が行なった僅かな親切からすると、とんでもない産物だった。思わず、これは高熱による夢ではないかと疑ったぐらいである。
児童公園のベンチで休んでいた眠りの国の王子は、シンデレラに出てくる王子に変わってジャケット一つで私を探しだし、幸せを運んできてくれた。
惜しむらくは、私のキスで王子が目覚めてくれるかどうか、確かめられなかったことである。
姫は、ただ愛を享受するだけの存在ではない。いつの日か、強い愛で王子を深い眠りから呼び起こしたいと、姫の入口に立った私は強く望んだ。 |
了
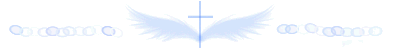
氷室先生と葉月君のイベント(「眠くなったらどうするんだ?」「寝ます」)が
大好きなのですよー(笑)。王子の天然っぷりが最高です。
ジャケットは、実際に私が持っているJaneMarpleの別珍のを元にしました。
(20020724 UP)
|
|