【喧嘩】
|
秋のとある日曜日の朝。
これから、私は姫条君とデートだ。平日に学校へ行く時はいつも時間ぎりぎりだというのに、こういう特別な日だけは張り切って早めに起床する。風呂に入って身体を磨き、お出かけ用の服に着替えて髪型も整え、朝食もしっかり取って私は家を出た。
今日の行き先は、はばたき市郊外の森林公園だ。
数日前、私が姫条君の間でどこかに遊びに行こうと案が出た。しかし情けないことに、二人してお金に余裕が無い。どこか近場でお金を掛けずに遊べる場所はないかとあれこれ考えた末、見事にここが選ばれたのである。尤も私は森林公園の雰囲気が大好きだったので、この結果は大満足だった。母に頼んでお昼用の沢山のサンドイッチを作ってもらったので、今日はそれを二人で食べるつもりだ。
私は、姫条君の顔を早く見たいと心を踊らせながら、待ち合わせ場所である公園入口へ急いだ。左手にした腕時計を見ると、時間には充分余裕があるが、足より気持ちが先走ってしまう。
大通りを曲がる。公園入口はすぐ目の前だ。私は素早く視線を左右に動かし──立っている姫条君を見つけた。
「姫条君!」
私は彼の名前を呼んで走り寄った。
姫条君も私に気付いたようで、顔を上げてにっこりと笑う。
「おはようさん。
何や、今日はめっちゃ早いやん。待ち合わせ時間の十分前やで」
「そう言う姫条君は、私よりも先に来ているじゃない。随分早いねぇ」
「ははは、そうやったな。いやぁ、自分とデートやて思ったら眠られへんかって、実はゆうべからずっとここにおってん」
「あ、そう」
私は姫条君の冗談に呆れながら笑った。しかし姫条君は、そんな私を不満そうに見る。
「あかんあかんーっ! ボケたらしっかりつっこんでくれんと! 会話は言葉のキャッチボールやで」
「そ、そうなの?」
私は戸惑った。
実は、姫条君からこう注意を受けるのはこれが初めてではない。他の誰かが聞いているわけでもないのに、どうして会話に笑いを入れないといけないのだろうと、私は姫条君から言われる度に思ってしまう。ノリの良い人はサービス精神が旺盛なのか。それとも、もう既に染み付いてしまって、意識しなくとも自然にこうなってしまうのか。
「ところで……今日の自分の服、可愛いし、よう似合ってるけど、確か前回もそれやったやんなー」
「えっ?」
私はびっくりしながら己の服を見た。以前に短期のアルバイトを頑張ってようやく買えた別珍のワンピースとボレロだ。前回、姫条君と遊んだ時はパーカーにプリーツスカートとラフな格好をした覚えがあるので、わざわざこれを選んできたのだが……。
しかし、はてと首を傾げているうちに、私は一つの恐ろしい結論に辿り着いた。
記憶通り、先日の私はパーカーとプリーツスカートを着て外出をした。しかしその相手は姫条君でなく、他の男子だったのである。よくよく思い返してみると、今日着ているワンピースとボレロを買ってすぐの週末に、これを着て姫条君とデートをしたのだった。しかも彼と遊びに行くのは、それ以来である。
やばい、と私は焦りだした。何と言い返そうかと必死で頭をめぐらせる。
すると姫条君が演技がかった風に大きな溜め息を吐いた。
「隠さんかってもええって。自分、俺の前ではそれまだ着てへんかったって、勘違いしてたんやんな?」
「……」
私は肯定も否定もできずに、ただ口を閉ざしていた。
姫条君の言葉は更に続く。
「あんましこういう事言いたくないねんけど……実は俺、自分が先週の日曜に、他の男とデートしてんのを見てん。まぁ、俺があれこれ言うべきやないし、黙っとこうと思っててんけど、前回と同じ服着て平気で笑ってる自分見てたら、何かカチンってきてな」
口調は優しいけれど、姫条君の顔は少し引き攣っている。
私はしまったなと思っていた。まさか他の男子と一緒にいるところを姫条君に見られていたとは。ちなみにそれは、デートなどといった甘ったるいものじゃない。今度とある授業でグループ発表をするのだが、それに使うものを買い出しに行っただけなのである。ただ、ノリが良くて話が上手い男子だったので、私は始終笑いっぱなしだった。端から見たら、普通のデートに思えたかもしれない。
私は誤解を解こうとした。しかし寸前で、はたと考える。
どうして私ばかりが悪びれなければいけないのだろう?
正直に言うと、私と姫条君はまだ恋人同士ではない。何かきっかけさえあればどうにかなると思うのだが、その一歩を前に出す勇気が出なくて、私は彼と友達以上の関係をだらだらと続けている。
姫条君は、他の女子生徒とも楽しく遊ぶ。いずれも”彼女”でないらしいが、彼を本気で好きな女子は結構多い。姫条君のそのプレイボーイっぷりは、度々私の胸を痛めてきた。そう、姫条君は私を責められないのだ。
私はかぶりを振って口を開いた。
「そう言う姫条君だって、他の女の子とデートしているそうじゃない。私が直接見たんじゃないけど、クラスや同じ部の友達から色々聞いているもの。この前は、奈津実ちゃんとゲームセンターで遊んでいたんだってね? 凄く仲良さそうだったって、皆の噂だよ」
「あ、あれは無理矢理……」
「前なんか、私がお昼を一緒に食べようと誘っても『忙しいから』って断ったくせに、××ちゃんと中庭で食べていたそうじゃない。まぁ、姫条君と××ちゃんは同じクラスってことで仲が良いんだろうけど」
「う──それは……」
「姫条君に、私をどうこう言う資格は無いんじゃない?」
「おいおい、自分それは言い過ぎやで」
流石に姫条君もムッとしたようだ。あからさまに不愉快そうな顔をしている。
しかし私は口を止めなかった。
「姫条君が誰とどうしようと、私には全然関係無い。今日も、本当は他の誰かと遊びたかったんじゃない? 私がいなくとも姫条君には、電話をすれば誘いにすぐ乗ってくる女の子が沢山いるもんね?」
私は姫条君の顔をじっと見た。
姫条君も私を見ている。
通常ならば、互いの顔を見つめあうなど甘い雰囲気が漂いそうなものだけれど、私達にあるのは殺伐とした空気だ。
暫くそうしていたが、姫条君がふっと目線をそらした。そして、やれやれといった風に重く息を吐く。
「最悪やな。このまま一緒に遊ぶなんて、とても出来そうにないわ。悪いけどー……って今日はお互い様やけど、俺帰るわ」
姫条君は、まだ言い足りなさそうな顔をして足早に去っていく。
私はすぐにしまったと後悔したがもう遅い。姫条君の姿は既に見えなくなっているし、一度口に出してしまった言葉は二度と取り返せない。
私は公園入口に一人ぽつんと取り残された。周囲は、カップルらしい男女がぽつぽつと公園の中に入っていく。私は手で持っていた鞄を見ながら呟いた。
「さ、サンドイッチ、どうしよう」
姫条君がよく食べるので、今日も多めに持ってきている。私一人ではとても片付けられそうにない。
これからどうしようかと私は途方に暮れた。今日はデートなのだと家族に言って出た手前、すぐに帰宅するだなんてできない。親だけならともかく、もし尽に知られたら何を言われるか分からないからだ。
私は重い足取りで、森林公園の中へゆっくりと歩いていった。
公園の芝生に、私は一人で腰を下ろしている。
周囲は家族連れやカップルばかりだ。天気が良いのが、何だか憎らしくなってくる。
することもないので、私は背を倒して芝生の上に寝転がった。一面に広がる青い空と白い雲が目にしみる。いっそのこと、このまま眠れたら時間が潰れるし、楽なのだが、昨晩はいつもよりも早めに寝たせいで、生憎ちっともそんな気になれない。
「あーあ」
私は腹の底から息を吐いた。
今日は、姫条君が言ったように最悪な日である。言わなくていいこと、言ってはいけないことばかり、私は口に出してしまった。具合の悪いことを指摘されて逆に当り散らしたとは、今の冷静な頭で考えると凄く恥ずかしい。まるで馬鹿みたいだ。
同じ服を続けて着てしまい、しかも自分でそれに気付かなかったとは、なんて情けない話だろう。花椿せんせいがWebコラムでそれに気を付けるよう何度も仰っているのをいつも読んでいたのに、私は本当に迂闊だった。せめて姫条君から言われる前に気付いて恥じていたら、こんなにこじれなかったに違いない。最初に言われた時、私がちゃんと素直になれたら、姫条君も怒らなかったはずだ。
でも、私が姫条君にぶつけた言葉は、日頃からずっと心に溜めていたものである。姫条君に人気がある分、常に私は言い様のない不安に晒されているのだ。学校で、女子生徒が彼を褒めていればドキドキするし、彼が女子生徒と一緒にいたと聞いただけで全身が緊張する。姫条君は、私に対してとても優しい。でもそれは決して私にだけでないのをよく知っているから、とても辛いのだ。
こう考えていると、私は暗い気持ちになってきた。せっかくの休みなのに、これでは本当に台なしである。
私は寝たまま大きく伸びをし、気分転換をした後、よっと声を出して上体を戻した。そして腰を上げ、完全に立ち上がる。服に付いた細かい芝生を両手で払うと、私は園内の散歩を始めた。
姫条君と言い合ったのは事実だ。明日、学校で謝るにしても、それはもう消せない。私は彼のことを思うだけで気分が沈んでしまう。しかしせめて今日はもう忘れてしまおうと決め、頭の中から彼を追い出すことにした。好きな曲を鼻唄で奏でながら、ゆっくりと園内を回る。
それから約一時間後。
普段から運動不足な私の足は、すっかりくたくたに疲れていた。沢山のベンチがある大きな広場に着いたのを機に休もうと決め、私は傍にあった水道でまず手を洗い、空いているベンチに向かった。
「ふう」
一人で散歩するというのも、やり慣れていないとなかなか酷だった。話し相手もいないし、ラジオなどもないから、気が紛れない。意識が己の中に集中してしまうので、私はついつい姫条君のことを考えてしまったのだ。
心も身体もくたくただったので、私はベンチに座ると全身の力が一気に抜けた。鞄からペットボトルのお茶を出し、ごくごくと飲む。いくら秋で空気が冷たいとしても、長時間歩けば嫌でも身体は温まる。全身に汗をうっすら掻いていたので、お茶はとても美味しく感じられた。
さて、と私は再度鞄に手を入れた。そしてサンドイッチの包みを取り出す。私にしたら、ゆうに三食分はあるか。幾つかに小分けをしてきたので、とりあえず一人前を出し、残りを鞄にしまった。流石に全部食べ切れないが、こうしてちょこちょこ口にしていたら量も減るはずだろう。残ったら、家に持ち帰ればいい。
「いだだきます」
そう唱えて、私は野菜サンドを一つ持った。
しかしいつもは静かな公園なのに、何だか今日は変に騒がしい。しかも、騒ぎ声は私の背後から聞こえてくる。一体何事かと振り返ってみたが、ベンチの裏は黄色に染まる銀杏の木々があるだけだ。その奥にも道が続いているはずなので、そこで誰かが騒いでいるのだろうか。
「?」
私は首を傾げながら、再びサンドイッチを食べ始めた。しかし少し経つと、再び煩い声が聞こえてくる。私は口をもぐもぐと動かしながら、そっと耳を傾けた。
『あれ? カンサイの兄ちゃんだ!』
『こんなところで何やってるのー?』
『しーっ、静かにしろや』
あれ……?と、聞き覚えのある声と関西弁に私は眉を寄せた。確認の為、もう暫く大人しく聞いてみる。
『もしかしてかくれんぼ?』
『あ、僕も混ざりたい! 兄ちゃん、一緒に遊ぼうよ』
『鬼はどこ?』
『なぁ、兄ちゃぁんっ』
『だから静かにしろって言うてるやろ?』
やっぱりそうだ。
思い切って振り返った私は唖然とした。目の前の木陰に数人の子供達がおり、あの姫条君が身体を折って隠れているではないか。
「姫条君?」
私が名を呼ぶと、姫条君は顔を思いっきり歪ませながら子供達の頭をポンと軽く叩いた。
「あああああっ!
ほら、お前らが煩いから見つかってしもうたやろ?」
姫条君はばつが悪そうに立ち、右手を上げた。
「よ、よう」
どんな顔をしたら良いかが分からない。私は気まずさを感じながら、目線を姫条君の顔より下げて挨拶をした。
「うん……。
あの、姫条君はあれからまっすぐ家に帰ったんじゃなかったの?」
「そのつもりやってんけど、途中で気が変わってな」
「もしかして、ずっとそうやって私の後をつけていたとか?」
「──まぁな。ほら、俺の代わりに他の奴が呼ばれてもしゃくやし。とりあえず陰で見張っとこうかって思ってな」
「……」
私は、私に見つからないようにそっと後をつける姫条君の姿を想像した。芝生で寝ていた時はともかく、私は公園内を一時間近く散策したが、彼も同じように歩いたのだろうか。
私は暫し呆れたが、次第に可笑しくなってきた。あははははと声に出して笑っていると、急に目の前の姫条君がおろおろし始めた。
「ど、どうした? 俺、何か変な事言うたか?」
「『見張る』って……あはは、姫条君に振られて淋しくなった私が、代わりに他の誰かを呼ぶと思った? うーん、女友達への連絡ならあり得るかもしれないけど、あんな言い合いをしておいて、他の男の子なんかに声を掛けないよ。これでも、私は身持ちが固いんだから。
言っておくけどね、姫条君が見たって言う先週の私だって、デートなんかじゃないんだよ。相手は確かに同じクラスの男子でも、授業で使うものの買い出しに出かけただけなんだから」
私は、にやっと口角を上げた。姫条君が信じられないという感じで私を見る。
「ほんまか?」
「うん。今日、前回と同じ服を着てきちゃったのは私が本当に悪かった。ごめんなさい、謝ります。
でも、先週の外出を変なことに結び付けるのは、姫条君の完全な勘違いだよ。安心して」
私がそう言うと、表情が固かった姫条君の顔が徐々に柔らかくなっていった。
「う……そんなら、俺かって言い分はあるで。
奈津美ちゃんとゲーセン行ったのは、無理矢理連れてかれてやで。あいつ、俺が宿題で困ってたとこにつけこんで、俺に奢れって煩かったんや。
××ちゃんとお昼食べたっていうんは、正しいけど一部間違ってるで。あれは皆で弁当持ち寄って食べたんや。ほら、中庭は日当たりいいし激戦区やんか? 場所取りで俺と××ちゃんが先にいたから、それ見て誰かが勘違いしたんとちゃうか?」
「それ、本当?」
今度は私が眉を寄せる番だった。
「あぁ、ホンマホンマ。自分、俺を信じてくれ」
正直なところ、私は姫条君の言葉をすぐには信じられそうになかった。しかし、彼のいつにない真剣な顔を見ているうち、不思議なことに段々その気になってきた。
姫条君はかぶりを振る。
「俺の説明が足りひんかって、変に不安にさせてごめんな。
でも、自分の事も誤解で良かったわー。俺、ほんまにホッとした」
「う……うん。私も本当にごめんなさい。明日、学校で会ったらちゃんと謝ろうと思ったんだけど、今日のうちにそれができて良かった。姫条君が私の後をずっとつけていたっていうのには、びっくりしたけどね」
私と姫条君は暫し見つめあった後、互いに大声で笑った。
「ほな、仲良しさんに戻ろな。
さて、どうやら弁当もあるみたいやし、お相伴に預からせてもらいましょか」
すると、姫条君の傍にいた子供達がぎゃあぎゃあと騒ぎ出す。
「あ、兄ちゃん! 俺もサンドイッチ食べたい!」
「俺も俺も」
「お前ら、少しは静かにせぇ! ほら、手ぇ洗いに行くで。
じゃあ、こいつらと水道行ってくるわ。ちょっと待っててな」
姫条君はそう言って右手をひらひらと振ると、子供達を連れて水道の方へ歩き出した。私は笑顔でそれを見送る。
一時はどうなるかと思ったが、上手く仲直りができて本当に良かった。お互いにつまらない誤解をしていたのがよく分かったし、これなら今日だけでなく未来も明るそうだ。
私は急いで残りのサンドイッチを鞄から出し、姫条君達の帰りを今か今かと待った。 |
了
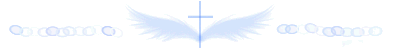
姫条君の台詞だけ先に書いて関西弁変換をお願いし……
それから暫く放っておいたSS。
最初からなかなか進まなくて
非常にだらだらとしてしまいました。何故かしら。
タイトルもいいのを思い付かなくて
仮タイトルそのままです。
姫条君のSSで、タイトル付けで満足しているのって一つも無いかも。
(20021229 UP)
|
|