【意地と後悔】
|
とある平日、所用で私が廊下を歩いていると、水道の前で腕組みをしている姫条君に会った。
「よ! 待ってたで」
「姫条君?」
彼とは登校時に校舎一階の昇降口で会っているのだが、その時は普通に挨拶を交わしただけだった。わざわざこうして私を待っていただなんて、一体何の用だろうか。
姫条君は子供っぽい笑みを私に向ける。
「他から聞いたんやけど、自分のクラス、明日調理実習なんやろ?」
「うん」
そう、明日の三、四時間目は女子だけが取る家庭科の授業があり、幾つかの班に分かれて調理実習をする。テーマは、ずばりお弁当だ。好きなメニューを班毎に決め、世間に溢れている冷凍食品を使わないで仕上げることになっている。しかも多くの生徒の提案と賛成により、希望者は二人分のお弁当を作っても構わないのだ。付き合っている“彼氏”がいる生徒は勿論、片思い中の人もそれを渡して頑張ろうと意気込み、この実習が発表された時の家庭科室は異様な熱気に包まれたのだった。
私が問いに頷くと、姫条君は私を肘で軽く突いた。
「なぁ──そのお弁当、俺にくれるやんなぁ?」
「……どうしようかな」
私は意地悪く呟く。
二人分を作っても良いと決まった時に、私の頭に浮かんだのは勿論この姫条君だった。彼は一人暮しをしているせいか、料理がとても上手い。時々、多く作り過ぎたと言って私にお裾分けをくれるので、いつも喜んでお誘いに乗っている。私自身は家で母親の家事の手伝いをする程度で、料理はあまり得意ではない。お弁当を作れなくもないが、簡単なものや冷凍もので埋まってしまいそうなので、今まで敢えてお返しをしてこなかった。だから今回の実習は、私にとって非常に良い機会だったりする。
しかし、素直にそれを言うのもつまらないと思った私は、つい意地悪をしてしまった。姫条君が困ったように眉を寄せる。
「何でも二人分作れるらしいやん。自分と俺で二人分、ほら丁度ぴったりやん! それでお昼を一緒に食べよう、なぁ?」
「ううん」
私は笑いを噛み殺しながら、わざとらしく悩んでみる。
「そんな殺生なぁ」
姫条君はやや演技がかった口調で言う。私は可笑しくて笑ってしまった。
「じゃ、またあとでね」
私は手を振って姫条君から離れた。意地悪をしても、結局私が彼にお弁当を渡すのは間違いない。彼が明日に自分用のお弁当を持ってこないよう、放課後までに本当のことを言うつもりだ。
せっかく姫条君に食べてもらうのだから、美味しいものができると良いなと私は思っている。既に先週の授業で、班毎にメニューを決めており、今日の放課後に班の皆で学校の裏にある食料品店へ出かけ、使う食材を選ぶ予定だ。買ったものを、明日の四時間目に合わせて店から家庭科室へ届けてもらうのである。だから班全員が同じ出来具合になるのだけれど、盛り付けや細かいところに力を入れたい。難しいけれど、姫条君をあっと言わせたいものだと私は心の中で気合いを入れていた。
その放課後。
食料品店へ買い出しに行くまで時間があったので、私は教室を飛び出した。後で姫条君に電話をしてお弁当の件を伝えても良いのだけれど、できれば直接言いたかったのだ。お弁当をあげると言った時に見られるであろう彼の笑顔を想像するだけで、私の心は弾み出す。
私は姫条君のクラスの教室へ駆け込んだ。しかし、残っていた生徒に彼がさっき出ていったと言われたので、慌てて廊下を走る。
すると、途中の踊り場に姫条君を見つけた。
「きじょ……」
だが、私は彼の名前を最後まで呼べなかった。姫条君のすぐ横に、奈津実ちゃんの姿があったからだ。
姫条君は私の声に気付くと、「お!」と片手を挙げて応じてくれた。けれども横の奈津実ちゃんの顔はとても怖い。私の介入を邪魔だと言わんばかりに、ギロッと睨んでくる。
私と奈津実ちゃんは、つい先日まで親友だった。正確に言えば、今も私はそう思っている。しかし彼女は、私が姫条君を好きで、しかもただの友達以上に仲が良いと知った途端、私にライバル宣言をしてきた。せっかく入学当初から親しくしてきたのに、彼女曰く私は“敵”になったそうだ。
奈津実ちゃんは、不愉快そうに顔をしかめた。
「あんた、まどかに一体何の用?」
「──ちょっと話したいことがあったの」
私の答えに、奈津実ちゃんがクスッと笑う。
「まさか、明日の調理実習で作るお弁当の件じゃないでしょうね」
「え?」
どうして奈津実ちゃんがそれを知っているのだろうと、私は驚いた。彼女は私と違って情報を掴むのが早いので、どうせ他の女子から話を聞いたのだろうが、何もわざわざ姫条君の前で牽制しなくても良いではないか。奈津実ちゃんには関係の無い話である。
私が反論しようとする前に、奈津実ちゃんが口を開いた。
「言っておくけど、まどかはもう駄目だからね。先約なんだから」
「?」
「実は、私のクラスも明日の一、二時間目に調理実習があるんだ。作るのはこっちもお弁当。同じ学校で、同じテキストを使って、同じ教師に教わっているんだから当然よね。
知らなかった?」
「……うん」
「まどかは、私の作ったお弁当を明日のお昼に食べるの! だから、今更あんたがのこのこ言いに来ても無駄なんだから。どうせ、まどかへの用事ってこのことだったんでしょう?」
私は返事をせず、奈津実ちゃんの横で頭を掻いている姫条君を見上げた。
「姫条君……」
「そうなん?」
困った顔をして尋ねる姫条君に、私は頷いて答えた。
「ごめんな。自分が俺に弁当をくれそうになかったから、こっちの話に乗ることにしてん。自分、昼間に俺がああ言ったからその気になってくれたん? それともあれはただの照れ隠しで最初っからこうするつもりやったとか? どっちにしてもこんな状況になるんやったら、もうちょっと待ってたら良かったなぁ」
無論、理由は後者だが、私にはそれを言う気力が無かった。ただただ首を左右にふる。
奈津実ちゃんがそんな私を眉を釣り上げて睨んだ。その後、姫条君に向かって叫ぶ。
「ちょっとちょっと、それってどういう意味? 聞き捨てならないじゃん!」
「ん?」
「私が言い出す前に、まどかがこの子にお願いしたの?」
「そうやで」
奈津実ちゃんの手がぶるぶると震えている。彼女は、姫条君が私にお弁当を所望したのが余程気に入らないらしい。
「とにかく、私がまどかのお弁当を作るんだからねっ! あんたがシャシャリ出る幕は無いの!」
奈津実ちゃんは更に大声で怒鳴った。周囲の生徒が、何事かとこちらを見ている。私は誰に言うでもなく、「何でもないから」と言い訳をした。
「そんな訳やし、自分には悪いことしたけど、ほんまごめんな」
姫条君は気を遣ってわざわざ私に謝ってくれたが、彼に非が無いのは分かっている。そう、一番駄目なのはこの私だ。
私は再度頷くと、のろのろと歩いてその場を離れる。背後で、奈津実ちゃんが鼻で笑ったのが聞こえた。
自業自得だと私は自嘲した。昼間に姫条君からお願いされた時に、素直に応じていれば良かったのだ。頼まれなくても最初から姫条君にお弁当をあげるつもりだっただけに、いくら悔やんでも足りない。しかも、私の代わりにあの奈津実ちゃんが作るという。チャンスをみすみす逃してしまっただなんて、最低だ。
それに、私は別のことでもショックを受けていた。奈津実ちゃんが、姫条君を“まどか”と下の名前で呼んでいたのである。私もかつて一度だけ、姫条君をそう呼んだことがあった。しかし彼は、自分で「女っぽい」と言うその素敵な名前で他人から呼ばれるのがいやだったのか、すぐに止めてくれとお願いされたのである。それなのに先程の姫条君は、奈津実ちゃんから下の名前で──しかも呼び捨てにされても全く動じていないようだった。あの会話で、奈津実ちゃんは何回“まどか”と呼んだだろうか。その度に、私は驚きと共に惨めな思いをしていた。つい先日まで、奈津実ちゃんも彼を名字で呼んでいたのに、いつの間にか私と彼女の差は開いていたらしい。
重い足を引き摺りながら、私は階段を上がって自分の教室に戻った。楽しみだった調理実習が一転、憂鬱になったのは言うまでもない。
それから私は、班の皆と共に調理実習の為の買い出しをした。そこで分かったのだが、私以外の女子は全員彼氏持ちだった。当然、皆は自分の分と彼氏の分……つまり二人分を作る。姫条君に断られた私は自分のだけで充分なのだけれど、会話の途中でつい見栄を張ってしまい、必要もないのに二人分作ることになった。ただ、奈津実ちゃんに知られては煩いので、皆にこのことを黙ってほしいと頼み込む。
「あ、もしかして姫条君にあげるんでしょう? あんた達が凄く仲が良いって、あちこちで噂になっているもんね。煩く騒がれるのが好きじゃないんだ?」
班の××という名前の女子が私にそっと耳打ちする。まさか真実を言う訳にはいかず、私は適当に返事をして誤魔化した。そうだと嘘を吐かなかったのは、私なりのプライドの表れだった。
次の日、私は一層重くなった気持ちを抱えて登校した。
廊下を歩いている途中で姫条君に会ったが、彼と会話を楽しむ気分にはなれなかった。
「おはようさん。自分、どうしたん? 何か暗いで」
姫条君とのことでこうなったのだと言いたいところだけれど、私はグッと我慢した。彼に文句を言うべき問題でないからだ。
代わりに、引き攣った顔で頷く。
「そんな顔してたら運が逃げていくで。“笑う門には福来る”、これが人生の基本や!」
私は返事もできず、あいまいに笑って姫条君から逃げた。別れ際、彼はまだ何か言い足りなさそうにしていたけれど、追いかけてこなかったのでそのまま放っておいた。
一時間目の授業が始まった時、教室で現国の授業を受けていた私はとても悲しくなっていた。今頃、家庭科調理室では、奈津実ちゃんが姫条君の為にお弁当をせっせと作っているはずである。私がきちんと返事をしなかったことで、言わば“棚からぼた餅”の幸運を得た彼女は、幸せいっぱいで実習に励んでいることだろう。献立では、班の皆に無理を言って姫条君好みのおかずを入れたのか? わざとらしくハートマークが溢れているのか? 私の想像は尽きなかった。頭に奈津実ちゃんの姿を浮かべては、こうなるのは私だったのにと今更嘆き、胸を痛める。
二時間目の授業が終わって、私が家庭科調理室へいよいよ移動しようとする時に、廊下で奈津実ちゃんとばったり会った。彼女は眉間に皺を寄せて、私をまた睨んでくる。
「……ま、せいぜい頑張りなさいよ」
「奈津実ちゃんは上手に出来たの?」
私の問いに、奈津実ちゃんはフフンと笑う。
「当然。だってまどかに食べてもらうんだもの。気合いから違うわよ。あんたは可哀想ねー。誰にも食べてもらえないだなんて。
あ、どうせなら多めに作って、運動部の男子にでもあげれば? そいつらなら、あんたのお弁当でも喜んで食べてくれるんじゃない?」
「……」
奈津実ちゃんは手加減がない。キツい言葉が、私を何度も突き刺していく。
これ以上彼女と一緒にいても自分が傷付くだけだと分かり、私は別れの挨拶もせずに歩き出した。
さて、私の本番の実習となる三時間目の作業は、悲しいぐらいに上手くいっていた。皆の意見で、自分達女子より男子好みに作った献立は、きじ焼き弁当である。きじと言っても、使うのはただの鳥モモ肉だ。皆は、ご飯と別におかずとして鳥肉を盛っていたが、私はどんぶり風に味の濃いものとご飯を一緒に食べたかったので、ご飯を浅く盛った上に揉み海苔をまんべんに散らし、鳥肉を乗せた。他のおかずは、筍とつくねの甘煮、だし巻き卵、人参の薄味グラッセ、ホウレン草のおひたしだ。彩りも良く、ボリュームもたっぷりある。デザートにオレンジゼリーも付けた。ちなみに入れ物のお弁当箱は、各自持参である。
四時間目の終了と共に実習も終わった。皆は、出来上がったばかりのお弁当を幸せそうに胸に抱き、いそいそと家庭科調理室を出ていく。今から彼氏のところへ行くのだろう。それを羨ましく思いながら、私も二人分のお弁当を持って教室へ向かった。そして私は皆に見られないよう注意を払いつつ、お弁当の一つを鞄の中にしまう。きっとこれは私か尽の晩ご飯となるに違いない。もう一つは、これから私が食べる昼食だ。皆は彼氏のところに行っているし、一人でポツンと食べるのはあまりにも淋しいので、裏庭に行ってこっそり食べようと決めた。
移動する途中、姫条君のクラスに入っていく奈津実ちゃんを見かけた。辛くて、思わず目を逸らす。幸い、奈津実ちゃんには気付かれなかったようなので、そのまま無視して通り過ぎた。
裏庭は昼休みだというのに閑散としていた。私は、日当たりの良い場所を見つけて腰を下ろす。
お弁当の蓋を開けた。辛口の赤い味噌で味を付けた鳥肉が、悲しいぐらいに美味しそうである。
「いただきます」
小さくそう呟いて、私は箸を持つ。
見た目通り、お弁当はとても美味しかった。難を言えば、他の女子が担当した卵焼きが出汁を少し入れ過ぎた上に巻きが甘かったが、充分に食べられるものだった。私が作った煮物は、味も触感も良かったのでホッとする。もしも酷い出来であったのなら、彼氏に食べさせる他の女子から文句が出かねないからだ。
お弁当箱がすっかり空になった時、背後の茂みがガサッと鳴った。誰かが来たのかと私が後ろを振り返ると、息を切らせた姫条君がそこに立っていた。
「こんなところに居たんか。めっちゃ探したんやで。良かった、見つけられて」
姫条君は、はぁっと大きく息を吐いて破顔した。いかにもホッとしたという表情に、私も嬉しくなる。だが、私は彼の口唇に赤いものを見つけてしまった。現実を見せられて、私は急に冷めた。
私は感情を押さえながら言う。
「……姫条君、口元にケチャップが付いてるよ」
「え、ほんま?」
姫条君が右手の甲でごしごしと口を拭く。私は冷ややかな目でそれを見つめた。奈津実ちゃんが作ったお弁当を食べた跡を見るだなんて、最悪である。
しかし、姫条君は全く気にしていないようだった。私の周囲をきょろきょろと見回している。
「どうしたの?」
「いや、もう一個のお弁当、どうしたんかなぁと思ってん」
「な、何でそれを知ってるの?」
私は慌てた。
「自分と同じ班の子を探し出してん。XXとかいう名前やったかなぁ。その子から、自分がお弁当二人分作ったって聞いたから、実際に確かめにきてん」
姫条君は、私があれからどうしたのかを気にしてくれたらしい。それは嬉しかったが、話したという××が余計なことを言っていないかと冷や冷やした。食材の買い出しの際に私に囁いたように、彼女は私が姫条君にお弁当をあげるものだと勘違いしていたからだ。
他人から変な形で伝わるよりはと思い、私は事情を姫条君に説明した。班にいる他の女子が全員彼氏持ちだったこと、話の展開上でつい見栄を張ってしまったこと、お弁当は誰にもあげずに教室の鞄の中に隠してあること……。
私の話を全部聞き終わった姫条君は、何故か安心しているようだった。
「ということは、自分がその弁当まだもってんのか。
良かったー……残ってて。他の男子に食われたんかと思ったら、俺、いてもたってもおられへんかって」
他の女子のお弁当を食べたくせに、と私は心の中で悪態をつく。それには気付かないようで、姫条君は顔をほころばせた。
「自分さえ良かったら、そのお弁当、俺にくれへんか?」
「え? だって姫条君、奈津実ちゃんのをさっき食べたんでしょう? もう要らないじゃない」
口に付いていたケチャップは何だったのだという意味を込めて、私は冷たく言った。これまで姫条君と何度も一緒に食事を取ったけれど、彼の食欲は人並みである。お弁当を二つも食べるだなんて無理だ。
しかし、姫条君は首を振った。
「晩飯にすんねん。流石に今、二つも食べられへんし」
「そんな……。私に気を遣って、無理して食べなくてもいいよ」
私は、自分の態度が卑屈かと一瞬思ったけれど、そう言わずにはいられなかった。姫条君に同情されて食べてもらうぐらいなら、家で尽にあげた方がマシである。
「無理ちゃうで。俺はほんまに自分のお弁当食べたいねん。実は、自分があんまり悲しそうな顔するから、一度はあっちを断ろうと思ったんやけど。でもそうしたら今度はあっちに対しても失礼やんか? 女の子にぬか喜びさせんの嫌やねんか。だから自分のこと思いつつ、その弁当食べた。
そやけど、自分の手料理を食べれるいい機会やったのにそれを逃したなって、これでも落ち込んだやで。そうしたら自分がもう一つ作ったらしいって聞けたし……。誰かに食われる前に俺が確保せな!と走ってきてん」
本当を言うと、階段の踊り場で姫条君に断られた時に、彼が奈津実ちゃんのをキャンセルしてくれないかと私は心のどこかで望んでいた。そして結局彼女を優先させた姫条君に、私は落ち込んだのである。だが、姫条君の今の話を聞いて、考えが少し変わった。姫条君は、一見軽薄そうだけれど根はとても真面目だ。そんな彼だからこそ、奈津実ちゃんを傷付けられなかったに違いない。一度は私を優先してくれようとしたという彼の言葉に、私は胸が詰まった。
私はお弁当に対する今までのわだかまりを吹っ切って、笑顔を向けた。
「つまんないことを言ってごめんね。
実は、せっかく作ったのこれが弟の晩ご飯になるかと思うと、少し憂鬱だったの。姫条君が食べてくれると、本当に嬉しい」
「ああ。俺の方こそ、早合点してごめんな。自分のお弁当が無事食べられるなんて最高や」
姫条君も喜んでくれている。見栄を張ったけれど作って良かったと、私はしみじみ思った。
しかし、私にはまだ不満があった。そう、姫条君への呼び掛け方だ。
謝りついでに、私はここで思い切って言ってみることにした。
「ねぇ、姫条君。私、気になっていることがもう一つあるんだけど」
「ん、何? 食べ物好き嫌いやったら、前に教えた通りやで」
「そうじゃなくて。
どうして姫条君は、奈津実ちゃんに下の名前で呼ばせているの? 私が以前に一度そう呼んだ時、姫条君ってば嫌がったじゃない」
「それか。もしかして自分、妬いてくれてんの?」
うっ……と私は言葉に詰まった。素直に頷けず、小さな声で理由を言う。
「だって、私もそう呼びたかったんだもん。目の前でされて、ちょっと悔しかったから」
すると、姫条君の手が伸びてきた。優しく私の髪を梳いてくれる。
「自分、かわいいなぁ。あれはな、あいつが勝手に呼び始めよってん。俺が止めてくれって言っても聞いてくれへんし。自分は、俺が嫌やって言うたから名字で呼んでくれてんねんのやろ? あいつもそういう気遣いが出来るようになったらいいんやけど」
「私、姫条君が奈津実ちゃんだけにそう呼ばせているのかと思った」
私の呟きに、姫条君が大きく首を振る。
「ちゃうで! そこ、誤解されると困るからしっかり訂正しとく。俺は許可した覚えないし。
だけど、自分がそう呼びたいって言うんならそれでもいいで、俺。自分にやったら構わへんし」
「本当?」
「あぁ」
私は嬉しくてたまらない。本人にちゃんと確認して良かったと、心の底から喜ぶ。
許可も下りたことだし、早速呼んでみようと私は咳払いをした。
「では、いきます。
──まどか君」
声に出すまでは緊張したけれど、意外に簡単に言えた。
姫条君が笑う。
「呼び捨てでもいいで」
「……まどか」
「おう」
「な、何か照れるね」
私は恥ずかしさで顔に血が昇るのを感じた。
「そうか?
あぁ、でも自分に名前で呼ばれんのもいい気分やな。もう一回呼んでくれへん?」
「まどか」
「はいはいー」
この予期せぬ展開に、私は本当にびっくりしていた。私が姫条君を“まどか”と下の名前で呼び捨てにできる日など、まだまだ遠いのだろうと今まで思っていたのだ。何だか急に姫条君──いや、まどかと親しくなったようで、凄く嬉しかった。目に見えない大きな壁を超えられたような気がしていた。
しかもこの直後、姫条君も私を呼び捨てで呼んでくれた。ただそれだけなのに、本当に幸せである。
私はお弁当箱をしまい、まどかと共に立ち上がった。これから教室に行き、こそこそと隠れてしまったお弁当を彼に渡さなければ。
色々あったが、終わり良ければ総べて良しである。もう二度とつまらない意地悪をしないと、私は心に強く決めた。 |
了
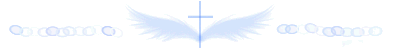
まどかスキーには奈津実ちゃんのうけが宜しくないようで
一度そういうのを盛り込んでみようと思ったんです。
奈津実ちゃんをすっかり悪役にしてますが
彼女とのEDも好きな私には少し心苦しかったりします。
(20021006 UP)
|
|