【きっかけ】
|
今から約二ヶ月前、なかなか行けないと噂のある人気ロックバンドのチケットの争奪戦に、奈津実ちゃんが見事に勝った。私の分も取れたというので、甘えてさせてもらうことになった。
今日は、そのライヴ当日である。会場は市内にあるイベントホールだ。
どうせなら入り待ちも出待ちもしようということになり、私と奈津実ちゃんは駅前で午前九時に待ち合わせをした。ファーストフードの朝メニューを食べ、鋭気を養って会場の裏口へ行く。私達の他にもファンがおり、その子達と色々喋りながら待っていると、メンバーの乗った車が目の前を通っていった。キャアキャア言って、私も奈津実ちゃんも懸命に手を振った。
その後、開場時間まで市内のショッピングモールで時間を潰す。お昼ご飯を食べた後、ウィンドーショッピングやお茶をして楽しんだ。
六時半から始まったライヴは、最初からファンの熱狂に包まれた。ライヴそのものもとても良く、私はアンコールで演奏されたバラードで涙ぐんでしまったほどだ。
終演後、その熱気も冷めぬうちに、私達は再び会場裏口へ急いだ。無事に再び通り過ぎるメンバー車を見て満足する。
朝に待ち合わせたのと同じ駅前で、私と奈津実ちゃんはようやく別れた。
楽しかったライヴを頭の中で思い返しながら、私はスキップを踏みながら帰宅する。
だが、私が家に着いて玄関のドアを開けた途端、顔をしかめた母親が今居間から飛んできた。
「こんなに遅くなるまで一体どこに行っていたのっ?」
「ライヴだよー。藤井さんがチケットを取ってくれたから、一緒に行くって言ったじゃない」
「今、何時だと思ってるの!」
私は時計を見た。現在の時刻は十時半である。ライヴ自体が終わったのは九時前だったが、出待ちをしたのですっかり遅くなってしまった。私が悪いのは明確なので、素直に謝る。
「ごめんなさい」
しかし、母親は強い口調で続ける。
「氷室先生から何度も電話があったわよ! 来週の日曜日に課外授業を行なうんですって。学校として団体で行くから、事前に参加人数を会場に伝えなくちゃいけないって、クラスの生徒さん一人一人に出欠を聞いているそうよ。
まったく……携帯に連絡しようと掛けてみたら、部屋に置きっぱなしだし」
「え?」
私は持っていた鞄の中を慌てて探った。入れたつもりだった携帯電話は、確かに無い。
「そ、それで氷室先生からは何回ぐらい電話があったの?」
「五回ぐらいかしら。日中、私は出かけていたから、家にいた尽が電話を取ってくれていたのよ。尽は事情を知らないから『姉はすぐ帰ると思います』って返事をしたらしくて。夜八時に電話があった時に私が出て、九時過ぎないと帰らないと言ったんだけどねぇ……。ついさっきも電話があったのよ」
携帯電話を家に忘れた日に氷室先生から電話が掛かってくるだなんて、悲しい展開である。氷室先生の課外授業は、楽しい上に勉強になるのだ。それに加え、私自身が先生に強い憧れ……というか恋心を抱いているので、一年の頃から欠かさず行っている。しかも今のクラスの中で、私だけが皆勤だ。私の不在のせいで、電話口で不愉快そうに眉を寄せる先生の姿が私の頭に浮かぶ。
「お母さん、どうしよう」
「明日の朝一番で、氷室先生にちゃんと謝りなさいよ!」
「それは勿論だけど……」
本当は今すぐにでも先生に電話をしたかった。だが、私は先生の電話番号を知らないのである。携帯と違い、家の電話には着信履歴が残らない。そういうサービスに家が加入していないのだ。もしかしたらと僅かな望みをかけ、学校に電話をしてみたけれど、案の定留守電のテープが回っているだけだった。
楽しかった気分は消え、私は不安のまま自室に向かう。途中、二階の廊下で隣の部屋の尽に会った。
「姉ちゃん! 氷室先生から何度も電話があったぞ! 目ぇ付けられて大変だな」
いつもは言葉を返すのだが、流石に今日はそんな気にはなれなかった。尽を無視し、黙ってドアを開けて中に入る。
部屋に入るなり、私は鞄を机の上に投げた。そのままベッドにダイブすると、枕元に私の携帯電話があるのが見えた。画面は着信有りとなっており、見ると自宅からである。母親が掛けた分だ。
それから暫くの間、私はベッドの上で氷室先生からの電話をひたすら待った。しかし、時間が時間なので電話機は全く鳴らない。気になったのでクラスの友人にメールで尋ねたところ、やはり氷室先生から出欠の問い合わせの電話があったそうだ。でも私は行かないから、という返事に、私は勿体無いと強く感じる。
日付けが変わったので、私はようやく腰を上げた。学生鞄に明日の教材を詰める。宿題や授業の予習は、昨日のうちに全部済ませてあるので支障無い。用意を終えて風呂に入り、ベッドに入った。
明日……いや、今日のこれからを思い、私はひどく憂鬱だった。
さて、朝早く目覚めた私は、朝食もそこそこに急いで登校した。学園の開門と同時に敷地内に入る。この時間だと部活動の朝練をする生徒達がいるぐらいで、学校はまだ閑散としていた。
私は昇降口から入ると教室に鞄を置いて、教職員玄関へ急いだ。氷室先生の靴箱を見たが、まだ来ていないらしい。何としても早く謝りたかったので、私はすぐ傍の廊下で待つことにした。
十分後、その氷室先生が颯爽と玄関に入ってきた。廊下に待機していた私は慌てて移動し、先生の前で頭を下げた。
「氷室先生、おはようございます! き……きき昨日はお電話を何度も頂いたそうで、その……申し訳ありませんでしたっ!」
「おはよう」
氷室先生の挨拶を聞いて、私は顔を上げた。先生は靴をとっくに履き替え、私を見下ろしている。その顔に怒りは無い。どちらかと言えば穏やかで優しい感じがするような気もするが、ただの無表情だと言われたらそう頷くしかない程度だ。
「こんな所で立ち話も何だ。
来なさい」
そう言うと、氷室先生は私の横をすり抜けて廊下を渡り、さっさと職員室に入っていく。私も慌てて続いた。
早朝の職員室は静かだった。中には事務員が一人だけいたが、山積みになった本を抱えてすぐ外へ出ていく。
氷室先生は自分の椅子に座った。流石、氷室先生だけあって、机の上が非常に綺麗である。すぐ横の教師など、どこに何が置いてあるか分からないぐらいの散らかり様で、いいコントラストになっていた。
私は氷室先生の横に立った。まず何から言おうかと、焦りながら必死に考える。
すると、氷室先生は机の上にある書類入れを開けて、中から一枚の紙を出して私に渡した。見ると、課外授業の予定が綺麗な硬筆で書かれている。
「今週末の日曜日に課外授業を行なう。場所は市内のプラネタリウムだ。季節の夜空を観察し、後でレポートを提出してもらう。
出欠はいつものように生徒の自由だが──君は真面目な生徒であるし、これまで全部参加しているので、今回も出席としておいた。予定は大丈夫か?」
「は、はいっ! 勿論です! もしまだ間に合うのなら、絶対にお願いしようと思っていましたから……」
良かった、と私は胸を撫で下ろした。プラネタリウムに行けないことよりも、欠席のせいで先生の心証が悪くなるのではないかと思っていたからだ。それにいくら自由参加とはいえ、皆が行くのに私が行かないなんて辛過ぎる。先生という、友達のように気軽に時間を一緒に過ごせない相手なのだから、少ない機会を何としても有効に利用したい。
安堵して喜ぶ私を見て、先生はフッと笑った。
「日曜日の集合時間と集合場所は、渡した紙にある通りだ。遅れないよう、注意しなさい」
「有難うございます。気を付けます」
私にとっては、課外授業に関わる全てがチャンスである。どんなことがあっても、遅れる訳にはいかない。
「ところで……」
先生が眼鏡の縁に手を掛けて言った。
「昨晩は、あんなに遅くなるまでどこへ出かけていたのだ?」
とうとう来たと私は思った。どうやら先生は、電話を何回も掛けさせられたこと自体は怒っていないようだ。しかし、これからお説教をされるかもしれない。夜遅くまで街で遊ぶなど、生真面目な氷室先生からすると許せないはずだ。嘘を吐いて誤魔化すべきかと考えたが、尽はともかく母親が電話で先生に詳細を告げた可能性もある。やはり素直に言うべきだと、私は覚悟を決めた。
「──友達にロックバンドのコンサートに誘われまして、市内のイベントホールにいました」
「コンサートなら、八時や九時に終わるだろう。それからまた他の場所に遊びに行ったのか?」
「実はあまりに楽しかったので、終演後に会場裏口へ行って、車で退出するメンバーを見送ったんです。それからはばたき駅前で友達と別れて、まっすぐ帰宅したんですけど……家に入るなり、母に叱られました」
私は首をすくめた。出待ちをするのは最初から決まっていたことだったが、それ以外は全部本当だ。しかし実際に口にすると安っぽい理由である。ライヴの後にカラオケに行ったと嘘を吐いた方が、余程真実味があった。
「そうか」
けれども、私の言葉を聞いた先生は顔をほころばせた。
「先生?」
「私にも経験がある。あれは××が指揮をした△△フィルオーケストラだったか。感激をどうしても伝えたくて、幼い私は親の制止の手を振り切って楽屋まで押しかけた。子供だということで、その場にいた係員も多めに見てくれたが。
君も同じような気持ちだったのだろう?」
「はぁ……」
幼い氷室先生が抱いた高尚な気持ちではなく、私と奈津実ちゃんの場合は単なるミーハー心からだが、ここは素直に返事をすることにした。氷室先生が満足げに頷く。
「それなら仕方あるまい。
ただ、遅くなるならご両親にきちんと伝えるべきだったな。お母様が私に随分恐縮されていた」
「はい、すみません。母から私の携帯電話に連絡があったようなのですが、電話機そのものを私が部屋に置いていってしまったんです。ちゃんと持っていれば、先生にもご迷惑をお掛けしないで済んだのですが。いつもは絶対に持っていくのに、よりによって昨日だけ忘れたんです」
「掛けている私の方が申し訳ないほどだった。お母様に宜しく伝えてほしい。
それと、君の弟君とも初めて話したが、彼も礼儀正しくて私は大変気分が良かった。ご両親は躾をちゃんとなさっているのだな」
「……」
それは絶対に変だ。おそらく尽は相手が教師だということで、猫を被ったのだろう。普段の尽を見ている私からすれば、礼儀正しいなんて言葉は絶対に出てこない。
「とにかく、今後は家に不在の時でもきちんと連絡が取れるように気を遣いなさい」
「はい」
返事をした後、私の頭にふと案が浮かんだ。
どうしようかと一瞬悩んだが、この機会を逃すと一生言えないかもしれないので、勢いがてら口にする。
「あの、先生。お差し支えなければ、今後の連絡は私の携帯電話に直接頂戴したいのですが。
出かける時に、前もって親にきちんと所在を明らかにするのは勿論ですけど、今回のようにまた先生にご迷惑をお掛けするのは絶対に嫌なので」
「ふむ……」
もしかしたら怒られるかと思ったが、先生は普通の顔で思案している。
「いいだろう。今、携帯電話を持っているか?」
「はい」
やった!と私は鼻息荒く返事をし、制服のスカートのポケットから電話を取り出した。先生も鞄の中から出す。私は先生の携帯電話を初めて見たが、飾りなど何もないシンプルな紐だけのストラップだった。
「ええと、私の番号は……」
氷室先生が、私の言う通りの番号を携帯に打っていく。そこから放たれるピッピッという電子音が、これが本当に現実なのだと私に教えてくれた。
「では、私の番号も教えておこう。見ず知らずの番号からの着信は、出ない方が良い」
「は、はいっ!」
私は緊張しながら、先生の携帯電話の番号をメモリーに登録した。最近はいたずら電話が多いので、非通知や知らない番号の電話は無視することが多い。だが、私は先生の番号まで教えてもらおうとは思っていなかった。聞けたら無論嬉しいが、ここまで望んでいなかったのである。何と嬉しい展開だろうか。
他に誰もいない職員室で氷室先生と電話番号の交換……考えてみれば、物凄いシチュエーションである。氷室先生の携帯の電話番号を知っている生徒なんてそう滅多にいないだろうが、この事実以上に私が先生の特別な生徒になれたような気がした。声にこそ出さなかったが、私は心の中でキャーッと叫ぶ。
氷室先生は携帯電話を鞄に戻すと、一度咳払いをした。
「では、もう宜しい。教室に戻りなさい」
「はい。本当にご迷惑をお掛けしました」
私は再度頭を下げた。
「それももういい。君も私にそれを言う為に、朝早くから登校して大変だっただろう。私は電話の件を少しも気にしていないのだから、君がこれ以上謝る必要は無い」
「……有難うございます」
ようやく安心して、私は笑った。見ると、先生も穏やかに微笑んでくれている。夜、眠る前に抱いていた不安が全部吹っ飛び、私は心の底から安堵した。
職員室を出てドアを閉めた途端、私は飛び上がって喜んだ。付近にいた生徒が、怪訝そうな顔をする。しかしそれを全く気にせず、私は手元の携帯電話をニヤニヤしながら見た。細かく震える手でボタンを操作する。画面に、先程教えてもらったばかりの氷室先生の電話番号が出た。
早速、通話のボタンを押す。
数秒待った後、氷室先生が出た。
「……どうした?」
「あ、はい。氷室先生にちゃんと電話が繋がるかどうかの確認です!」
「くだらないことをしていないで、早く教室に戻りなさい」
「すみません」
私は慌てて電話を切った。流石にこれは調子に乗り過ぎたようだ。しかしこれで、教えてもらった電話番号で確かに先生に繋がるかと思うと、嬉しくて仕方がない。元々嘘を言われたとは微塵も思っていなかったけれど、こうして実証できると安心があった。
私は氷室先生の番号が出ている画面を見つめながら、ゆっくりと歩いて教室へ向かった。
階段の踊り場に上がった時、少し気になることが頭をよぎったので足を止める。
私は、女友達と携帯電話をよく見せ合う。もしも彼女達に氷室先生の電話番号がここに登録されていることを知られたら、色々面倒ではないか。馬鹿正直に氷室先生と名を打ってあるが、今のうちに変えておくべきだろう。
暫く考えて、やはりこれしかないかと私はボタンを二つ押した。数字で0と1──説明するまでもなく、先生の名前の略だ。目敏い人は気付くかもしれないが、私の思いを知られなければ平気なはずである。名前をダイレクトに入れておくより安心だった。
私は、重大な秘密を先生と共有できたような気になった。そして、一日も早くこの電話番号が有効に使える時が来ないかと、心の中で強く祈りながら教室へ再び歩き出した。 |
了
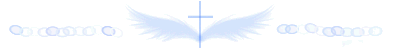
友達ならともかく、先生から携帯に直接電話があるなんて絶対に変……と思い、
ゲームを補足する気分で書いてみました。
ゲームでは、先生に電話が掛けられないのが辛い〜〜。
デートに誘えたら良いのにと、攻略する度にいつも思っています。
(20021009 UP)
|
|